|| 極限演算子と積分演算子の関係
「極限」と「積分」が交換できる条件
スポンサーリンク
目次
極限「無限を有限で表現する方法」
上限下限「極限っぽいけど異なるやつ」
上極限下極限「上限下限の数列を作って収束させる操作」
極限の線型性「斉次性と加法性を両方持つ」
極限の斉次性「定数の掛け算部分の取り外し」
上限と下限では「符号が + なら成立する」
極限の加法性「 f(x+y)=f(x)+f(y) の形」
上限と下限では「単調増加などの前提が必要になる」
定数の極限「極限演算子での定数の振る舞い」
ルベーグ積分「測度と上限で定義する方法」
積分の単調性「関数の大小と積分の大小」
リーマン積分の単調性「リーマン和の極限」
ルベーグ積分の単調性「単関数積分の上限」
非負単関数積分の単調性「ルベーグ積分の基礎」
非負可測関数積分の単調性「ほぼ最終的な結論」
一般の可測関数積分の単調性「最終的に欲しい結論」
連続関数の積分「極限と積分が交換可能」
項別積分の定理「非負単関数の積分の場合」
単調収束定理「非負可測関数の積分の場合」
Fatouの補題「非負可測関数の積分と下極限」
優収束定理「一般の可測関数かつ広範囲」
Fatou-Lebesgueの定理「優収束定理の一般化」
極限 Limit
この記事の主役はこれなので
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to \infty} a_n &=& α \end{array}
これが分かっていないと
( ↓ は左から順に具体的な値が決まる)
\begin{array}{ccc} \forall ε & \textcolor{skyblue}{\Bigl(} & \exists N & \textcolor{pink}{\Bigl(} & \forall n≥N & \Bigl( & |a_n-α|<ε & \Bigr) & \textcolor{pink}{\Bigr)} & \textcolor{skyblue}{\Bigr)} \end{array}
かなり辛い内容になっています。
( ε は 0 ではない正の実数で n,N は自然数)
ε\text{-}N 論法を軽く解説
↑ の見た目はかなりえぐいですが
中身それ自体はそんなに難しくないです。
\begin{array}{lcc} \displaystyle \left| \frac{1}{n} - 0 \right|<10^{-10} && 10^{10}<n \\ \\ |a_{n_*}-α|<ε_* && N_*≤n_* \end{array}
まずこれは
「定数 ε_*,N_*,n_* 」の状態で正しいという主張
\begin{array}{ccclcr} & & & |a_{n_*}-α|<ε_* && N_*≤n_* \\ \\ & & \forall n≥N_* & |a_{n}-α|<ε_* && N_*≤n \\ \\ & \exists N & \forall n≥N & |a_{n}-α|<ε_* && N≤n \\ \\ \forall ε & \exists N & \forall n≥N & |a_{n}-α|<ε && N≤n \end{array}
最終的な論理式は
そこから順番に一般化してるだけで
\begin{array}{ll} 全てのnで & |a_{n}-α|<ε_* & が成立 \\ \\ 全てのnで & |a_{n}-α|<ε_* & が成立 & そんなNが存在 \\ \\ 全てのnで & |a_{n}-α|<ε & が成立 & そんなNが存在 & これが全てのεで成立 \end{array}
それ以上でもそれ以下でもありません。
(最も左の記号から具体的な値が入る)
上限下限 Superior Inferior
これは「極限」と似た概念で
似たような性質を持つんですが
\begin{array}{ccc} 上限である &⇔& 上界の最小元である \\ \\ 下限である &⇔& 下界の最大元である \end{array}
定義がちょっと複雑で
(以下 n,N,ε は ↑ と同じで a_n,α も実数)
\begin{array}{lcl} \forall n \,\, a_n≤α && 上界の要素である \\ \\ \forall ε \,\, \exists N \,\, α - ε < a_N && 上界の最小元である \\ \\ \\ \forall n \,\, α≤a_n && 下界の要素である \\ \\ \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N < α + ε && 下界の最大元である \end{array}
単純な形では
「極限」の性質を満たしてくれません。
(絶対値で定義されてないため正負が関わる)
下極限や上極限などでの表現
この「下限上限」の表現には
\begin{array}{rcc} \displaystyle \sup_{N≤n}\{a_n\} &=& α_N \\ \\ \displaystyle \inf_{N≤n}\{a_n\} &=& α_N \end{array}
こういったものもあって
これは当然
\begin{array}{lcl} \forall n \,\, a_n≤α && 上界の要素である \\ \\ \forall ε \,\, \exists N \,\, α - ε < a_N && 上界の最小元である \\ \\ \\ \forall n \,\, α≤a_n && 下界の要素である \\ \\ \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N < α + ε && 下界の最大元である \end{array}
↑ とは異なるわけですが
どんな感じに定義されてるか曖昧ですよね。
まあ「極限」の定義を理解していれば
\begin{array}{ccclcr} & & & |a_{n_*}-α|<ε_* && N_*≤n_* \\ \\ & & \forall n≥N_* & |a_{n}-α|<ε_* && N_*≤n \\ \\ & \exists N & \forall n≥N & |a_{n}-α|<ε_* && N≤n \\ \\ \forall ε & \exists N & \forall n≥N & |a_{n}-α|<ε && N≤n \end{array}
なんとなーく想像できるとは思うんですが
実際、わりとそのままです。
\begin{array}{lr} & a_{n_{≥N}}≤α_N \\ \\ \forall n≥N & a_{n}≤α_N \end{array}
「上界である」はこのようになっていて
\begin{array}{ccl} & & α_{N} - ε^* < a_{n_{≥N}} \\ \\ & \exists n≥N & α_N - ε^* < a_n \\ \\ \forall ε & \exists n≥N & α_N - ε < a_n \end{array}
「上界の最小元である」は
こんな感じになっています。
α_N を定数として定める N は
「定数」として定義されていて
\begin{array}{ccc} α_N &=& \sup\{ a_n \mid N≤n \} \end{array}
この段階では量化されません。
(ただし N 自体は自然数なら任意にとれます)
下極限と上極限
以上のことから
\begin{array}{rcr} \displaystyle \limsup_{n\to\infty} a_n &=& \displaystyle \lim_{N\to\infty} \sup_{N≤n}\{a_n\} \\ \\ \displaystyle \liminf_{n\to\infty} a_n &=& \displaystyle \lim_{N\to\infty} \inf_{N≤n}\{a_n\} \end{array}
「上極限・下極限」を意味する
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \sup_{N≤n}\{a_n\} &=& L \end{array}
この演算の中身は
\begin{array}{ccc} \displaystyle \left| \inf_{N_*≤n}\{a_n\} - L \right| &<& ε^* \end{array}
「 N を固定して上限を見つける」ところから始まり
\begin{array}{ccc} & & & \displaystyle \left| \inf_{N^*_{≥N_{↓}}≤n}\{a_n\} - L \right| < ε^* \\ \\ & & \forall N≥N^*_{↓} & \displaystyle \left| \inf_{N≤n}\{a_n\} - L \right| < ε^* \\ \\ & \exists N_{↓} & \forall N≥N_{↓} & \displaystyle \left| \inf_{N≤n}\{a_n\} - L \right| < ε^* \\ \\ \forall ε & \exists N_{↓} & \forall N≥N_{↓} & \displaystyle \left| \inf_{N≤n}\{a_n\} - L \right| < ε \end{array}
ここから一般化される形で定義されます。
(独立して見た方が分かりやすい)
極限の線型性
この記事では
「極限」「上限下限」を意味する
\begin{array}{lcc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} a_n &=& α \\ \\ \displaystyle \sup\{a_n\} &=& α \\ \\ \displaystyle\inf\{ a_n \} &=& α \end{array}
これらの演算子を多用します。
その中でも
「線型性」は特に基礎的な操作になるので
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \Bigl( c_a a_n + c_b b_n \Bigr) &=& \displaystyle \lim_{n\to\infty} \Bigl( c_a a_n \Bigr) + \displaystyle \lim_{n\to\infty} \Bigl( c_b b_n \Bigr) \\ \\ &=& \displaystyle c_a \lim_{n\to\infty} \Bigl( a_n \Bigr) + \displaystyle c_b \lim_{n\to\infty} \Bigl( b_n \Bigr) \end{array}
これを問題無く行えるよう
こうなることをきちんと確認しておきます。
(こうならない演算が普通にある)
線型性に必要な要件
以下のような性質のことを
\begin{array}{lcl} f(αx+βy) &=& αf(x) + βf(y) \end{array}
「線型性」と言うんですが
実はこれの根元に来るのは
「斉次性」「加法性」という性質で
(線型性の形から明らか)
\begin{array}{lcl} f(αx)&=& αf(x) && 斉次性 \\ \\ f(x+y)&=&f(x)+f(y) && 加法性 \end{array}
「線型性」の証明を行うには
これらをそれぞれ証明する必要があります。
極限の斉次性
これは直感的に明らかな性質ですが
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} c a_n&=& \displaystyle c \lim_{n\to\infty} a_n \end{array}
c の値の範囲を実数全体に広げる場合
\begin{array}{ccc} \displaystyle c \lim_{n\to\infty} a_n &=& cα \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} c a_n&=& cα \end{array}
証明が意外と面倒だったりします。
前提と定義から分かること
まず確認しておくと
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} a_n &=& α \end{array}
これは前提とするので
\begin{array}{ccc} \displaystyle c \lim_{n\to\infty} a_n &=& cα \end{array}
これは明らかであるとします。
ほぼ全ての実数 c では
分からないのは片側
\begin{array}{ccc} \forall ε & \exists N & \forall n≥N & |ca_{n}-cα|<ε \end{array}
この定義が目指す答えになることから
\begin{array}{ccc} ca_{n}-cα \end{array}
これを考えたいわけですが
\begin{array}{ccc} |ca_{n}-cα| &=& |c(a_n-α)| \end{array}
見た目で分かる通り
絶対値の性質 |αβ|=|α| \cdot |β| を使うと
\begin{array}{ccr} |c(a_n-α)| &=& c|a_n-α| && 0<c \\ \\ |c(a_n-α)| &=& -c|a_n-α| &&c<0 \end{array}
これはこうなりますから
\begin{array}{ccc} |a_n-α| &<& \displaystyle \frac{ε}{|c|} \end{array}
このような ε をとれば
後はこれを変形するだけで欲しい結論が示されます。
(これは前提なのでここから得られた結果は正しい)
0 で割る行為は定義できない
↑ が成立するのは
「 c が 0 ではない実数」の時です。
\begin{array}{ccc} |a_n-α| &<& \displaystyle \frac{ε}{|c|} \end{array}
ということは
これを使うという理屈では
\begin{array}{ccc} |a_n-α| &<& \displaystyle \frac{ε}{0} \end{array}
c=0 の場合
欲しい結論を得ることができません。
(この不等式の右側は定義できない)
c=0 のパターンで欲しい結論を得たいなら
\begin{array}{ccc} |0 \cdot a_n - 0 \cdot α | &=& |0-0| \end{array}
必ず ε で抑えられる値である
0 になるという計算結果から
\begin{array}{ccc} |0 \cdot a_n - 0 \cdot α | &<& ε \end{array}
直接的に定義を得る必要があります。
(このパターンでは証明に別の理屈が必要)
下限と上限でも成立しそうだけど
↑ と同様に
直感的に考えると
\begin{array}{lcc} \sup\{a_n\} &=& α && 前提 \\ \\ \sup\{ca_n\} &=& c\sup\{a_n\} &&結論 \end{array}
これも成立しそうです。
実際
\begin{array}{lcccl} \forall n \,\, a_n≤α &{}&\to&& \forall n \,\, ca_n≤cα \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, α - ε < a_N &{}&\to&{}& \displaystyle \forall ε^* \,\, \exists N \,\, α - \frac{ε^{*}}{c} < a_N \end{array}
0<c の場合と
( ε=ε^*/c としてもとれる範囲は同じ)
\begin{array}{ccc} \sup\{ca_n\} &=&\sup \{0\} \\ \\ c\sup\{a_n\} &=& 0 \end{array}
c=0 の場合では
特に問題無くこの性質は満たされます。
斉次性が保証されない場合
しかし c<0 の場合では
\begin{array}{lcccl} \forall n \,\, a_n≤α &{}&\to&& \forall n \,\, ca_n≥cα \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, α - ε < a_N &{}&\to&{}& \displaystyle \forall ε^* \,\, \exists N \,\, α - \frac{ε^*}{-c} < a_N \\ \\ &{}&\to&{}& \displaystyle \forall ε^* \,\, \exists N \,\, cα + ε^* > ca_N \end{array}
0<c の場合と同様にやると
どうしても不等号の向きが変わってしまいます。
( c は負なので ε に入れる際は符号を逆に)
そしてこの形は
\begin{array}{lcccl} \forall n \,\, cα≤ca_n \\ \\ \displaystyle \forall ε^* \,\, \exists N \,\, ca_N < cα + ε^* \end{array}
「下限」の定義であるため
cα は数列 \{ca_n\} の下界の最大元です。
ということは
\begin{array}{ccc} \sup\{ca_n\} &=& ? \\ \\ \inf\{ ca_n \} &=& cα &=& c \sup \{a_n\} \end{array}
c<0 の場合
これはこのようになってしまうため
「斉次性」を満たさないと言えます。
下限の定義から
↑ で出てきた
\begin{array}{ccc} \sup\{ca_n\} &=& ? \end{array}
これがこのままというのは気持ち悪いので
\begin{array}{lcccl} \forall n \,\, a_n≤α &{}&\to&& \forall n \,\, ca_n≥cα \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, α - ε < a_N &{}&\to&{}& \displaystyle \forall ε^* \,\, \exists N \,\, α - \frac{ε^*}{-c} < a_N \\ \\ &{}&\to&{}& \displaystyle \forall ε^* \,\, \exists N \,\, cα + ε^* > ca_N \end{array}
「下限」の時と同じ要領で
(これは上限の定義から入った)
今度は「下限」の定義から入ってみます。
(下限の存在を前提とします)
\begin{array}{lcccl} \forall n \,\, α≤a_n &{}&\to&& \forall n \,\, cα≥ca_n \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N<α+ε &{}&\to&{}& \displaystyle \forall ε^* \,\, \exists N \,\, a_N < \frac{ε^*}{-c} + α \\ \\ &{}&\to&{}& \displaystyle \forall ε^* \,\, \exists N \,\, cα - ε^* < ca_N \end{array}
すると
\begin{array}{lcc} \forall n \,\, cα≥ca_n \\ \\ \displaystyle \forall ε^* \,\, \exists N \,\, cα - ε^* < ca_N \end{array}
これは「上限」の定義になりますから
以上の結果より
\begin{array}{ccc} \sup\{ ca_n \} &=& cα &=& c \inf \{a_n\} \end{array}
これはこのようになると言えます。
(あくまで c<0 の範囲では)
上限下限が斉次性を持つには
まとめると
\begin{array}{rcr} \sup\{ca_n\} &=& c\sup\{a_n\} \\ \\ \inf\{ca_n\} &=& c\inf\{a_n\} \end{array}
これが成立するのは
0≤c の場合でだけで
\begin{array}{rcccr} \inf\{ ca_n \} &=& cα &=& c \sup \{a_n\} \\ \\ \sup\{ ca_n \} &=& cα &=& c \inf \{a_n\} \end{array}
c<0 の場合はこのようになります。
極限の加法性
この性質については
\begin{array}{lcc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} a_n &=& α \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} b_n &=& β \end{array}
この前提と
\begin{array}{ccc} |x+y| &≤& |x|+|y| \end{array}
「三角不等式」を使うと
特に複雑な手順を必要とせず
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \Bigl( a_n + b_n \Bigr) &=& α+β \end{array}
この結果をすぐに得ることができます。
加法性の証明
やることは単純
\begin{array}{ccc} |(a_n+b_n)-(α+β)| &<& ε &&? \end{array}
「三角不等式」の適用により
\begin{array}{ccc} |(a_n+b_n)-(α+β)| &≤& |a_n-α|+|b_n-β| \end{array}
これが確実にこうなることから
\begin{array}{ccc} |a_n-α|+|b_n-β| &<& ε_a + ε_b \end{array}
こんな不等式を得ることができるので
( ε_a + ε_b は ε と同じく限りなく 0 に近付ける)
\begin{array}{ccc} |(a_n+b_n)-(α+β)| &<& ε \end{array}
結果、こうなると言えます。
(これがそのまま極限の定義になる)
上限下限の加法規則
これも直感的には同じになりそうですが
\begin{array}{rcc} \sup\{ a_n+b_n \} &=& \sup\{a_n\}+\sup\{b_n\} \\ \\ \inf\{ a_n+b_n \} &=& \inf\{ a_n \}+\inf\{ b_n \} \end{array}
実はこれも一般的には成立しません。
\begin{array}{lcccl} \forall n \,\, α≤a_n &{}&\to&& \forall n \,\, α+c≤a_n+c \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N<α+ε &{}&\to&{}& \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N +c < α+c + ε \end{array}
「定数」の場合や
\begin{array}{lcccl} \forall n \,\, α≤a_n &{}&\to&& \forall n \,\, α+b_m≤a_n+b_m \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N<α+ε &{}&\to&{}& \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N + b_m < α + b_m + ε \end{array}
「 n に関係の無い数列」であれば
(この時の b_m は実数の定数として扱う)
\begin{array}{lcccl} \displaystyle \inf \{a_n\}=α &&\to&& \displaystyle \inf \{a_n+c\}=α+c \\ \\ \displaystyle \inf\{a_n\}=α &&\to&& \displaystyle \inf\{a_n+b_m\}=α+b_m \end{array}
確実に成立しますが
(上限でもこうなるのは明らか)
「 n で変わる数列の和」である場合
\begin{array}{lcc} \forall n \,\, α≤a_n \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N<α+ε \\ \\ \\ \forall n \,\, β≤b_n \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, b_N<β+ε \end{array}
ここから分かるのは ↓ だけです。
\begin{array}{ccc} \forall n \,\, α+β≤a_n+b_n \end{array}
実際
\begin{array}{rcc} \sup\{ a_n+b_n \} &=& \sup\{a_n\}+\sup\{b_n\} \\ \\ \inf\{ a_n+b_n \} &=& \inf\{a_n\}+\inf\{b_n\} \end{array}
これが成立しない反例が存在します。
振動と反例
例外となる反例は
\begin{array}{ccl} a_n &=& \left\{ \begin{array}{ccl} 1 && n\in\mathrm{odd} \\ \\ 0 && n\in\mathrm{even} \end{array} \right. \\ \\ \\ b_n&=&\left\{ \begin{array}{ccc} 0 && n\in\mathrm{odd} \\ \\ 1 && n\in\mathrm{even} \end{array} \right. \end{array}
だいたい振動と定義関数を使えば作れます。
(数列同士の下限を相殺する感じ)
確認してみると
\begin{array}{lcc} \inf\{a_n\} &=& 0 \\ \\ \inf\{b_n\} &=& 0 \end{array}
それぞれの「下限」はこうです。
そしてこれらの「和の下限」は
\begin{array}{ccc} a_n+b_n &=& \left\{ \begin{array}{ccl} 1+0 && n\in\mathrm{odd} \\ \\ 0+1 && n\in\mathrm{even} \end{array} \right. \end{array}
「数列の和」が全て 1 になるので
\begin{array}{ccc} \inf\{a_n+b_n\} &=& 1 \end{array}
当然 1 になります。
ということは
\begin{array}{ccc} \inf\{a_n\} + \inf\{b_n\} &≤& \inf\{a_n+b_n\} \\ \\ 0 &≤& 1 \end{array}
こういうことなので
結果、これは反例になると言えます。
(和の下限は下限の和と常に等しいわけではない)
独立した添え字のパターン
↑ でさらっと流しましたが
\begin{array}{lcccl} \forall n \,\, α≤a_n &{}&\to&& \forall n \,\, α+b_m≤a_n+b_m \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N<α+ε &{}&\to&{}& \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N + b_m < α + b_m + ε \end{array}
これについて
念のため厳密に扱っておきます。
まず「下界の要素であるか」については
\begin{array}{ccc} \forall m \,\, \forall n \,\, α+b_m≤a_n+b_m &&\to&& \forall n \,\, α+b_{m_*}≤a_n+b_{m_*} \end{array}
これは厳密にはこうなっています。
(本質的にはどちらを先に定数とするか問題)
m を選ぶまではどの b_m か分からない
\begin{array}{ccc} b_m &\to& b_{m_*} &\to& 定数 \end{array}
でも定数 m_* を選ぶと
b_m の具体的な値が分かるので
\begin{array}{ccc} \forall n \,\, α+b_{m_*}≤a_n+b_{m_*} \end{array}
この論理式では
b_{m_*} は「定数」として振舞います。
(引き算すれば 0 になって消えてくれる)
「下界の最大元である」も同様
\begin{array}{ccc} \displaystyle \exists N \,\, a_N + b_m < α + b_m + ε^* \end{array}
これも「 m を決めてある」状態なので
(このようになる M が存在する)
\begin{array}{ccc} \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, \exists M \,\, a_N + b_M < α+β + ε \end{array}
このような形から
\begin{array}{ccc} \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N + b_m < α + b_m + ε \end{array}
↑ は導くことができます。
(この場合は m が量化されない)
一般化した論理式から
↑ は「一般化された話」で
先に示したものはこの具体例です。
\begin{array}{lcc} \forall m \,\, \forall n \,\, γ≤a_n+b_{m} \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, \exists M \,\, a_N + b_M < γ + ε \end{array}
ということは、これは一般形
\begin{array}{ccc} \displaystyle \inf_{n,m}\{ a_n+b_m \} &=& γ \end{array}
このような記号を考えれば
これは論理式の表現の一つになり得ます。
( n,m を別々に動かして下限を得る操作)
そして実はこれ
\begin{array}{lcc} \forall n \,\, α≤a_n \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N < α + ε \\ \\ \\ \forall m \,\, β≤b_{m} \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists M \,\, b_M < β + ε \end{array}
この前提を使って話を進めると
\begin{array}{lcccl} \forall n \,\, α≤a_n &&\to&& α≤a_{n_*} \\ \\ \forall m \,\, β≤b_m &&\to&& β≤b_{m_*} \end{array}
ここからは
\begin{array}{lcccr} α+β≤a_{n_*}+b_{m_*} &&\to&& \forall n \,\, α+β≤a_n+b_{m_*} \\ \\ &&\to&& \forall m \,\, \forall n \,\, α+β≤a_n+b_m \end{array}
これが導かれて
(量化の順番により先に定数になる方が決まる)
\begin{array}{lcccr} \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N < α + ε &&\to&& \displaystyle\exists N \,\, a_N < α + \frac{ε^*}{2} \\ \\ &&\to&& \displaystyle a_{N_*} < α + \frac{ε^*}{2} \\ \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists M \,\, b_M < β + ε &&\to&& \displaystyle\exists M \,\, b_M < β + \frac{ε^*}{2} \\ \\ &&\to&& \displaystyle b_{M_*} < β + \frac{ε^*}{2} \end{array}
ここからは
\begin{array}{lcccr} a_{N_*}+b_{M_*} < α + β + ε^* &&\to&& \exists M a_{N_*}+b_{M} < α + β + ε^* \\ \\ &&\to&& \exists N \,\, \exists M \,\, a_{N}+b_{M} < α + β + ε^* \end{array}
これが導かれるので
(これも前提より存在が確約されてる)
その結果として
\begin{array}{ccc} \displaystyle\inf_{n,m}\{ a_n+b_m \} &=& α & + & β \\ \\ &=& \displaystyle\inf_{n}\{ a_n \} & + & \displaystyle\inf_{m}\{ b_m \} \end{array}
この関係を導くことができます。
(本質的にこれは定数の話と同じ)
定数の極限
これも直感的に明らかですが
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} c &=& c \end{array}
念のため定義から確認しておきます。
(未証明の段階では右を α としておく)
定数の極限をとると定数になる証明
これは本当にそのまま
\begin{array}{rcc} |c-c|<ε && N≤n \\ \\ 0<ε && N≤n \end{array}
定数 c は n に関係無く c なので
これが成立するのは明らかですから
( n,N がなんであれ成立する)
\begin{array}{cccr} \forall ε & \exists N & \forall n≥N & |a_{n}-α|<ε && \\ \\ \forall ε & \exists N & \forall n≥N & |c-c|<ε && ? \\ \\ \forall ε & \exists N & \forall n≥N & 0<ε &&〇 \end{array}
こうなるのは明らかだと言えます。
(下の論理式の変形で欲しい論理式が導ける)
n に関係の無い一般項
この場合も同様の理屈で
\begin{array}{cccr} \forall ε & \exists N & \forall n≥N & |a_k-a_k|<ε \\ \\ \forall ε & \exists N & \forall n≥N & 0<ε \end{array}
n に関係無くこうなるので
そのまま変化せずに出力されます。
( a_n でも a_n に収束するのは当然)
ルベーグ積分 Lebesgue Integral
「単関数近似定理」を根拠とする積分
\begin{array}{lcc} \displaystyle \int_{(-\infty,\infty)} 1_{[a,b)}(x) \,dμ(x) &=& μ\Bigl( [a,b) \Bigr) \\ \\ \displaystyle \int_D f \, dμ &=& \displaystyle \sup\left\{ \int_D φ \, dμ \right\} \end{array}
「単関数積分の上限」として定義されていて
(これをして良い根拠が単関数近似定理)
\begin{array}{ccc} φ_n(x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} c_k 1_{ I_k }(x) \end{array}
その「単関数の積分」は
\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} I &=& \displaystyle \bigsqcup_{k=1}^{n} I_k \\ \\ \displaystyle \int_{I} φ_n(x) \, dμ(x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} c_k μ(I_k) \end{array} \end{array}
「ルベーグ測度 μ 」によって定義されています。
(ルベーグ測度については本題から逸れるので省略)
ルベーグ積分の線型性
この性質についても
\begin{array}{lcl} \displaystyle\int f &=& \displaystyle \int f^+ - \int f^- && ? \\ \\ \displaystyle\int f &=& \displaystyle \int \Bigl( f^+ + (-1)f^- \Bigr) && 〇 \end{array}
「一般の可測関数」を考えたい時など
( f^+ は正の部分 f^- は負の部分で両方とも正)
\begin{array}{ccc} f(αx+βy) &=& αf(x) + βf(y) \\ \\ \displaystyle \int αf+βg &=& \displaystyle α\int f + β\int g \\ \\ \displaystyle \int f^+ +(-1)f^- &=& \displaystyle \int f^+ + (-1)\int f^- \end{array}
「ルベーグ積分」を考える上でほぼ必須なため
ここできちんと示しておきます。
(見やすさのために略記)
ルベーグ積分の斉次性
「上限」を定義とする「可測関数」
\begin{array}{ccc} f(x) &=& \displaystyle \sup \left\{\sum_{k=1}^{n} c_k 1_{D_k} (x) \right\} \end{array}
これを直接触る前に
\begin{array}{rcr} φ_n(x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} c_k 1_{D_k} (x) \\ \\ αφ_n(x) &=& \displaystyle α\sum_{k=1}^{n} c_k 1_{D_k} (x) \end{array}
まずはその基礎になる
「非負単関数の積分」について見てみます。
やることはそのまま
\begin{array}{ccc} \displaystyle α\sum_{k=1}^{n} c_k 1_{D_k} (x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} αc_k 1_{D_k} (x) \end{array}
「総和の斉次性」さえ理解していれば
「単関数のルベーグ積分」が「斉次性」を持つ
(正の単関数としたいので 0≤α とする)
\begin{array}{lclcl} \displaystyle \int αφ_n(x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} (α c_k) μ(D_k) \\ \\ &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} α c_k μ(D_k) \\ \\ &=& \displaystyle α\sum_{k=1}^{n} c_k μ(D_k) &=& \displaystyle α\int φ_n(x) \end{array}
この事実については
リーマン積分と同様の手順で確認することができます。
(有限総和の斉次性については明らかなので省略)
非負可測関数の場合
「非負可測関数」の定義は
\begin{array}{rcr} f(x) &=& \displaystyle \sup \left\{\sum_{k=1}^{n} c_k 1_{D_k} (x) \right\} \\ \\ αf(x) &=& \displaystyle α \sup\left\{\sum_{k=1}^{n} c_k 1_{D_k} (x) \right\} \end{array}
「非負単関数」により
このように定められていて
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int αf(x) &=& \displaystyle α \sup\left\{\sum_{k=1}^{n} c_k μ(D_k) \right\} &&? \\ \\ \displaystyle α\int f(x) &=& \displaystyle α \sup\left\{\sum_{k=1}^{n} c_k μ(D_k) \right\} &&〇 \end{array}
その積分の定義はこのようになっています。
(ここでも 0≤α の場合に限るとします)
ということは
\begin{array}{ccc} \displaystyle α \sup\left\{\sum_{k=1}^{n} c_k μ(D_k) \right\} &=& \displaystyle \sup\left\{ \sum_{k=1}^{n} αc_k μ(D_k) \right\} \end{array}
これは「上限」の定義に依存する話ですから
\begin{array}{lcl} \displaystyle α \sup\left\{ c_n \right\} &=& \displaystyle \sup\left\{α c_n \right\} \end{array}
根本的には
この等式の成立によってこれは証明されます。
( α が正であるため上限の性質より明らか)
一般の可測関数の場合
これは示された ↑ の事実を使うと
\begin{array}{lcl} \displaystyle\int f &=& \displaystyle \int f^+ - \int f^- \end{array}
「可測関数の積分」の定義より
0≤α の場合については
\begin{array}{lcl} \displaystyle α\int f &=& \displaystyle α \left(\int f^+ - \int f^- \right) \\ \\ &=& \displaystyle α\int f^+ - α\int f^- \\ \\ &=& \displaystyle \int αf^+ - \int αf^- &=& \displaystyle \int αf \end{array}
すぐに問題無く成立すると分かります。
(この場合は非負可測関数の話になる)
問題となるのは α<0 のパターンで
\begin{array}{rcrcr} f &=& f^+ & - & f^- \\ \\ αf &=& αf^+ & - & αf^- \\ \\ αf &=& -(-αf^+) & - & (- (-αf^-)) \\ \\ αf&=& -(-αf^+) & + & (-αf^-) \end{array}
これを示すには
「正の部分」「負の部分」の逆転を考えて
(負の関数だと現状ではルベーグ積分できない)
\begin{array}{lcl} \displaystyle\int αf &=& \displaystyle\int (-αf^-) - \int (-αf^+) \\ \\ &=& \displaystyle\int (-α)f^- - \int (-α)f^+ \\ \\ &=& \displaystyle (-α) \int f^- - (-α)\int f^+ \\ \\ &=& \displaystyle -α \int f^- + α\int f^+ \\ \\ &=&\displaystyle α \left( \int f^+ - \int f^- \right) &=& \displaystyle α \int f \end{array}
なんとか「非負可測関数」の話にすり替える
という手順が必要になります。
ルベーグ積分の加法性
これも ↑ と同様の流れで証明できます。
\begin{array}{lcl} φ_n(x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} a_k 1_{D_k} (x) \\ \\ ψ_n(x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} b_k 1_{D_k} (x) \end{array}
基本は常に「非負の単関数」です。
証明で使うのは
\begin{array}{ccccl} i≠j⇒D_i ∩ D_j=∅ && \to && \displaystyle D=\bigcup_{k=1}^{n}D_k \\ \\ i≠j⇒D_i ∩ D_j=∅ && ← && \displaystyle D=\bigsqcup_{k=1}^{n}D_k \end{array}
共通の積分範囲 D と共通の分割 D_k
(これで一般性が保証される理由については後述)
ここから
\begin{array}{ccc} φ_n+ψ_n \\ \\ \displaystyle \sum_{k=1}^{n} a_k 1_{D_k} (x) + \sum_{k=1}^{n} b_k 1_{D_k} (x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} (a_k+b_k) 1_{D_k} (x) \end{array}
「単関数の和」の形と
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_D φ_n + \int_D ψ_n &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} a_k μ(D_k) + \sum_{k=1}^{n} b_k μ(D_k) \end{array}
「非負単関数の積分」の定義により
\begin{array}{lcl} \displaystyle \sum_{k=1}^{n} a_k μ(D_k) + \sum_{k=1}^{n} b_k μ(D_k) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} a_k μ(D_k) + b_k μ(D_k) \\ \\ &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} (a_k + b_k) μ(D_k) \\ \\ &=& \displaystyle \int_D \left( \sum_{k=1}^{n} (a_k+b_k) 1_{D_k} (x) \right) \end{array}
これはこのような流れで証明できます。
(ほぼ全ての非負単関数で成立 詳細は後回し)
非負可測関数では
これについては
「単関数近似定理」を意識する必要があって
\begin{array}{ccccc} 0 &≤& φ_n & ≤ & f \\ \\ 0 &≤& ψ_n & ≤ & g \end{array}
まずこの関係から
\begin{array}{lcl} φ_n + ψ_n &≤& f+g \end{array}
この当然の結果を得る必要があります。
(非負可測関数を直接触るのは基本避ける)
これが分かっていれば
「非負単関数」の時に得られた結果から
\begin{array}{lcl} \displaystyle\int f+g &=& \displaystyle \sup \left\{ \int φ_n+ψ_n \right\} \end{array}
「非負単関数の積分」の加法性と
「上限」の性質を認めるなら
(非負単関数なので加法性が使える)
\begin{array}{lcl} \displaystyle \sup \left\{ \int φ_n+ψ_n \right\} &=& \displaystyle \sup \left\{ \int φ_n + \int ψ_n \right\} \\ \\ &=& \displaystyle \sup \left\{ \int φ_n \right\} + \sup \left\{ \int ψ_n \right\} \end{array}
こうなると言えるので
後は
\begin{array}{ccl} \displaystyle \int f &=& \displaystyle \sup \left\{ \int φ_n \right\} \\ \\ \displaystyle \int g &=& \displaystyle \sup \left\{ \int ψ_n \right\} \end{array}
「非負可測関数の積分」の定義を考えれば
\begin{array}{lcl} \displaystyle\int (f+g) &=& \displaystyle \sup \left\{ \int φ_n+ψ_n \right\} \\ \\ &=& \displaystyle \sup \left\{ \int φ_n \right\} + \sup \left\{ \int ψ_n \right\} &=& \displaystyle \int f + \int g \end{array}
欲しい結論に辿り着くことができます。
一般の可測関数の場合
これについては
↑ からすぐに導かれそうですが
\begin{array}{lcl} \displaystyle\int f &=& \displaystyle \int f^+ - \int f^- \\ \\ \displaystyle\int g &=& \displaystyle \int g^+ - \int g^- \end{array}
↓ のゴールを目指す上で必要な部分が
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int f+g &=& \displaystyle \int (f + g)^+ - \int (f + g)^- \end{array}
「非負可測関数の積分」の定義と
「非負可測関数の加法性」だけでは
\begin{array}{lcl} (f + g)^+ &=& f^+ + g^+ && △ \\ \\ (f + g)^- &=& f^- + g^- && △ \end{array}
どうも上手く説明できません。
(正と負の足し算がどちらになるか不明)
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int f + \int g &=& \displaystyle \int f^+ - \int f^- + \int g^+ - \int g^- \\ \\ &=& \displaystyle \int f^+ + \int g^+ - \left( \int f^- + \int g^- \right) \\ \\ &=& \displaystyle \int f^+ + g^+ - \int f^- + g^- \\ \\ &=& \displaystyle \int (f+ g)^+ - \int (f + g)^- &&? \end{array}
ただ足し算をして式変形するだけでは不十分です。
欲しい結果から
これを示すためには
ゴールから逆算する必要があります。
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int f+g &=& \displaystyle \int f + \int g \\ \\ \displaystyle \int (f + g)^+ - \int (f + g)^- &=& \displaystyle \left( \int f^+ - \int f^- \right) + \left( \int g^+ - \int g^- \right) \end{array}
この結果を僅かな事実から目指していくとなると
ちょっと難しい気もしますが
使える事実は限られているので
\begin{array}{lcl} f+g &=& (f+g)^+ - (f+g)^- \\ \\ f+g &=& ( f^+ - f^- ) + ( g^+ - g^- ) \end{array}
証明は意外と一本道になります。
というのも
\begin{array}{ccc} (f+g)^+ - (f+g)^- &=& ( f^+ - f^- ) + ( g^+ - g^- ) \end{array}
↑ から得られる結果はこれだけ
(ここくらいしかスタート地点が無い)
\begin{array}{lcl} (f+g)^+ - (f+g)^- &=& ( f^+ - f^- ) + ( g^+ - g^- ) \\ \\ (f+g)^+ + f^- + g^- &=& f^+ + g^+ + (f+g)^- \end{array}
使える事実も「非負可測関数」の結果だけなので
(とりあえず両辺を非負にするしかない)
この結果から
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int (f+g)^+ + f^- + g^- &=& \displaystyle \int f^+ + g^+ + (f+g)^- \\ \\ \displaystyle \int (f+g)^+ + \int f^- + \int g^- &=& \displaystyle \int f^+ + \int g^+ + \int (f+g)^- \end{array}
「非負可測関数」の「積分」と「加法性」より
(使える操作がこれくらいしかない)
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int (f+g)^+ + \int f^- + \int g^- &=& \displaystyle \int f^+ + \int g^+ + \int (f+g)^- \\ \\ \displaystyle \int (f+g)^+ - \int (f+g)^- &=& \displaystyle \int f^+ +\int g^+ -\int f^- - \int g^- \\ \\ \displaystyle \int (f+g)^+ - \int (f+g)^-&=& \displaystyle \int f^+ -\int f^-+ \int g^+ - \int g^- \end{array}
後はゴールに寄せて並び替えていくと
(ここまで来るとやれることがこれしかない)
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int (f + g)^+ - \int (f + g)^- &=& \displaystyle \left( \int f^+ - \int f^- \right) + \left( \int g^+ - \int g^- \right) \\ \\ \displaystyle \int f+g &=& \displaystyle \int f + \int g \end{array}
結果、自然とこの結論に行き着きます。
大小関係の保存
この記事の主題である
「優収束定理」の根幹を成す
\begin{array}{rcr} a_n &≤& b_n \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} a_n &≤& \displaystyle \lim_{n\to\infty} b_n \end{array}
この関係について
ここできちんと解説しておきます。
(これにより等号の片側を保証できる)
前提は ↓
\begin{array}{lcc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} a_n &=& α \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} b_n &=& β \end{array}
「発散する」場合は大小関係が明らかなので
ここでは「極限値は存在する」ことにしておきます。
(振動パターンもここでは考えないものとします)
数列の大小 ⇒ 極限値の大小
この話自体は単純なんですが
\begin{array}{lcl} a_n≤b_n &&\to&& 0≤b_n-a_n \end{array}
ここからの式変形が少しだけ複雑です。
こんな形で
\begin{array}{lcl} β-α &=& (β-b_n+b_n)-(α-a_n+a_n) \\ \\ &=& (β-b_n)-(α-a_n)+(b_n-a_n) \end{array}
「極限値」と「数列」の関連を得て
\begin{array}{lcccl} -ε_α &<& a_n-α &<& ε_α \\ \\ -ε_β &<& b_n-β &<& ε_β \end{array}
「極限」の定義を確認しながら
(全ての n≥N で ↑ が成立する)
\begin{array}{lcr} β-α &≥& (β-b_n)-(α-a_n) +0 \\ \\ β-α &>& -ε_β - ε_α \end{array}
前提を使って不等式を構成し
( N=\max(N_α,N_β) として n はそれ以上)
\begin{array}{rcl} -ε_β - ε_α &<& 0 \\ \\ -ε_β - ε_α &<& β-α \end{array}
そこから ↑ の結論を得るんですが
一連の流れの変数の扱いが複雑で
見た目以上に難解になっています。
ちなみに
↑ の事実から
\begin{array}{ccc} 0 &≤& β-α \end{array}
β-α が 0 以上であれば ↑ が成立するため
その結果としてこの結論を得ています。
( α,β は n に依存しない)
極限値の大小 ⇒ 数列の大小
これの複雑さについては
\begin{array}{ccc} \displaystyle α ≤ β &&\to&& a_n≤b_n \end{array}
逆側について考えてみると実感しやすいです。
(これは極限が定義されていない状態になる)
分かりやすい話
\begin{array}{lcl} a_n = 1 && α=1 \\ \\ \displaystyle b_n = \frac{1000}{n} && β=0 \end{array}
例えばこのような反例があることから
「全ての n で」成立しない
( a_n≤b_n はある N 以上でしか成立しない)
これはこの時点で明らかなんですが
\begin{array}{ccc} \begin{array}{lcl} β-α &=& (β-b_n)-(α-a_n)+(b_n-a_n) \end{array} \end{array}
この関係式と ↓ を見ると
\begin{array}{ccc} 0 &≤& β-α \end{array}
一見、成立しているように見えてしまいます。
(この関係式だけじゃ問題点が見当たらない)
問題点と論理式
結論から行くと
\begin{array}{lcl} a_n = 1 && α=1 \\ \\ \displaystyle b_n = \frac{1000}{n} && β=0 \end{array}
↑ のような反例があるのに
関係式的には成立してるように見える
この問題は
\begin{array}{lcc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} a_n &=& α \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} b_n &=& β \end{array}
これが定義されていないから起こっています。
(極限値の大小は定数の大小でしかない)
具体的には
\begin{array}{lllr} \forall ε_a & \exists N_a & \forall n≥N_a & |a_n-α|<ε_a \\ \\ \forall ε_b & \exists N_b & \forall n≥N_b & |b_n-β|<ε_b \end{array}
この N_a,N_b が定まってないんです。
(全ての n だと ε を任意に選んだら矛盾し得る)
というのも
n が \max\{N_a,N_b\} より下の範囲では
\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccl} β-α &=& (β-b_n)-(α-a_n)+(b_n-a_n) \\ \\ 0 &≤& (β-b_n)+(a_n-α)+(b_n-a_n) \end{array} \end{array}
この関係式から結論を得る過程で
\begin{array}{lcl} |a_n-α|&<&ε_a \\ \\ |b_n-β|&<&ε_b \end{array}
ε を使うことができません。
(小さい方を選ぶと片方で ε が使えない)
となると
\begin{array}{ccc} -ε_β - ε_α &<& b_n-a_n \end{array}
この成立を
「全ての n で」保証することができないため
\begin{array}{ccc} \displaystyle α ≤ β &&\to&& a_n≤b_n \end{array}
結果
これは必ずしも成立するとは言えない、となります。
( \max\{N_a,N_b\} より下で不成立になり得る)
十分大きな
これを双方で成立させたい場合の表現として
「十分に大きな n 」というものがあって
\begin{array}{lcl} \displaystyle | a_{10^8} - α | < 10^{-8} \\ \\ \displaystyle | b_{10^8} - β | < 10^{-8} \end{array}
この表現を用いる場合に限れば
\begin{array}{rcr} a_n &≤& b_n \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} a_n &≤& \displaystyle \lim_{n\to\infty} b_n \end{array}
「大小関係保存」は双方向で成立すると言えます。
(小さい n で成立しないかもという可能性を排除)
ただ注意点として
これは『 ε,N を定めて計算した後に分かる』ものなので
\begin{array}{ccc} N_* &\to& ε && × \end{array}
「最初に」は具体的な大きさを求められません。
(つまり十分大きな n とは都合の良い n のこと)
\begin{array}{ccc} n≥N & | a_{n} - α | < ε \end{array}
まず精度 ε を定めるのが先で
N は「後で」定められることになります。
(つまり N の導出手順は変わらない)
積分の単調性
↓ は見た目から直感的に明らかですが
\begin{array}{ccc} f(x) &≤& g(x) \\ \\ \displaystyle\int_{a}^{b} f(x) \,dx &≤& \displaystyle\int_{a}^{b} g(x) \,dx \end{array}
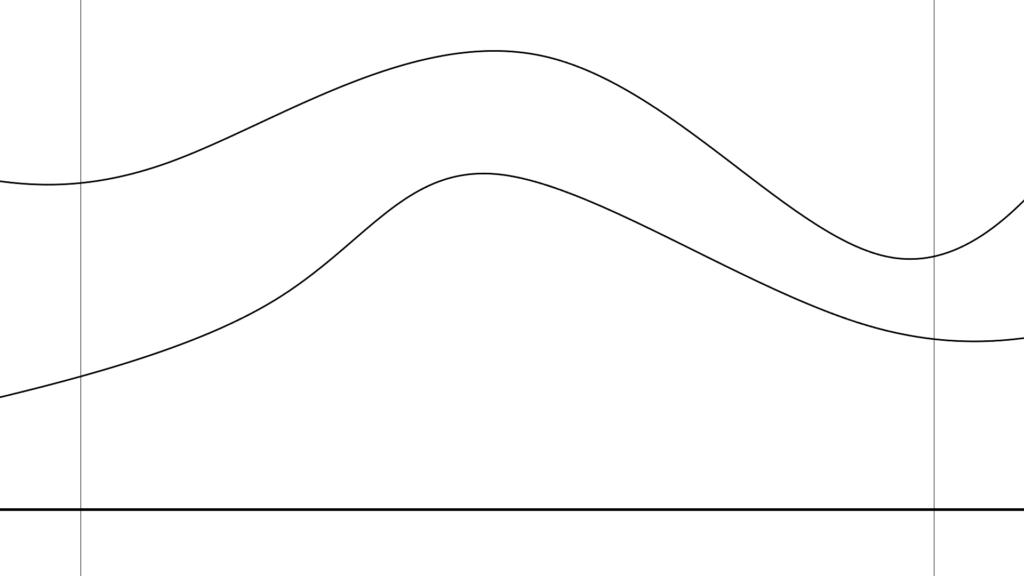
念のため誤魔化さず証明しておきます。
注意点として
「関数の大小関係」を前提とした時
「積分値が発散する」パターンでは
\begin{array}{ccc} f(x) &≤& g(x) \\ \\ \displaystyle \int f(x) \,dx &≤& \infty \end{array}
こうなるので
これは考えるまでもなく明らかとします。
(つまり基本的に積分値が有限のパターンを考える)
リーマン積分の単調性
というわけで早速
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{a}^{b} f(x) \, dx &=& \displaystyle \lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N} f(x_n) \left( \frac{b-a}{N} \right) \end{array}
「リーマン積分」の単調性を示すために
\begin{array}{lcl} f(x) &≤& g(x) \end{array}
\begin{array}{lcl} \displaystyle f(x_1) +f(x_2)&≤& \displaystyle g(x_1)+g(x_2) \\ \\ \displaystyle \sum_{n=1}^{N} f(x_n) \left( \frac{b-a}{N} \right) &≤& \displaystyle\sum_{n=1}^{N} g(x_n) \left( \frac{b-a}{N} \right) \end{array}
「リーマン和」による定義と
\begin{array}{rcccc} -ε &<&a_n-α&<&ε \\ \\ -ε &<&b_n-β&<&ε \end{array}
極限の定義から導かれる
\begin{array}{rcr} a_n &≤& b_n \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} a_n &≤& \displaystyle \lim_{n\to\infty} b_n \end{array}
「極限」の「大小関係保存」について確認してみます。
(以上がこの話の前提になる)
すると
以上の前提に納得できれば
\begin{array}{rcr} \displaystyle \sum_{n=1}^{N} f(x_n) \left( \frac{b-a}{N} \right) &≤& \displaystyle\sum_{n=1}^{N} g(x_n) \left( \frac{b-a}{N} \right) \\ \\ \displaystyle \lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N} f(x_n) \left( \frac{b-a}{N} \right) &≤& \displaystyle \lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N} g(x_n) \left( \frac{b-a}{N} \right) \end{array}
これはそのまま
このような形で示すことができます。
(ほぼ極限の大小関係保存の話)
ルベーグ積分の単調性
「リーマン積分」はほぼ定義だけで示せますが
「ルベーグ積分」の場合はちょっと面倒です。
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_D f dμ &=& \displaystyle \sup \left\{ \sum_{n=1}^{N} c_n μ(D_n) \right\} \end{array}
これは根本的には「単関数」の話なので
\begin{array}{rcl} f(x)&=&\displaystyle\sum_{n=1}^{N} a_n 1_{A_n}(x) \\ \\ g(x)&=&\displaystyle\sum_{n=1}^{M} b_n 1_{B_n}(x) \end{array}
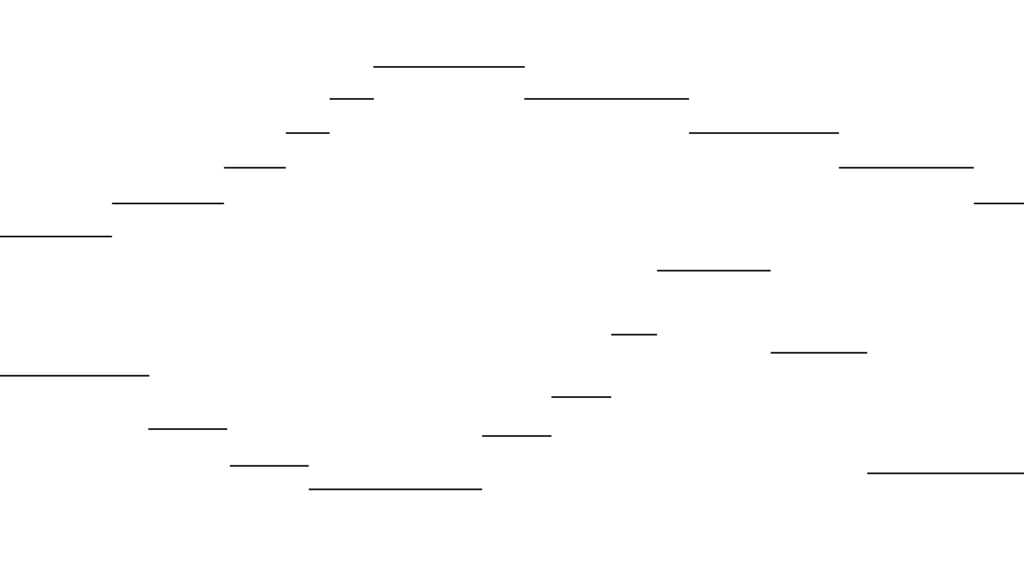
まず「可測関数 f 」の中身が
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_{[a,b]}\sum_{n=1}^{N} a_n 1_{A_n}(x) \,dμ &=& \displaystyle \int_{[a,b]}\sum_{n=1}^{M} b_n 1_{B_n}(x) \,dμ \\ \\ \displaystyle \sum_{n=1}^{N} a_n μ(A_n) &≤& \displaystyle \sum_{n=1}^{M} b_n μ(B_n) \end{array}
「単関数」である場合を考えてみれば良さそうですが
「単関数の中身」である
「定義関数」の形では大小比較ができても
\begin{array}{lcl} a_n 1_{A_n}(x) &≤& b_n 1_{B_n}(x) &&〇 \\ \\ a_n μ(A_n) &≤& b_n μ(B_n) && ? \end{array}
「積分」の形ではちょっとよく分からないので
思ったより簡単には証明することができません。
(図形の見た目で直感的には分かる)
積分範囲の分割
とまあそんな感じなので
とりあえず ↓ について考えたいわけですが
\begin{array}{lcl} a_n μ(A_n) &≤& b_n μ(B_n) \end{array}
これはこのままでは比較が難しいです。
( A_n と B_n の関係が不明)
というのも
\begin{array}{lcl} D &=& \displaystyle\bigsqcup_{n=1}^{N} A_n \\ \\ D&=&\displaystyle\bigsqcup_{n=1}^{M} B_n \end{array}
これらは「共通する図形 D の分割」ですが
\begin{array}{ccc} A_1 &=& [0,3) \\ \\ B_1&=&[0,1) \end{array}
「分割の方法」に特に指定が無いため
\begin{array}{ccc} a_1 μ(A_1) &=& 1\cdot μ(A_1) \\ \\ b_1 μ(B_1) &=& 2\cdot μ(B_1) \end{array}
局所的な大小は逆転し得る状態にあります。
(一般的に考えるならこうなる)
「共通の x 」について考えてはいるので
\begin{array}{lcl} x &\in& A_n &\subset & D \\ \\ x &\in& B_n &\subset & D \end{array}
各点での比較を行えば
\begin{array}{ccc} f(x)&≤&g(x) \end{array}
前提より
\begin{array}{ccc} a_n 1_{A_n}(x) &≤& b_n 1_{B_n}(x) \end{array}
確実に大小関係を求めることはできますが
\begin{array}{ccc} a_n μ(A_n) &≤& b_n μ(B_n) &&? \end{array}
少なくとも現状だと
そう簡単には比較することができません。
(どうにか比較できる形にする必要がある)
細かく分割してみる
ここで必要になるのが
「細分割」という概念で
\begin{array}{lcl} C_i &⊂& A \\ \\ C_i &⊂& B \end{array}
例えばそれぞれ3つの区間に分割した時
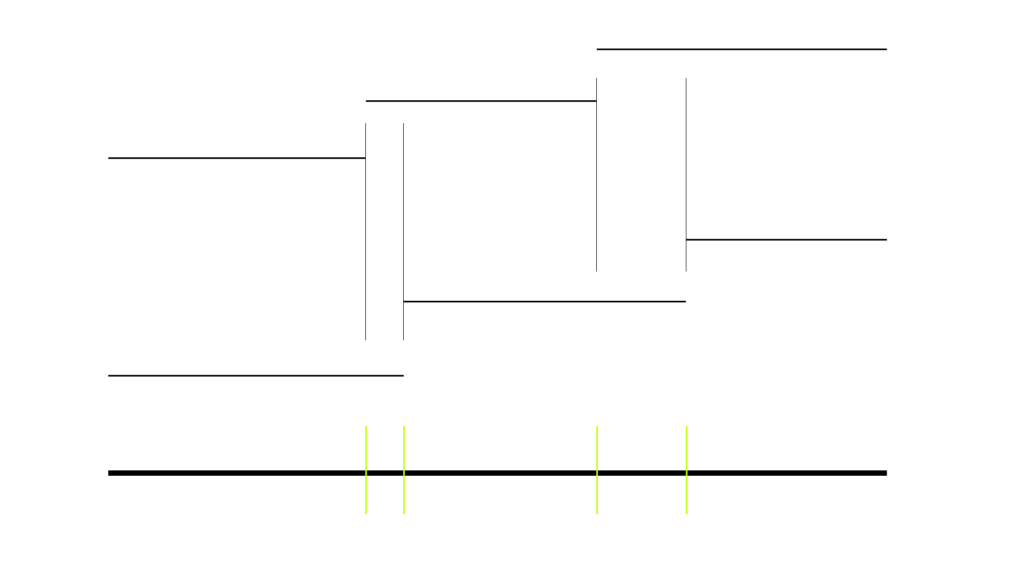
\begin{array}{lcl} A_n &\to& C_i \\ \\ B_n &\to& C_i \end{array}
このような「より細かい分割」があれば
「同一の区間で表現できる」ようになりますよね。
まあ要はそういう話で
\begin{array}{rcl} f(x)&=&\displaystyle\sum_{n=1}^{N} a_n 1_{A_n}(x) &=& \displaystyle\sum_{n=1}^{N_{*} } a^{\prime}_n 1_{C_n}(x) \\ \\ g(x)&=&\displaystyle\sum_{n=1}^{M} b_n 1_{B_n}(x) &=& \displaystyle \sum_{n=1}^{N_{*}} b^{\prime}_n 1_{C_n}(x) \end{array}
これを認めると
2つの単関数はとても比較しやすい形になってくれます。
(常に a^{\prime}_n≤b^{\prime}_n になるので比較が楽)
細分割の存在
これは画像を見て分かる通り
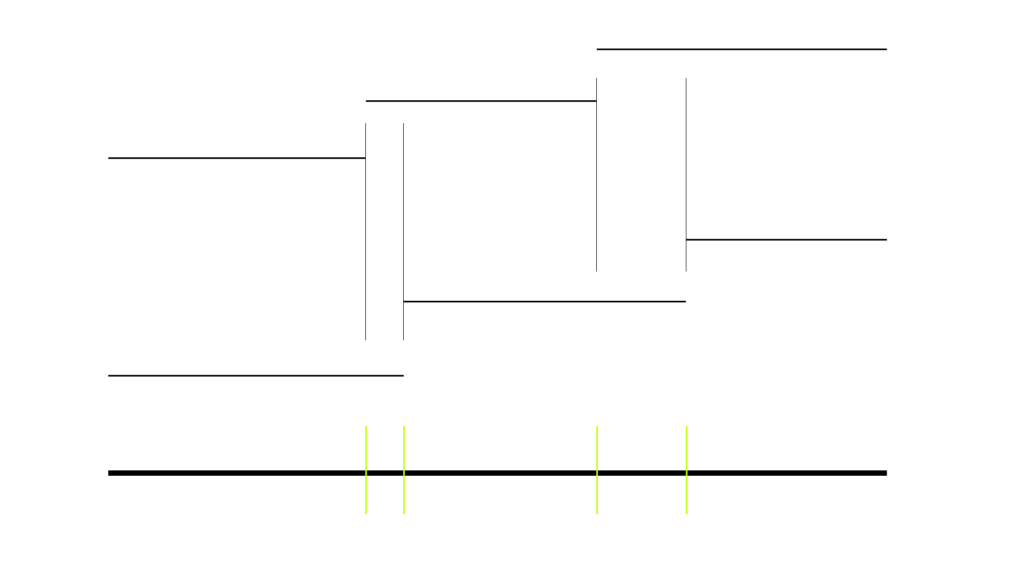
\begin{array}{ccc} A_1∩B_1 & ∅ & ∅ \\ \\ A_2∩B_1 & A_2∩B_2 & ∅ \\ \\ ∅ & A_3∩B_2 &A_3∩B_3 \end{array}
「 A_i と B_j の共通部分の存在」から
(上を A_i 下を B_j とします)
\begin{array}{lcl} C_{ij}&=&A_i∩B_j \end{array}
「共通部分の全て(空集合含め)」という形で
その存在が保証されます。
そして「共通部分」である以上
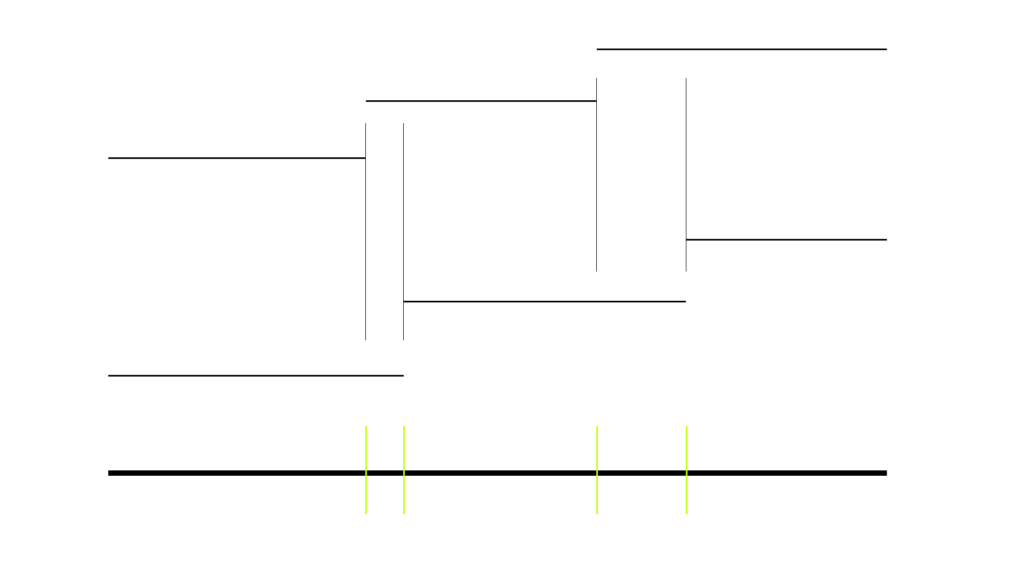
\begin{array}{ccc} A_1∩B_1 (a_1,b_1) & ∅ & ∅ \\ \\ A_2∩B_1(a_2,b_1) & A_2∩B_2(a_2,b_2) & ∅ \\ \\ ∅ & A_3∩B_2(a_3,b_2) &A_3∩B_3(a_3,b_3) \end{array}
これには必ず
添え字が同じになる a_n,b_n の値が対応するので
\begin{array}{lcl} C_n = A_i∩B_j && \to & & \begin{array}{lcl} a^{\prime}_n & = & a_i \\ \\ b^{\prime}_n &=& b_j \end{array} \end{array}
再定義された単関数の a^{\prime}_n,b^{\prime}_n の中身は
添え字によって明確に定義されます。
(空集合の時も定義できる)
単関数積分の単調性
↑ で語った通り
\begin{array}{rcl} f(x)&=&\displaystyle\sum_{n=1}^{N} a_n 1_{A_n}(x) \\ \\ g(x)&=&\displaystyle\sum_{n=1}^{M} b_n 1_{B_n}(x) \end{array}
この2つの「単関数」は
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_{D}\sum_{n=1}^{N} a_n 1_{A_n}(x) \,dμ &=& \displaystyle \int_{D}\sum_{n=1}^{M} b_n 1_{B_n}(x) \,dμ \\ \\ \displaystyle \sum_{n=1}^{N} a_n μ(A_n) &≤& \displaystyle \sum_{n=1}^{M} b_n μ(B_n) \end{array}
同じ積分範囲 D の x を扱っています。
また「 μ は同一の測度」であり
\begin{array}{lcl} f(x) &=&\displaystyle \sum_{n=1}^{N_*} a^{\prime}_n μ(\textcolor{pink}{C_n}) \\ \\ g(x) &=& \displaystyle \sum_{n=1}^{N_*} b^{\prime}_n μ(\textcolor{pink}{C_n}) \end{array}
「同一の可測集合を扱う」ため
『同一の分割範囲 C_n 』で計算が可能です。
実際に
どのような形で A_n と B_n が関わっているか
\begin{array}{lcl} {} A_n∩B_n = ∅ &\to& \begin{array}{l} {} μ(A_n)?μ(B_n) {} \end{array} \\ \\ \\ {} A_n∩B_n ≠ ∅ &\to& \begin{array}{lcl} A_n ⊂B_n \\ \\ A_n⊃B_n \\ \\ ¬(A_n ⊂B_n) ∧ ¬(A_n⊃B_n) \end{array} \end{array}
これはなにも定まってないなら分かりませんが
「単関数の大小関係」を定めた上で
\begin{array}{lcl} \displaystyle\sum_{n=1}^{N} a_n 1_{A_n}(x) &≤& \displaystyle\sum_{n=1}^{M} b_n 1_{B_n}(x) \end{array}
「細分割の存在」を認めるなら
\begin{array}{lcl} {} \displaystyle\sum_{n=1}^{N_*} a^{\prime}_n 1_{\textcolor{pink}{C_n}}(x) &≤& \displaystyle\sum_{n=1}^{N_*} b^{\prime}_n 1_{\textcolor{pink}{C_n}}(x) \end{array}
全ての x でこうなることは確実であり
(定義関数が変わっただけで単関数に変化は無い)
この結果から
\begin{array}{ccc} {} \displaystyle \sum_{n=1}^{ N_*} a^{ \prime}_n μ(\textcolor{pink}{C_n}) & ≤ & \displaystyle \sum_{n=1}^{N_*} b^{\prime}_n μ( \textcolor{pink}{C_n}) {} \\ \\ \displaystyle \int_D f(x) \,dμ &≤& \displaystyle \int_D g(x) \,dμ \end{array}
欲しかったこの結論を得ることができます。
(前提の大小関係より a^{\prime}_n≤b^{\prime}_n なので)
非負可測関数での単調性
↑ が解決した時点で
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int_{D} φ_N(x) \,dx & = & \displaystyle \int_{D} \lim_{N\to\infty} φ_N(x) \,dx\end{array}
いろんな説明で使えるこの関係は示せるんですが
(ここまでの関係でだいたいカバーできる)
せっかくなので
ここまでの事実から
\begin{array}{lcl} f(x) &=& \displaystyle\sup \left\{ \sum_{n=1}^{N}a_n 1_{A_n}(x) \right\} \\ \\ g(x) &=& \displaystyle\sup \left\{ \sum_{n=1}^{M}b_n 1_{B_n}(x) \right\} \end{array}
「非負可測関数」の場合も確かめておきます。
大小関係と上限の定義
やることは少し複雑です。
\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} \displaystyle\sum_{n=1}^{N}a_n 1_{A_n}(x) &≤& \displaystyle \sum_{n=1}^{M} b_n 1_{B_n}(x) \\ \\ \displaystyle\sum_{n=1}^{N}a_n μ(A_n) &≤& \displaystyle \sum_{n=1}^{M} b_n μ(B_n) \end{array}\end{array}
↑ が分かっているので
なんとなくすぐ分かりそうなものですが
\begin{array}{ccc} φ_N&≤&φ_{N+1}&≤& \cdots &≤& f \\ \\ ψ_M&≤&ψ_{M+1}&≤& \cdots &≤& g \end{array}
「単関数近似定理」に基づく
\begin{array}{ccc} f(x)&≤&g(x) \\ \\ \displaystyle\sup \left\{ \sum_{n=1}^{N}a_n 1_{A_n}(x) \right\} &≤& \displaystyle\sup \left\{ \sum_{n=1}^{M}b_n 1_{B_n}(x) \right\} \end{array}
この前提だけでは
(任意の非負可測関数は単関数で近似できる)
欲しい結論である ↓ について
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int φ_N &≤& \displaystyle\int ψ_M & & ? \end{array}
直接的に示すことができません。
(ルベーグ積分は単関数積分値の上限をとる)
ルベーグ積分の定義と上限
これを示すには
「 f,g に収束する非負単関数」の
\begin{array}{lclcl} && f &≤& g \\ \\ φ_N &≤& f &≤& g \\ \\ φ_N &≤& & {} & g \end{array}
この事実だけに留まらず
(前提より φ_N は g に近似する候補の1つでもある)
\begin{array}{ccc} \int f&=& \displaystyle\sup\left\{ \int φ \right\} \end{array}
「ルベーグ積分」の定義に加えて
「上限」の定義も使う必要があります。
上限の大小関係とルベーグ積分の定義
「非負可測関数」の「単調性」を示す
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int f &≤& \displaystyle \int g \end{array}
この話において厄介なのは
\begin{array}{l} \displaystyle\sup \left\{ \sum_{n=1}^{N}a_n 1_{A_n}(x) \right\} \\ \\ \displaystyle\sup \left\{ \sum_{n=1}^{M}b_n 1_{B_n}(x) \right\} \end{array}
これらの「見分けが難しい」点です。
「単関数近似定理」より
\begin{array}{ccc} φ_N &≤& f &≤& g \\ \\ \displaystyle \sum_{n=1}^{N}a_n 1_{A_n}(x) & ≤ & \displaystyle\sup \left\{ \sum_{n=1}^{N}a_n 1_{A_n}(x) \right\} \end{array}
「非負単関数 φ_N 」が
「 f に近似できる」のと同様に
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_D φ_N &\in& \displaystyle\left\{ \int_D ψ_M \right\} \end{array}
φ_N は「 g に近似する可能性もある」ので
( f と g が一致する場合など)
↓ を明確に区別するというのは
\begin{array}{ccc} \displaystyle\left\{ \int_D φ_N \right\} &?& \displaystyle\left\{ \int_D ψ_M \right\} \end{array}
思っている以上に難しかったりします。
(この辺りの定義を理解していない場合)
ルベーグ積分の正確な定義と集合の違い
自明のこととして流してきましたが
\begin{array}{ccc} \sup & \{ ? \} \end{array}
「上限をとる対象(上限の右のやつ)」について
この辺りで明確にしておきます。
結論から行くと
「上限」の横に書かれているものは「集合」です。
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_D f &=& \displaystyle \sup \left\{ \int_D φ \right\} \end{array}
例えば「ルベーグ積分」の定義の場合
\begin{array}{ccc} φ & \mathrm{is} & \mathrm{Simple \,\, Function} \end{array}
\begin{array}{ccc} \displaystyle \left\{ \int_D φ \right\} &←& \displaystyle \left\{ \int_D φ \,\, \middle| \,\, 0≤φ≤f \right\} \end{array}
正確にはこのようになっていて
\begin{array}{lclcl} && f &≤& g \\ \\ φ &≤& f &≤& g \\ \\ φ &≤& & {} & g \end{array}
この集合には
「条件を満たす単関数積分の全て」が含まれています。
(より正確には積分値である定数が含まれている)
上限をとる集合と大小関係
以上のことを念頭に
↓ の大小関係が成立するという前提を考えると
\begin{array}{lclcl} && f &≤& g \\ \\ φ &≤& f &≤& g \\ \\ φ &≤& & {} & g \end{array}
g のルベーグ積分の右辺にある集合は
\begin{array}{l} \displaystyle \left\{ \int_D ψ \,\, \middle| \,\, 0≤ψ≤g \right\} \\ \\ \displaystyle \left\{ \int_D ψ \,\, \middle| \,\, 0≤ψ ≤f ≤g \right\} ∪ \left\{ \int_D ψ \,\, \middle| \,\, f< ψ ≤g \right\} \end{array}
こうですから
\begin{array}{ccl} [0,1) &=& \{ x \in R \mid 0≤x<1 \} \\ \\ [0,1) &=& \{ y \in R \mid 0≤y<1 \} \end{array}
f 以下の範囲にある ψ は
\begin{array}{ccc} \displaystyle \left\{ \int_D φ \,\, \middle| \,\, 0≤ φ ≤f \right\} &=& \displaystyle \left\{ \int_D ψ \,\, \middle| \,\, 0≤ψ ≤f ≤g \right\} \end{array}
φ と同じく「 f 以下の単関数」なので
( φ と ψ の定義は両方とも f 以下の単関数)
\begin{array}{ccc} \displaystyle \left\{ \int_D ψ \,\, \middle| \,\, 0≤ψ≤g \right\} \end{array}
この集合の中に
φ の積分は全て含まれていると言えます。
(これは前提にある大小関係から分かる結果)
まとめると
\begin{array}{ccc} f &≤& g \\ \\ \displaystyle \left\{ \int_D φ \,\, \middle| \,\, 0≤φ≤f \right\} &⊂& \displaystyle \left\{ \int_D ψ \,\, \middle| \,\, 0≤ψ≤g \right\} \end{array}
つまり2つの集合の関係はこうです。
( φ と ψ には条件以外の縛りが無い)
上限下限と包含関係
ここまで分かれば
「包含関係」と「上限下限」の
\begin{array}{lcl} A⊂B &\to& \left\{ \begin{array}{lcl} \sup A & \textcolor{pink}{≤} & \sup B \\ \\ \inf A & \textcolor{skyblue}{≥} & \inf B \end{array} \right. \end{array}
この関係が分かっていれば
\begin{array}{ccc} \displaystyle int f &≤& \displaystyle \int g \end{array}
この結論はすぐに得ることができます。
(広い方がより大きく小さくとれる感じ)
念のため確認しておくと
これについては
\begin{array}{lcl} A &=& \{ x \mid 0≤x≤1 \} \\ \\ B &=& \{ x \mid -1≤x≤2 \} \\ \\ &=& \{ x \mid -1≤x<0 \}∪\{ x \mid 0≤x≤1 \}∪\{ x \mid 1<x≤2 \} \end{array}
これで納得できると思います。
(値を文字に置き換えれば一般性が証明できる)
ルベーグ積分の定義と上限の関係
以上
内容をまとめると
\begin{array}{lcl} \displaystyle\int_D f &=& \displaystyle\sup \left\{ \int_D φ \,\, \middle| \,\, 0≤φ≤f \right\} \\ \\ \displaystyle\int_D g &=& \displaystyle\sup \left\{ \int_D ψ \,\, \middle| \,\, 0≤ψ≤g \right\} \end{array}
f,g のルベーグ積分の定義はこうで
(単関数積分の基礎になる測度に基づく定義)
\begin{array}{lcl} \begin{array}{ccc} f &≤& g \\ \\ \displaystyle \left\{ \int_D φ\,\, \middle| \,\, 0≤φ≤f \right\} &⊂& \displaystyle \left\{ \int_D ψ \,\, \middle| \,\, 0≤ψ≤g \right\} \end{array} \end{array}
前提である大小関係 f≤g より
「単関数の積分を集めた集合」はこうなることから
その上限をとれば
\begin{array}{ccc} \displaystyle \sup\left\{ \int_D φ \,\, \middle| \,\, 0≤φ≤f \right\} &≤& \displaystyle \sup\left\{ \int_D ψ \,\, \middle| \,\, 0≤ψ≤g \right\} \\ \\ \displaystyle \int_D f &≤& \displaystyle\int_D g \end{array}
これがそのまま「ルベーグ積分」の定義になるので
これにより、欲しかった関係は示されたと言えます。
一般の可測関数の場合
以上のことが分かると
\begin{array}{ccc} f &≤& g \\ \\ 0 &≤& g-f \end{array}
前提から明らかなこの結果と
\begin{array}{rcr} 0 &≤& g-f \\ \\ \displaystyle \int 0 &≤& \displaystyle \int g-f \end{array}
「非負可測関数の単調性」
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int (g-f) &=& \displaystyle \int g - \int f \end{array}
そして「ルベーグ積分の線型性」から
「一般の可測関数の単調性」については
\begin{array}{rcl} \displaystyle \int 0 &≤& \displaystyle \int g - \int f \\ \\ \displaystyle \int f & ≤ & \displaystyle \int g \end{array}
すぐに求めることができます。
ルベーグ積分とゼロ関数
直感的には明らかですが
念のため補足しておくと
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int 0 &=& 0 \end{array}
f=0 の時の非負単関数については
\begin{array}{ccc} 0 &≤& φ &≤& f \\ \\ 0 &≤& φ &≤& 0 \end{array}
ルベーグ積分の定義より
常に 0 を返す単関数になると言えるので
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_D φ_N &=& \displaystyle \sum_{n=1}^{N} c_n μ(D) \\ \\ \displaystyle\int_D \sum_{n=1}^{N}0*1_{D_n} &=& \displaystyle \sum_{n=1}^{N} 0* μ(D) &=& 0 \end{array}
「非負単関数の積分」の定義より
\begin{array}{ccl} \displaystyle \int 0 &=& \displaystyle \sup\left\{ \int φ_N \,\, \middle| \,\, 0≤φ_N≤0 \right\} \\ \\ &=& \displaystyle \sup\{ 0 \} \end{array}
上限は必ず 0 になりますから
ゼロ関数の積分値は 0 になります。
極限と積分
直感的には常に成立しそうですが
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_D \left( \lim_{n\to\infty} f_n \right) \, dμ &=& \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_D f_n \, dμ \\ \\ \displaystyle \int_D \left( \lim_{n\to\infty} φ_n \right) \, dμ &=& \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_D φ_n \, dμ \end{array}
実はこの操作は保証されていません。
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_D \left( \lim_{n\to\infty} f_n \right) \, dμ &=& \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_D f_n \, dμ \end{array}
現時点では
これは事実ではなく推定になります。
(これが成立する最も広い条件を提示するのが優収束定理)
連続関数の積分と極限
最も単純なパターンである
「連続関数 f_n 」が「連続関数 f 」に収束する
\begin{array}{rcc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \sup |f_n(x)-f(x)| &=& 0 \\ \\ \sup |f_n(x)-f(x)| &<& ε \end{array}
つまり「一様収束する」パターンでは
(一様収束については長くなるので別記事で)
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_D \left( \lim_{n\to\infty} f_n \right) \, dμ &=& \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_D f_n \, dμ \end{array}
これは問題無く成立します。
連続関数のパターンでは
証明は少し大変です。
\begin{array}{lcl} | f(x) - α| &<&ε \end{array}
「収束」を考える過程で
\begin{array}{ccc} f(x) &≤& g(x) \\ \\ \displaystyle\int_{a}^{b} f(x) \,dx &≤& \displaystyle\int_{a}^{b} g(x) \,dx \end{array}
「積分の単調性」より
(ここではリーマンでもルベーグでも良い)
\begin{array}{lcl} \displaystyle \left| \int_{a}^{b} f_n(x) \,dx - \int_{a}^{b} f(x) \,dx \right| \\ \\ \displaystyle \left| \int_{a}^{b} \Big( f_n(x) - f(x) \Bigr) \,dx \right| \end{array}
目標となる関係から導かれる
\begin{array}{ccc} -|f(x)| &≤& f(x) &≤& |f(x)| \\ \\ \displaystyle\int_{a}^{b} -|f(x)| \,dx &≤& \displaystyle \int_{a}^{b} f(x) \,dx &≤& \displaystyle\int_{a}^{b} |f(x)| \,dx \\ \\ \displaystyle - \int_{a}^{b} |f(x)| \,dx &≤& \displaystyle \int_{a}^{b} f(x) \,dx &≤& \displaystyle\int_{a}^{b} |f(x)| \,dx \\ \\ -α &≤& \displaystyle \int_{a}^{b} f(x) \,dx &≤& α \end{array}
この関係を認めるなら
\begin{array}{lcl} \displaystyle \left| \int_{a}^{b} f(x) \, dx \right| &≤& \displaystyle \int_{a}^{b} \left| f(x) \right| \, dx \\ \\ \displaystyle \left| \int_{a}^{b} \Big( f_n(x) - f(x) \Bigr) \,dx \right| &≤& \displaystyle \int_{a}^{b} \Big| f_n(x) - f(x) \Bigr| \,dx \end{array}
これが成立すると言えるため
(この関係を得るための ↑ )
後は図形の見た目から
そのまま「底辺×高さ」を考えてみると
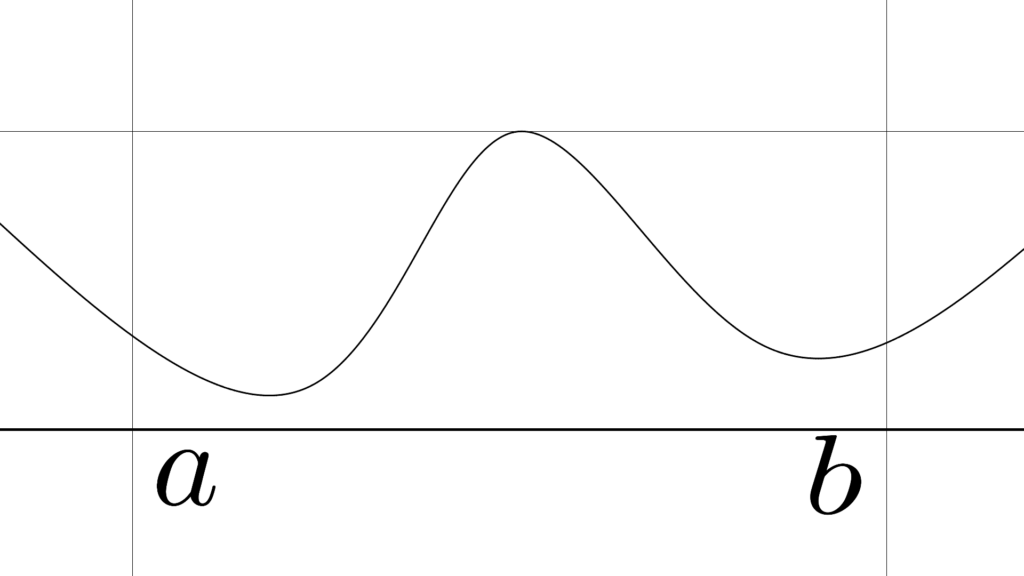
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{a}^{b} \Big| f_n(x) - f(x) \Bigr| \,dx &≤& (b-a)\sup |f_n(x)-f(x)| \end{array}
面積の関係はこのようになると言えることから
(このようにとれば一様収束の前提が使える)
\begin{array}{lcl} \displaystyle \left| \int_{a}^{b} f_n(x) \,dx - \int_{a}^{b} f(x) \,dx \right| &<&(b-a) ε \end{array}
結果
「収束する」という結論が導かれます。
(有限定数倍の ε も任意の正の実数)
ということは
まとめると
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{a}^{b} \lim_{n\to\infty} f_n(x) \,dx&=& \displaystyle \int_{a}^{b} f(x) \,dx &&前提 \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_{a}^{b} f_n(x) \,dx &=& \displaystyle \int_{a}^{b} f(x) \,dx && 結論 \end{array}
以上の結果から
この欲しかった結論は示されたと言えます。
(連続関数と一様収束がこれの前提になる)
項別積分の定理
「連続関数」のパターンは示せたので
\begin{array}{lcl} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_{a}^{b} φ_n(x) \,dx &=& \displaystyle \int_{a}^{b} \lim_{n\to\infty} φ_n(x) \,dx \end{array}
次は「単関数」に関わる
「項別積分」について解説してみます。
補足しておくと
「項別積分」っていうのは
\begin{array}{rcr} \displaystyle \sum_{n=1}^{\infty} \int_{a}^{b} f_n(x) \,dx &=& \displaystyle \int_{a}^{b} \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \,dx \\ \\ \displaystyle \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \int_{a}^{b} f_n(x) \,dx &=& \displaystyle \int_{a}^{b} \lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N} f_n(x) \,dx \end{array}
要は ↑ みたいな感じのやつで
この概念を考えていくと出てくる
\begin{array}{lcl} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_{a}^{b} f_n(x) \,dx &?& \displaystyle \int_{a}^{b} \lim_{n\to\infty} f_n(x) \,dx \end{array}
この操作がどうなるのかという疑問から
(極限と積分が交換可能か問題)
「極限と積分」の「交換」
これが成立する条件を調べる過程で
\begin{array}{lcl} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_{a}^{b} f_n(x) \,dx &=& \displaystyle \int_{a}^{b} \lim_{n\to\infty} f_n(x) \,dx \end{array}
「単関数」について
このようになるという結論が導かれます。
(こうなるための条件が整備されていく)
単関数列での項別積分の定理
再度確認しておくと
「極限」と「積分」について
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{a}^{b} \lim_{n\to\infty} f_n(x) \,dx&=& \displaystyle \int_{a}^{b} f(x) \,dx \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_{a}^{b} f_n(x) \,dx &=& \displaystyle \int_{a}^{b} f(x) \,dx \end{array}
「連続関数」のパターンは示せました。
しかし
「連続」とは限らない
\begin{array}{lcl} φ_2(x)&=& c_1 1_{D_1}(x) + c_2 1_{D_2}(x) \end{array}
「単関数」では
(単関数はだいたい不連続関数)
\begin{array}{lcl} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_{a}^{b} φ_n(x) \,dx &=& \displaystyle \int_{a}^{b} \lim_{n\to\infty} φ_n(x) \,dx \end{array}
まだこうなることを示せていません。
まあ直感的には明らかなんですが
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{[a,b]} \lim_{n\to\infty} φ_n(x) \,dx&=& \displaystyle \int_{[a,b]} f(x) \,dx \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_{[a,b]} φ_n(x) \,dx &=& \displaystyle \int_{[a,b]} f(x) \,dx \end{array}
この成立はいろんな話の基礎になるので
ここから話を発展させるために
ここできちんと確かめておきます。
前提の確認と着地
まずこの場合の「単関数」ですが
「単関数近似定理」を使うために
\begin{array}{ccc} φ_n&≤&φ_{n+1}&≤& \cdots &≤&f \end{array}
φ_n の関数列は「単調増加」とし
f を「ほとんど全てで有限値となる関数」とします。
(発散する場合は上下関係が明らかなので自明とする)
確認しておくと
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_{D} \lim_{n\to\infty} φ_n(x) \,dx & = & \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_{D} φ_n(x) \,dx \end{array}
着地はこうです。
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} φ_n &=& f \end{array}
そして多少きつめではありますが
\begin{array}{ccc} φ_n&≤&φ_{n+1}&≤& \cdots &≤&f \end{array}
前提はこうであるとします。
(きついけどこういう単関数の使用頻度が一番高い)
単関数の積分と上限
確認しておくと
\begin{array}{lcl} \displaystyle\int_D φ_N \, dμ &=& \displaystyle \sum_{n=1}^{N} a_n μ(D_n) \end{array}
「単関数の積分」はこうです。
(ルベーグ測度に因む妥当な定義)
そして「単関数の積分の単調性」から
\begin{array}{ccc} φ_N&≤&φ_{N+1} \\ \\ \displaystyle \int_D φ_{N} \, dμ &≤& \displaystyle \int_D φ_{N+1} \, dμ \end{array}
「単関数の積分」の数列が
「単調増加列である」ことは明らかですから
「非有界である」場合
\begin{array}{ccc} φ_N &≤& f \\ \\ \displaystyle \int_D φ_{N} \, dμ &≤& \displaystyle \int_D f \, dμ &=& \infty \end{array}
上下関係は明らかであるため
この場合は明らかであるとして
「有界である」パターンを考えると
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int_D φ_{N} \, dμ \end{array}
「有界単調数列は収束すること」より
これは「収束する」と言えるので
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int_{D} φ_N(x) \,dx & = &\displaystyle \sup\left\{ \displaystyle \int_D φ_{N} \, dμ \right\} \end{array}
極限をとると
これは「上限」に至ります。
(上限の存在公理により保証される)
単関数積分の条件とルベーグ積分の定義
ということは
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int_{D} φ_N(x) \,dx & = &\displaystyle \sup\left\{ \displaystyle \int_D φ_{N} \, dμ \right\} \end{array}
この形が
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_D f \, dμ &=& \displaystyle \sup\left\{ \displaystyle \int_D φ_{N} \, dμ \right\} \end{array}
「ルベーグ積分の定義そのもの」であることより
(これを保証するために定義されたとも言える)
結果として
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int_{D} φ_N(x) \,dx & = & \displaystyle \int_{D} \lim_{N\to\infty} φ_N(x) \,dx\end{array}
欲しかったこの関係は示されたと言えます。
(つまり定義によってこの定理は導かれる)
単調収束定理 Monotone Convergence
以上の結果を用いると
\begin{array}{lclcr} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n &=& \displaystyle \int \lim_{n\to\infty} f_n && f_n \to f \\ \\ \displaystyle \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \int f_n &=& \displaystyle \int \lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N} f_n && \displaystyle \sum_{n=1}^{N} f_n \to f \end{array}
「非負値可測関数」についても
この操作が可能であることを証明できます。
(この定理についている名前が単調収束定理)
単調収束定理の証明
前提はそのまま
\begin{array}{ccc} 0 &≤& f_n &≤& f_{n+1} &≤& \cdots &≤& f \end{array}
「 f_n が単調増加列である」こと
\begin{array}{ccc} \displaystyle\lim_{n\to\infty} f_n &=& f \end{array}
「上限」がこうなること
それだけで、追加はありません。
(厳密には可測関数周りの定義が必要)
より正確には
「条件を追加せずに示したい」というのが先にあって
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n &=& \displaystyle \int \lim_{n\to\infty} f_n \end{array}
その上で同様の結論を得たいというのが
この定理を示す上でのスタートラインになります。
(直感的には同じだけどまだこの時点では仮説)
ただその肝心の証明ですが
「非負可測関数の上限」をとる意味はあまり無いので
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_D f \, dμ &=& \displaystyle \sup\left\{ \displaystyle \int_D φ_N \, dμ \right\} \\ \\ \displaystyle \int_D f \, dμ &?& \displaystyle \sup\left\{ \displaystyle \int_D f_n \, dμ \right\} \end{array}
前回と同様の流れでは示すことができません。
となると直接的な比較方法は不明なので
「同じであること」を意味する結果として
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int f_n &≤& \displaystyle \int f \\ \\ \displaystyle \int f_n &≥& \displaystyle \int f \end{array}
「両側の大小比較をとる」など
間接的な方法を採用する必要があります。
分かりやすい大小関係
前提から導かれる
「ルベーグ積分の単調性」より
\begin{array}{rcr} f_n &≤& f_{n+1} \\ \\ \displaystyle \int f_n &≤& \displaystyle \int f_{n+1} \\ \\ f_n &≤& f \\ \\ \displaystyle \int f_n &≤& \displaystyle \int f \end{array}
「全ての n で」こうなることから
(この記事ではこれを帰納的定義より明らかとする)
「有界単調数列の収束」を考えると
(有界が前提なら必ず何かしらの値に収束する)
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n &≤& \displaystyle \int f \end{array}
こちら側の大小関係はすぐに導くことができます。
( f の積分は上界ではあるが上限とは限らない)
ややこしい方の大小関係
これが分かった上で「同じである」ことを示す
これにはもう片側の大小関係が必要なんですが
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int f_n &≥& \displaystyle \int f \end{array}
結論から行くと
これは「関数の比較」から
\begin{array}{ccrcc} & & f_n &≤& f \\ \\ φ_N &≤& \displaystyle \lim_{n\to\infty} f_n &≤& f \end{array}
「大小関係を誤魔化す」という形で
\begin{array}{lcl} \displaystyle \lim_{N\to\infty} φ_N &=& f \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} f_n &=& f \end{array}
けっこう強引に求められます。
( f から小方向に離して大小を定める辺りが複雑)
ほぼゴール地点からの逆算です。
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int φ_N≤\int f_n & \overset{N,n\to\infty}{\longrightarrow} & \displaystyle \int f≤\int f \end{array}
感覚的にはこんな感じのことをするわけですが
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int φ_N&≤& \displaystyle\int f_n && ? \\ \\ \displaystyle \int φ_N&≤& \displaystyle\int f && 〇 \end{array}
これを理解するには
「極限と上限」の厳密な理解が必要になります。
(この時点ではどの順番で N,n を動かすか不明)
都合の良い大小関係を構築できるのか
示したい形である ↓ から
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int f_n &≥& \displaystyle \int f \end{array}
「無限」を取り除いて
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int φ_N &≤& \displaystyle \int f_n \end{array}
この形を得るには
↓ の形を使う必要があるわけですが
\begin{array}{ccc} φ_N &≤& f_n \end{array}
これは前提から導かれるわけではありません。
(都合よくこうならない可能性が普通にある)
実際、どの順番でどのように変数を動かすか
これが定まってない状態だと
\begin{array}{ccc} φ_N &≤& f_n \end{array}
好きに n,N を定めることができるため
\begin{array}{ccc} φ_N &≤& f_n && ? \\ \\ f &≥& f_n && N\to M \end{array}
欲しい結果になる有限の n が存在しない
\begin{array}{ccc} f_n &=& \displaystyle \frac{\lfloor nx \rfloor }{n} \\ \\ φ_2 &=& \displaystyle 0 \cdot 1_{\left[ 0,\frac{1}{2} \right)}(x) + \frac{1}{2}\cdot 1_{\left[ \frac{1}{2},1 \right)}(x) \\ \\ f &=& x \end{array}
そんな可能性が普通に考えられます。
( f に収束するスピードが異なる単関数など)
例外と床関数
補足しておくと
\begin{array}{ccc} \lfloor x \rfloor &\in& 整数 \end{array}
これは「小数点以下切り捨ての整数値」を取り出す
(この認識は正確には正の範囲に限ります)
\begin{array}{ccc} \lfloor 1 \rfloor &=& 1 \\ \\ \lfloor 2.9 \rfloor &=& 2 \\ \\ \lfloor π \rfloor &=& 3 \end{array}
「床関数」と呼ばれるもので
(実数を整数に変換する役割を持つ)
\begin{array}{ccc} \lfloor x \rfloor &=& \left\{ \begin{array}{ccl} 0 && x\in [0,1) \\ \\ 1 && x\in [1,2) \\ \\ 2 && x\in [2,3) \\ \\ \vdots \\ \\ n && x\in [n,n+1) \\ \\ \vdots \end{array} \right. \end{array}
厳密にはこのように定義されています。
(つまりこれは拡大実数値単関数)
必ず f_n が大きくなるようにする
↑ の問題を解消したい
\begin{array}{ccc} f &≥& f_n \end{array}
そのためには
「こうならない n がある」
という状態を維持する必要があって
そこから
そのための方法の1つとして
( f より f_n が大きくなる n の存在を保証したい)
\begin{array}{ccc} 0&<&p&<&1 \end{array}
「その範囲ならどんな値でも良い」ような
(後で調整のための値 p を動かして f にできる)
\begin{array}{rcr} pf &≤& f_n \\ \\ \displaystyle \int pf &≤& \displaystyle \int f_n \end{array}
常にこのようにできる
『調整できる値 p の存在』を考えることができます。
(どの p を選んでも n が存在する)
確認しておくと
この p を任意とする場合
\begin{array}{lcc} \displaystyle\lim_{ p \to 1} pf &=& f \\ \\ \displaystyle\lim_{p\to 1} pφ_N &=& φ_N \end{array}
このようになる「極限」を定義できるのは明らか。
( p の任意性より極限の定義を満たす)
ということは
この p に定数 p_* を入れた後
任意に n を定めるという形で動かせば
\begin{array}{ccc} p_*f &<& f \\ \\ p_*f &<& \displaystyle \lim_{n\to\infty} f_n \end{array}
n を下から抑える
そんな有限値 N の存在を保証することができ
\begin{array}{ccc} \exists N & \forall n≥N & pf≤f_n \end{array}
その結果として
このようになる n の存在を保証できます。
(極限操作が可能なまま f 以上の f_n とできる)
論理式で厳密に整理してみる
ここまで
「量化子」の扱いに慣れてない内だと
だいぶ分かり辛いかもしれませんが
\begin{array}{ccc} P &\equiv& \displaystyle \int pf ≤ \int f_n \end{array}
これを適当に命題 P とでもしておくと
\begin{array}{ccc} \begin{array}{rcr} pf &≤& f_n \\ \\ \displaystyle \int pf &≤& \displaystyle \int f_n \end{array} \\ \\ ↓ \\ \\ \begin{array}{ccc} \displaystyle \int pf &≤& \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n \end{array} \end{array}
↑ の話を論理式で表現したら
\begin{array}{ccc} \forall p \in (0,1) & \exists N & \forall n≥N & P \end{array}
欲しい命題はこんな感じになります。
( p を好きに決める → 都合の良い N が存在)
分かり難いかもですが
ざっと解説しておくと
まず p が (0,1) の範囲ならなんでも良くて
\begin{array}{ccc} pf &≤& f_n &≤& f \end{array}
f_n の上限が f である以上
pf とこのようなる f_n は必ず存在することから
( pf が f と一致することは無い)
\begin{array}{ccc} \displaystyle\int pf &≤& \displaystyle\int f_n \end{array}
「可測関数の積分の単調性」より
このようになる n は必ず存在すると言える。
( ↑ の上下関係が必ず成立する以上こちらも必ず成立)
そして p は任意であることから
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{p\to 1} pf &=& f \end{array}
「後から」調整できるので
結果、この結論を得ることができる。
ややこしいかもしれませんが
\begin{array}{cccr} & {} & & p_*f ≤ f_{n_*} \\ \\ & \exists N & \forall n≥N & p_*f ≤ f_{n} \\ \\ \forall p & \exists N & \forall n≥N & pf ≤ f_{n} \end{array}
以上がこれまでで実現できたものになります。
(これで内側から順に極限をとれる)
厳密には可測関数ではダメ
直感的に考えると
\begin{array}{ccc} pf &≤& f_n \end{array}
このようになる n は存在しそうです。
(関数のほとんど全ての変数で ↑ が成立する)
しかし「可測関数」の範囲は非常に広いため
実は以下のような反例が存在し
(収束先が常に 1 か 0 にしたい ↓ )
\begin{array}{ccc} f_n(x) &=& \left\{ \begin{array}{ccl} 0 && x\in (n,\infty) \\ \\ 1 && x\in (-\infty,n] \end{array} \right. \end{array}
↑ は必ず成立するわけでは無い
ということが事実として判明してしまいます。
(極限を許される可測関数の範囲の広さが原因)
反例の確認
確認しておくと
f_n(x)≤f(x) であることや
「非負可測関数」「単調増加」を実現した上で
\begin{array}{ccc} f_n(x) &=& \left\{ \begin{array}{ccl} 0 && x\in (n,\infty) \\ \\ 1 && x\in (-\infty,n] \end{array} \right. \end{array}
「収束先 f 」を一定にすると
\begin{array}{rcl} f(x) &=& 1 \\ \\ pf(x) &=& \displaystyle \frac{1}{2} f \end{array}
「任意の実数 x 」では
\begin{array}{ccc} pf(x) &≥& f_n(x) && (n,\infty) \\ \\ pf(x) &≤& f_n(x) && (-\infty,n] \end{array}
左の収束先の pf(x) は
f(x)=1 である以上、常に p なので
\begin{array}{ccc} pf(x) &≤& f_n(x) && x\not\in (n,\infty) \\ \\ p &>& 0 && x \in (n,\infty) \end{array}
これは「任意の実数 x では」成立しません。
まとめると
\begin{array}{ccc} pf(x) &\textcolor{pink}{>}& f_n(x) && x\in (n,\infty) \end{array}
この範囲では常にこうなることから
\begin{array}{ccc} pf(x) &≤& f_n(x) \end{array}
(n,\infty) の範囲に x がある場合
このようになる n は存在しないと言えます。
(つまり不成立を示す反例になる)
可測関数にするのは後
このような反例が存在する以上
「可測関数」という範囲には制限が必要です。
\begin{array}{ccc} pf=p\sup\{φ\} &&\to&& pφ \end{array}
そうなると
丁度良い制限は何かって話なんですが
\begin{array}{ccc} \sup\{ φ \} &=& f \end{array}
「単関数近似定理」を考えると
「後で上限をとる」ことで近似が可能な
\begin{array}{rcc} φ &≤& f_n \\ \\ pφ &≤& f_n \end{array}
「有限」の範囲で定義可能である
「 f に収束する非負単関数 φ 」
これが良い感じに使えそうだと予想できます。
非負単関数なら問題が無いのか
「非負可測関数」では問題があった
なら「非負単関数」でも問題がありそうですが
\begin{array}{rcc} φ &≤& f_n \\ \\ pφ &≤& f_n \end{array}
実は「非負単関数 φ 」と比較する場合
全ての x でこのようになる n は必ず存在します。
(省略してますが関数には変数が定義されてます)
存在することの証明
確認のため
↑ で紹介したような反例にならって
\begin{array}{rcr} φ &≤& f_n \\ \\ \displaystyle \int_D φ &≤& \displaystyle \int_D f_n \end{array}
「積分範囲 D 」の中で
「ある φ では n が存在しない」と仮定してみます。
(これが否定されれば必ず存在することになる)
すると
「反例になる φ 」を考えた時
\begin{array}{ccc} \exists x_*\in D & pφ(x) > f_n(x) \end{array}
このように不等式を満たさない x_* が
積分範囲 D の中に存在するのは確実
(この x_* が無いなら仮定は矛盾する)
ということは
それを集合として定義すると
(定数として扱うのでそれを全部集めてみる)
\begin{array}{ccc} D_n &=& \{ x\in D \mid pφ(x) ≤ f_n(x) \} \end{array}
これが「全ての n で D と一致しない」
そんな x の集合(積分範囲の一部)になります。
( n がどれだけ大きくても x_* が存在する)
ここまで定めた上で
この集合と前提を考えると
\begin{array}{ccc} f_n &≤& f_{n+1} \\ \\ D_n &⊂& D_{n+1} \end{array}
上限の話でした話と同様の比較を行えば
D_n が「単調増加列」であることは明らかですから
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} f_n(x) &=& f(x) \end{array}
「 f_n の上限が f である」ことも考えると
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \bigcup_{n=1}^{N} D_n &=&D \end{array}
現時点では予想になりますが
この集合は必ずこうなるはずだと考えられます。
まとめると
\begin{array}{ccc} x_* & \in &\displaystyle\bigcup_{n=1}^{\infty} D_n \end{array}
この無限和集合は D と一致するはずであることから
このような x_* \in D は存在しないと予想できます。
矛盾の導出
整理しておくと
\begin{array}{ccc} \forall x\in D & pφ(x) ≤ f_n(x) \end{array}
反例の形を参考に
「全ての n でこうならない φ が存在する」と仮定すると
\begin{array}{ccc} pφ(x_*) &>& f_n(x_*) && x_* \in D_* \end{array}
ある範囲 D_* では
「 φ との比較では全ての n でこうならない」
\begin{array}{ccc} \exists x_*\in D & pφ(x_*) > f_n(x_*) \end{array}
つまり「全ての n 」で
「こうなる x_* が存在する」ということが導かれます。
(ここまでが間違ってると予想される仮定)
ここから
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} f_n(x_*) &=& f(x_*) \end{array}
「 f_n は f に収束する」という事実を利用すれば
(この制限により反例のような単関数は構成不可)
\begin{array}{ccc} pφ &<& φ &≤& f \end{array}
φ と比較可能な f を得ることが可能なので
(反例のような関数ではこうならない)
\begin{array}{ccc} f_n(x_*) &<& pφ(x_*) \end{array}
全ての n でこうなる x_* の存在から
\begin{array}{ccc} \displaystyle\lim_{n\to\infty} f_n(x_*) &<& pφ(x_*) \end{array}
これは明らかですから
以上の事実から
\begin{array}{ccc} f(x_*) &<& pφ(x_*) \end{array}
このような関係が得られてしまいます。
(この時点で明らかに矛盾した結果)
ということは
\begin{array}{ccc} f(x_*) &<& pφ(x_*)&<& φ(x_*) \end{array}
p の定義を考えると
この関係は確実に成立すると言えるので
\begin{array}{ccc} f(x_*) &<& φ(x_*) \end{array}
φ の定義より
これは確実に矛盾していますから
これで「仮定が間違ってる」ということが示されました。
↑ の補完
これでほとんどの場合で矛盾を示せましたが
0<φ の時でない場合
\begin{array}{ccc} f(x_*) &<& pφ(x_*)&<& φ(x_*) \end{array}
「 pφ<φ の形から矛盾を導く」
この理屈は厳密には使えないため
\begin{array}{ccc} f(x_*) &<& 0 \end{array}
実は φ=0 のパターンは
別で考える必要があります。
ただ話自体はほぼ同じで
(矛盾を示すための理屈が異なる)
\begin{array}{ccc} 0≤f &&\to&& \lnot (f<0) \end{array}
これもまた
「 f は非負可測関数である」という定義に反することから
矛盾すること自体はすぐに導くことができます。
ややこしい大小関係の証明
以上のことから
「 f に収束する単関数 φ 」を考えると
\begin{array}{rcr} pφ &≤& f_n \\ \\ \displaystyle \int_D pφ &≤& \displaystyle \int_D f_n \end{array}
全ての x \in D で
このようになる n は確実に存在するので
(厳密には n を下から抑えられる自然数が存在する)
\begin{array}{ccr} \displaystyle \int_D pφ &≤& \displaystyle \int_D f_n \\ \\ \displaystyle \int_D pφ &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \end{array}
これは確実にこうなり
\begin{array}{rcr} \displaystyle \int_D pφ &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \\ \\ \displaystyle \lim_{p \to 1 }\int_D pφ &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \end{array}
また「任意の p で成立する」ことから
\begin{array}{rcr} \displaystyle \lim_{p \to 1 }\int_D pφ &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \\ \\ \displaystyle \lim_{p \to 1 } p\int_D φ &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \\ \\ \displaystyle \int_D φ &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \end{array}
こうなると言えて
最後に「単関数 φ の任意性」から
(順番的にはまず任意に単関数が決まって ↑ の話になる)
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_D φ &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \end{array}
左は「上限」をとれると言えるので
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_D φ &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \\ \\ \displaystyle \sup \left\{ \int_D φ \right\} &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \end{array}
その結果として
\begin{array}{ccc} \displaystyle \sup \left\{ \int_D φ \right\} &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \\ \\ \displaystyle \int_D f &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \end{array}
欲しい結論を得ることができます。
変数の順番と論理式
補足しておくと
具体的な値が入る順番は φ\to p \to n で
\begin{array}{ccc} \displaystyle \sup \left\{ \lim_{p\to 1}\int_D pφ \right\} &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \\ \\ &↑ \\ \\ \displaystyle \int_D pφ &≤& \displaystyle \int_D f_n \end{array}
極限が使えるよう一般化する順番は
↑ の順番の元になった n \to p \to φ です。
(この順番にすると矛盾無く欲しい結果が得られる)
なので論理式としては
\begin{array}{ccc} \forall φ & \forall p & \exists N &\forall n≥N & pφ ≤ f_n \\ \\ \forall φ & \forall p & \exists N &\forall n≥N &\displaystyle \int_D pφ ≤ \int_D f_n \end{array}
簡易的にはこんな感じになります。
(内側から順に極限をとれる)
関数の上下関係と積分の上下関係
また ↓ の部分に関しては
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_D pφ &≤& \displaystyle\int_D f_n \end{array}
「非負可測関数」上の話であるため
\begin{array}{lcl} pφ &≤& f_n \end{array}
「ルベーグ積分の単調性」の前提が満たされてる以上
\begin{array}{ccc} pφ ≤ f_n &⇒& \displaystyle \int_D pφ ≤ \int_D f_n \end{array}
この命題も必ず真になるので
(ある範囲で前提が真なら結論も真)
\begin{array}{ccc} \forall φ & \forall p & \exists N &\forall n≥N &\displaystyle \int_D pφ ≤ \int_D f_n \end{array}
このようになると言えます。
(命題が逆だったら保証されてない)
等しくなる
以上の結果から
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int f_n &≤& \displaystyle \int f \\ \\ &{}& \displaystyle \int f &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int f_n \end{array}
この2つの関係が得られたので
「非負可測関数」の場合でも
\begin{array}{lcl} \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int f_n &=& \displaystyle \int f \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int f_n &=& \displaystyle \int \lim_{n\to \infty }f_n \end{array}
「極限と積分の交換」は可能だと言えます。
( f_n は単調増加で f に収束する)
ファトゥの補題 Fatou’s Lemma
これは「非負値可測関数の積分」と
「下極限」についての定理で
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \liminf_{n\to\infty} f_n &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_n \end{array}
この不等式が成立する条件を与えてくれます。
(次に紹介する優収束定理の証明に必要)
補題の証明
これは「優収束定理の後」に
「優収束定理を整理する」ために得られた結果なので
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int F - f &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int F - f_n \\ \\ \displaystyle \int F + f &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int F + f_n \\ \\ \displaystyle \int \liminf_{n\to\infty} f_n &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_n \end{array}
この補題の証明は
「優収束定理の証明」の一部だと思って良いです。
(この補題は単体ではほぼ意味を持たない)
実際、目指したい形が補題そのものなので
\begin{array}{lcc} \displaystyle \int f &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_n \\ \\ \displaystyle \int \liminf_{n\to\infty} f_n &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_n \end{array}
証明はここから逆算する形で導かれます。
(後述する優収束定理でこの形が出てくる)
優収束定理からの逆算
「優収束定理」というのは
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n &=& \displaystyle \int \lim_{n\to\infty} f_n && f_n \to f \end{array}
「積分と極限の交換」が
「一般の可測関数」でも成立する
\begin{array}{ccc} |f_n|&≤&F \end{array}
このために必要な最低限の条件を提供する定理で
(この条件を優収束条件という)
これを証明するためには
\begin{array}{ccl} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n &\overset{?}{=}& \displaystyle \int \lim_{n\to\infty} f_n \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n &\overset{?}{=}& \displaystyle \int f \end{array}
この2つの比較が必要になるわけですが
この辺り
詳細な流れは後で解説するとして
\begin{array}{ccc} -F &≤& f_n &≤&F \end{array}
ともかく
これを使って示す時
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int F - f &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int F - f_n \\ \\ \displaystyle \int F + f &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int F + f_n \end{array}
こんな結果が必要になります。
(より正確にはこの形から優収束条件が予想される)
ここで必要になるのが
\begin{array}{ccc} f&=&\displaystyle\lim_{n\to\infty} f_n &=& \displaystyle\liminf_{n\to\infty} f_n \end{array}
この「ファトゥ補題」なんですが
実はこの辺りはほぼ結果論で
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \liminf_{n\to\infty} f_n &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_n \end{array}
「下極限」と「極限」の定義より
この関係は自然と導かれます。
(下極限は単調増加数列の極限なので予想可能)
極限と下極限
念のため整理しておくと
\begin{array}{ccc} \displaystyle \liminf_{n\to\infty} f_n &=& \displaystyle \lim_{N\to\infty} \inf_{N≤n} \left\{ f_n \right\} \end{array}
「下極限」の定義はこうです。
(集合を狭めて下限を大きくしていく)
そして N と N+1 の差は
最も小さい可能性のある f_N が除かれるだけなので
\begin{array}{ccc} \displaystyle\inf_{N≤n} \left\{ f_n \right\} &≤& \displaystyle\inf_{N+1≤n} \left\{ f_n \right\} \end{array}
こうなることから
これは「単調増加する数列」になります。
(詳細は別の記事で)
ということは
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \inf_{N≤n} \left\{ f_n \right\} &=& F \end{array}
「有界である」のなら
これは必ず「上限」に一致するため
(非有界の場合は \infty になるので明らかとする)
\begin{array}{rcr} \displaystyle \liminf_{n\to\infty} f_n &=& F \\ \\ \displaystyle \int \liminf_{n\to\infty} f_n &≤& \displaystyle\int F \end{array}
「可測関数の積分」の「単調性」より
\begin{array}{rcr} \displaystyle\inf_{N≤n} \left\{ f_n \right\} &≤& F \\ \\ \displaystyle \int \inf_{N≤n} \left\{ f_n \right\} &≤& \displaystyle \int F \end{array}
こういう形を考えると
良い感じの上下関係を得られそうな気がします。
関数列の下限と非負可測関数
以上のことと
「下限」について考えてみると
\begin{array}{ccc} N &≤& n \\ \\ \displaystyle\inf_{N≤n} \left\{ f_n \right\} &≤& f_n \end{array}
この2つの関係はこうなりますから
(あくまで N≤n の範囲では)
「 f_n は非負可測関数である」
これを前提とするなら
\begin{array}{rcr} \displaystyle\inf_{N≤n} \left\{ f_n \right\} &≤& f_n \\ \\ \displaystyle \int \inf_{N≤n} \left\{ f_n \right\} &≤& \displaystyle \int f_n \end{array}
「単調性」を適用するとこうなるので
(ここでも N≤n の範囲での話)
「任意に N を定める」としてもこうなり
(範囲内ならどのような N でも成立)
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \inf_{N≤n} \left\{ f_n \right\} &≤& \displaystyle \int f_n && N≤n \end{array}
「任意の N 以上の n 」でも
これは必ず成立すると言えます。
極限の定義と欲しい結果
以上のように定義できることから
「任意に N を定める」と
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \inf_{N_*≤n} \left\{ f_n \right\} &≤& \displaystyle \int f_n && N_*≤n \end{array}
これは成立すると言えて
「任意に N 以上の n を定める」と
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \inf_{N_*≤n_*} \left\{ f_{n_*} \right\} &≤& \displaystyle \int f_{n_*} && N_*≤n_* \end{array}
これが成立することから
n\to N の順番に「極限」をとっていくと
\begin{array}{rcr} \displaystyle \int \inf_{N_*≤n_*} \left\{ f_{n_*} \right\} &≤& \displaystyle \int f_{n_*} && N_*≤n_* \\ \\ \displaystyle \int \inf_{N_*≤n} \left\{ f_{n} \right\} &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n} && N_*≤n \\ \\ \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int \inf_{N≤n} \left\{ f_{n} \right\} &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n} && N≤n \end{array}
この結果が得られます。
ということは
f_n が「非負可測関数」であれば
その「下限」もまた当然「非負可測関数」になるので
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int \inf_{N≤n} \left\{ f_{n} \right\} &=& \displaystyle \int \lim_{N\to\infty} \inf_{N≤n} \left\{ f_{n} \right\} \end{array}
後は「ルベーグの単調収束定理」を使えば
\begin{array}{rcr} \displaystyle \int \inf_{N≤n} \left\{ f_{n} \right\} &≤& \displaystyle \int f_{n} && N≤n \\ \\ \displaystyle \int \lim_{N\to\infty} \inf_{N≤n} \left\{ f_{n} \right\} &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n} && N≤n \\ \\ \displaystyle \int \liminf_{n\to\infty} f_{n} &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}
この式から欲しい結論が導かれます。
(これは f_n が f に収束するという前提無しで成立)
逆ファトゥの補題
↑ の話は「上極限」に変えても
\begin{array}{ccc} \displaystyle \limsup_{n\to\infty} f_{n} &=& \displaystyle \lim_{N\to\infty} \sup_{N≤n}\{f_{n}\} \end{array}
似たような結果を得ることができ
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \limsup_{n\to\infty} f_{n} &\textcolor{pink}{≥}& \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}
これはそのまま
「逆ファトゥの補題」と呼ばれています。
(上極限の場合では不等号が逆になる)
上極限の場合では
ただし証明するとなると
「上限」の性質を使うだけではダメです。
\begin{array}{ccc} \displaystyle \sup_{N≤n}\{f_n\} &≥& \displaystyle \sup_{N+1≤n}\{f_{n}\} \end{array}
この不等号が逆になる理由でもあるんですが
(抜ける f_N が最大の場合がある)
\begin{array}{ccc} \displaystyle \sup\{f_n\} &≥& F \end{array}
「収束先 F の存在」を仮定しても
\begin{array}{ccc} \displaystyle \sup\{f_n\} &≥& f_n && n≥N \end{array}
「下極限」の時とは異なり
「単調増加列」の構築には手間が必要になるため
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \sup\{f_n\} &≥& \displaystyle \int f_n \end{array}
このままでは
同様の結果を導くことができません。
(単調収束定理を適用する準備が必要)
非負可測関数列という前提の下では
直感的に考えるのであれば
「ファトゥの補題」と同様の前提である
\begin{array}{ccc} 0 &≤& f_n \end{array}
「 f_n は全て非負可測関数列である」
この前提で「逆ファトゥの補題」は成立しそうです。
しかし
「上限」の数列は
\begin{array}{ccc} \displaystyle \sup_{N≤n}\{f_n\} &≥& \displaystyle \sup_{N+1≤n}\{f_{n}\} \end{array}
「単調減少列」であるため
同様の手順で証明することはできません。
それに
例えば ↓ のような
\begin{array}{ccc} \displaystyle n \frac{1}{n} &=& \left\{ \begin{array}{ccc} \displaystyle μ\Bigl( [0,n] \Bigr)\frac{1}{n} \\ \\ \displaystyle n μ\left( \left[ 0,\frac{1}{n} \right] \right) \end{array} \right. \end{array}
縦横「同時に引き延ばされる」ことになる
\begin{array}{lcc} \displaystyle \int \limsup_{n\to\infty} f_{n} &=& 0 \\ \\ \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} &=& 1 \end{array}
以下のような「非負可測関数」を考えると
\begin{array}{ccc} [0,1] & \mathrm{Borel}\Bigl( [0,1] \Bigr) & μ^* \end{array}
\begin{array}{ccc} f_n &=& n1_{[0,\frac{1}{n}]}(x) \end{array}
この関数から導かれる
\begin{array}{lcl} \displaystyle\int_{[0,1]} n1_{[0,\frac{1}{n}]}(x) &=& \displaystyle n\int_{[0,1]} 1_{[0,\frac{1}{n}]}(x) \\ \\ &=& \displaystyle n μ^* \left( \left[ 0,\frac{1}{n} \right] \right) \\ \\ &=& \displaystyle n \left( \frac{1}{n} - 0 \right) \\ \\ &=&1 \end{array}
積分の計算結果や
\begin{array}{ccc} \displaystyle \limsup_{n\to\infty} n1_{[0,\frac{1}{n}]}(x) &=& \left\{ \begin{array}{ccl} \displaystyle\lim_{n\to\infty} n && x=0 \\ \\ 0 && x \in (0,1] \end{array} \right. \end{array}
上極限で得られる収束先の関数から
(1点のルベーグ積分は単関数の定義より 0 に定まる)
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \limsup_{n\to\infty} f_{n} &\textcolor{pink}{≥}& \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} \\ \\ 0 &≤& 1 \end{array}
これは反例になってしまうため
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \limsup_{n\to\infty} f_{n} &\textcolor{pink}{≥}& \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}
「逆ファトゥの補題」は
「ファトゥの補題と同様の前提」では成立しない
そんな結論が導かれてしまいます。
単関数の定義と不定形
補足しておくと
↑ の積分結果は
\begin{array}{ccc} D &=& \displaystyle \bigsqcup_{n=1}^{N} D_n \\ \\ \displaystyle \int_D φ_N(x) \, dμ &=& \displaystyle \sum_{n=1}^{N} c_n μ(D_n) \end{array}
「単関数」が「有限値のみをとる」場合の話です。
(ルベーグ積分はこの上限として定義される)
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int f &=& \displaystyle \sup \left\{ \int φ \right\} \end{array}
先に「有限値 n × 0 」を行うから
(上限をとりたい集合の中身が全て 0 )
\begin{array}{ccl} f&=&\displaystyle \limsup_{n\to\infty} n1_{[0,\frac{1}{n}]}(x) \\ \\ &=& \left\{ \begin{array}{ccl} \displaystyle\lim_{n\to\infty} n && x=0 \\ \\ 0 && x \in (0,1] \end{array} \right. \end{array}
\begin{array}{ccc} \displaystyle \sup \left\{ \int φ \right\}&=& \displaystyle \sup \left\{ n μ^*\Bigl( \{ 0 \} \Bigr) + 0 \cdot μ^*\Bigl( (0,1] \Bigr) \right\} \end{array}
\infty\times 0 の形をした
「不定形」を回避することができています。
しかし「単関数」は
「拡大実数」の範囲でも定義されることがあって
\begin{array}{ccc} φ &=& \infty \end{array}
その場合
「上限をとる集合」の中には
「無限をとる単関数」も含まれ得ることから
\begin{array}{ccc} \displaystyle \sup \left\{ \int φ \right\}&=& \displaystyle \sup \left\{ \infty \cdot μ^*\Bigl( \{ 0 \} \Bigr) + 0 \cdot μ^*\Bigl( (0,1] \Bigr) \right\} \end{array}
例えば今回の場合であれば
必ず「不定形」が現れてしまいます。
拡大実数値単関数と不定形の定義
じゃあその定義だとダメじゃんって話なんですが
\begin{array}{ccc} \displaystyle \sup \left\{ \int φ \right\}&=& \displaystyle \sup \left\{ \infty \cdot μ^*\Bigl( \{ 0 \} \Bigr) + 0 \cdot μ^*\Bigl( (0,1] \Bigr) \right\} \end{array}
実はこの場合
\begin{array}{cccl} c & μ &&{}&& cμ \\ \\ 0 & \infty && \to&& cμ=0 \\ \\ \pm\infty & 0 &&\to&& cμ=0 \end{array}
これらはこのように定義されることで
(高さが無いなら 0 だし 1 点は面積を成さない)
\begin{array}{ccc} \infty \cdot μ^*\Bigl( \{ 0 \} \Bigr) &=& 0 \end{array}
生じる「不定形」を解消しています。
(直感的なルールのゴリ押しで解決)
結果
\begin{array}{rcc} \displaystyle \sup \left\{ \infty \cdot μ^*\Bigl( \{ 0 \} \Bigr) + 0 \cdot μ^*\Bigl( (0,1] \Bigr) \right\} &=& 0 \\ \\ \displaystyle \sup \left\{ n μ^*\Bigl( \{ 0 \} \Bigr) + 0 \cdot μ^*\Bigl( (0,1] \Bigr) \right\} &=& 0 \end{array}
これは問題にならず
この場合もまた結果は同様になります。
(この定義が無いと拡大実数値の範囲だとダメ)
極端な例外を排除するために
脱線しましたが
これが「逆ファトゥの補題」の問題点で
\begin{array}{ccc} \displaystyle \limsup_{n\to\infty} n1_{[0,\frac{1}{n}]}(x) &=& \left\{ \begin{array}{ccl} \displaystyle\lim_{n\to\infty} n && x=0 \\ \\ 0 && x \in (0,1] \end{array} \right. \end{array}
このような「非負可測関数」の存在を認める場合
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \limsup_{n\to\infty} f_{n} &\textcolor{pink}{≥}& \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}
こちらのパターンは必ず成立するとは言えません。
これを常に成立させるためには
\begin{array}{ccc} f_n &=& n1_{[0,\frac{1}{n}]}(x) \end{array}
これを認めないような
そんな良い感じの条件が必要で
結論から行くと
この問題は
\begin{array}{rcr} |f_n(x)| &≤& F \\ \\ \displaystyle \int |f_n(x)| &≤& \displaystyle\int F &<& \infty \end{array}
間接的に「ルベーグ可積分」を意味する
「優関数 F の存在」によって解消されます。
降って湧いてきた条件
ただこの時点では
\begin{array}{ccr} |f_n(x)| &≤& F \\ \\ & & \displaystyle\int F &<& \infty \end{array}
この「優収束条件」は意味が分からないと思います。
\begin{array}{ccc} -F&≤& f_n &≤& F \end{array}
なぜこれでうまくいくのか
↑ の時点では直感的に説明することができません。
優収束定理 Dominated Convergence
「非負可測関数」で ↓ が成立する
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f^+_n &=& \displaystyle \int \lim_{n\to\infty} f^+_n && f^+_n \to f^+ \end{array}
なら「一般の可測関数」でもこれは成立しそう
そんな感じで証明されたのがこの定理で
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n &=& \displaystyle \int \lim_{n\to\infty} f_n && f_n \to f \end{array}
この操作が可能になる
かなり広い条件をこれは提供してくれます。
優収束定理の証明
この定理の証明というと
\begin{array}{ccc} |f_n| &≤& F \end{array}
だいたいの文献では
なんかいきなり「優収束条件」なるものが出てきて
\begin{array}{lcl} 0 &≤& F-f_n \\ \\ 0 &≤& f_n-(-F) \end{array}
特に何の説明も無いまま
これを前提にして話を進められますが
この「優収束条件」とやら
\begin{array}{ccc} |f_n| &≤& F \end{array}
どこから出てきた?って話ですよね。
どう見ても飛躍してる条件です。
自然に考えるのであれば
\begin{array}{ccc} f_n &≤& f_{n+1} \end{array}
「一般の可測関数(実数)」では
まずこのように考えるのが流れとしては明瞭
(これまで単調収束定理までずっとこうだったため)
となると
この「優収束条件」という前提は
「単調増加」という前提の後に得られたはずで
\begin{array}{ccc} f_n&≤&f_{n+1} \\ \\ &↓ \\ \\ |f_n| &≤& F \end{array}
いきなり出てきてはいないはずです。
(どう見てもパっと思いつく条件ではない)
単調増加列であるという前提の下では
自然に考えるのなら
まず「単調収束定理」の形にしたいので
\begin{array}{ccc} 0 &≤& f_n + ? \end{array}
f_n が入る形として
なにかしら都合の良い非負値関数を考えたくなります。
分かりやすいのは
\begin{array}{ccc} f_1 &≤& f_2 &≤& \cdots &≤& f_n &≤& \cdots \end{array}
「単調増加」から分かる「下限 f_1 の存在」
これを使って
\begin{array}{ccc} F_n &=& f_n-f_1 \end{array}
「全ての n で」非負値関数になる形と
\begin{array}{ccc} F_{n+1}-F_n &=& (f_{n+1}-f_1)-(f_n-f_1) \\ \\ &=& f_{n+1}-f_n \end{array}
増加列 F_n を得ることにより
まず単調収束定理の前提を得てみます。
単調収束定理の適用と線型性
↑ の情報をまとめると
つまり「単調収束定理」が使えるということなので
\begin{array}{lcl} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n-f_1 &=& \displaystyle \int \lim_{n\to\infty} f_n-f_1 \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n-f_1 &=& \displaystyle \int f - f_1 \end{array}
この形が得られますから
\begin{array}{lcl} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n-f_1 &=& \displaystyle \int f - f_1 \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} \left( \int f_n - \int f_1 \right) &=& \displaystyle \int f - \int f_1 \end{array}
後は「線型性」を使って変形していくと
\begin{array}{lcl} \displaystyle\lim (a_n + c) &=& \displaystyle\lim a_n + \lim c \\ \\ &=& \displaystyle\lim (a_n) + c \end{array}
「定数」の「極限」はこうなるので
\begin{array}{lcl} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \left( \int f_n - \int f_1 \right) &=& \displaystyle \int f - \int f_1 \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} \left( \int f_n \right) - \int f_1 &=& \displaystyle \int f - \int f_1 \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n &=& \displaystyle \int f \end{array}
結果
「積分と極限の交換」が可能である
\begin{array}{lcl} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n &=& \displaystyle \int f \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n &=& \displaystyle \int \lim_{n\to\infty} f_n \end{array}
これが「一般の可測関数」の場合でも示されます。
(単調収束定理と似たような条件下で)
非負可測関数に変換することが重要
以上の証明を参考に
\begin{array}{ccc} 単調増加 \\ \\ ↓ \\ \\ 非負値可測関数の生成 \\ \\ ↓ \\ \\ 単調収束定理の適用 \end{array}
手順を逆算してみると
\begin{array}{ccc} \displaystyle\lim_{n\to\infty} f_n &=& f \end{array}
この「 f への収束」はまだ変えられませんが
(ここは最初に手を付けるとややこしくなりそう)
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n-f_1 &=& \displaystyle \int f - f_1 \end{array}
「単調増加する」ことよりも
「非負可測関数の形にする」こと
\begin{array}{ccc} 0 &≤& f_n-f_1 \end{array}
こちらの方が重要である
これがなんとなく分かります。
(収束自体は単調増加でなくても良い)
実際
\begin{array}{lcc} f_n-f_1 && 〇 \\ \\ f_n+? && ? \end{array}
これでなくとも
「非負可測関数を作れる条件」であれば
\begin{array}{lcl}\displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n-f_1 &=& \displaystyle \int f - f_1 \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n -? &=& \displaystyle \int f - ? \end{array}
これは示せそうなので
\begin{array}{ccc} f_n &≤& f_{n+1} \end{array}
この条件は一般化できそう
これがこの時点でなんとなく予想できます。
優収束条件に至るまで
これは「結果」から逆算していくと
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n - F &=& \displaystyle \int f - F \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int F - f_n &=& \displaystyle \int F - f \end{array}
「非負値可測関数を作りたい」という要望から
\begin{array}{ccc} 0 &≤& f_n - F \\ \\ 0 &≤& F - f_n \end{array}
結果的に導くことができるんですが
↑ の時点では
まだ「優収束条件」にまで発想が伸びません。
\begin{array}{ccc} 0 &≤& |f_n-F| \end{array}
「優関数」と呼ばれることになる
「都合の良い可積分関数の雛型 F 」
これが導かれるのみです。
都合の良い関数 F の存在を認める場合
念のため確認しておくと
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n - F &=& \displaystyle \int f - F \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int F - f_n &=& \displaystyle \int F - f \end{array}
これを得るために
\begin{array}{lcl} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n &=& \displaystyle \int f \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n &=& \displaystyle \int \lim_{n\to\infty} f_n \end{array}
「単調収束定理」を使いたいわけですが
(非負値可測関数かつ単調増加)
\begin{array}{ccc} G_n &=& |f_n-F| \end{array}
「単調収束定理」を使いたい場合
G_n は「単調増加列」である必要があります。
(単調増加列でなければ G_n の単調性が示せない)
あまり変えずに単調増加へ
「単調収束定理に寄せる」方向で
「前提を追加せず」に単調増加にしたい
\begin{array}{ccc} H_n&=& ?\Bigl( G_n \Bigr) \end{array}
この要請を叶えるとなると
そういった良い感じの操作が必要になります。
(基本的な数学の演算で頑張りたい)
何から手を付ければという感じですが
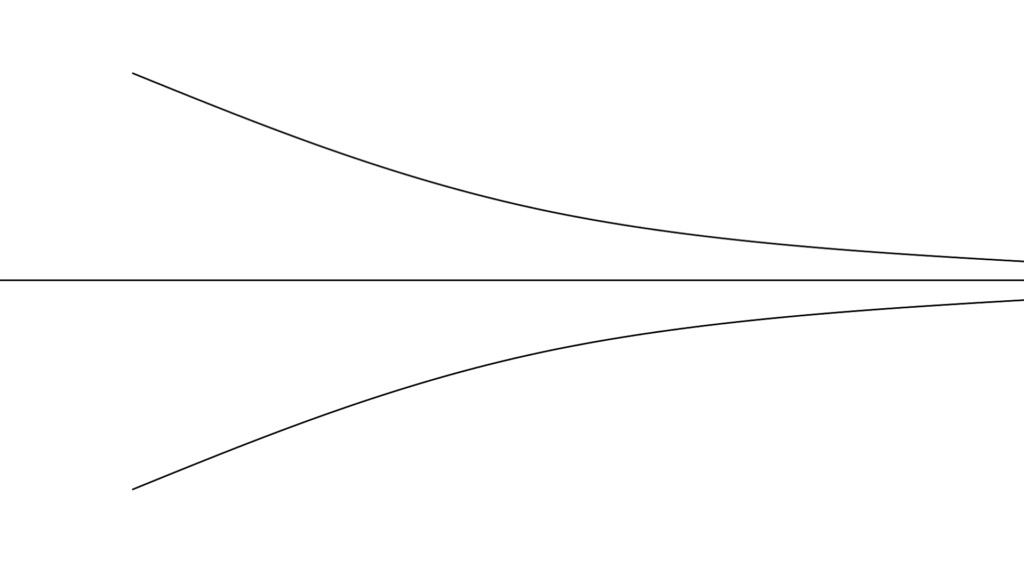
基本に立ち返ると
「単調増加」は ↑ の下曲線のようなものです。
(実現したいものの視覚的なイメージ)
となると
この図形的な感覚から
\begin{array}{ccc} \displaystyle \liminf_{n\to\infty} f_n &=& \displaystyle \lim_{N\to\infty} \inf_{N≤n} \left\{ f_n \right\} \end{array}
「下極限」は連想しやすく
(必ず存在する単調増加列の代表例)
実際
\begin{array}{ccc} H_N &=& \displaystyle\inf_{N≤n}\Bigl\{ |f_n-F| \Bigr\} \end{array}
このように「 G_n の下限」をとると
\begin{array}{ccc} \displaystyle\inf_{N≤n}\Bigl\{ |f_n-F| \Bigr\} &≤& \displaystyle\inf_{N+1≤n}\Bigl\{ |f_n-F| \Bigr\} \\ \\ H_N &≤& H_{N+1} \end{array}
強引ではありますが
これは「単調増加列」になってくれますし
(ファトゥの補題に繋がり始める)
\begin{array}{ccc} \displaystyle\lim_{n\to\infty} f_n &=& f \end{array}
この「下限」は N で下から抑えているため
f_n は f に収束してくれます。
より緩い条件の下で
以上のことから
\begin{array}{ccc} \displaystyle\lim_{n\to\infty} f_n &=& f \end{array}
「単調増加に限らない収束」と
\begin{array}{ccc} 0 &≤& |f_n - F| \end{array}
この条件さえ満たしているのなら
\begin{array}{ccc} \displaystyle \inf_{N≤n}\Bigl\{ |f_n-F| \Bigr\} \end{array}
これに対して「単調収束定理」を使えるので
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int \inf_{N≤n}\Bigl\{ |f_n-F| \Bigr\} &=& \displaystyle \int \lim_{N\to\infty}\inf_{N≤n}\Bigl\{ |f_n-F| \Bigr\} \end{array}
この関係が得られます。
そして面倒ですが
「絶対値」を取り外せば
\begin{array}{ccc} |f_n-F| &=& \left\{ \begin{array}{ccc} f_n-F && 0≤f_n-F \\ \\ F-f_n && 0≤F-f_n \end{array} \right. \end{array}
これらはこうなりますから
(この記事では片側だけ示す)
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int \inf_{N≤n}\Bigl\{ f_n-F \Bigr\} &=& \displaystyle \int \lim_{N\to\infty}\inf_{N≤n}\Bigl\{ f_n-F \Bigr\} \end{array}
0≤f_n-F の場合だとこの式はこうなり
(逆側でも式の形自体はほぼ同じ)
\begin{array}{ccc} -ε_{\mathrm{inf}} +α &<& \displaystyle\inf_{N≤n}\{a_n\} &≤& a_N &<& α+ε_{\mathrm{sup}} \end{array}
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \lim_{N\to\infty}\inf_{N≤n}\Bigl\{ f_n-F \Bigr\} &=& \displaystyle \int f-F \end{array}
右側はこうなります。
(極限と下極限は一致する)
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int \inf_{N≤n}\Bigl\{ f_n-F \Bigr\} &\overset{?}{=}& \displaystyle \lim_{N_+\to\infty} \int f_{N_+}-F \end{array}
しかし左側はこうなるとは限らないので
(有限値 N_+ で下限をとるならこうなるが他は不明)
結果
\begin{array}{lcl} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int \inf_{N≤n}\Bigl\{ f_n \Bigr\}-F &=& \displaystyle \int f-F \\ \\ \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int \inf_{N≤n}\Bigl\{ f_n \Bigr\} &=& \displaystyle \int f \end{array}
この関係は得られますが
「交換可能」という結論を得ることはできません。
(左に関わる条件が何か必要だと分かる)
反例の存在
念のため確認しておくと
\begin{array}{lcl} \displaystyle\int_{[0,1]} n1_{[0,\frac{1}{n}]}(x) &=& \displaystyle n\int_{[0,1]} 1_{[0,\frac{1}{n}]}(x) \\ \\ &=& \displaystyle n μ^* \left( \left[ 0,\frac{1}{n} \right] \right) \\ \\ &=& \displaystyle n \left( \frac{1}{n} - 0 \right) \\ \\ &=&1 \end{array}
これは「逆ファトゥの補題」で触れた
\begin{array}{ccc} \displaystyle \liminf_{n\to\infty} n1_{[0,\frac{1}{n}]}(x) &=& \left\{ \begin{array}{ccl} \displaystyle\liminf_{n\to\infty} n && x=0 \\ \\ 0 && x \in (0,1] \end{array} \right. \end{array}
この「可測関数」を使うと
そのまま反例の存在を確認できます。
実際
\begin{array}{ccc} \displaystyle \sup \left\{ \int φ \right\}&=& \displaystyle \sup \left\{ \infty \cdot μ^*\Bigl( \{ 0 \} \Bigr) + 0 \cdot μ^*\Bigl( (0,1] \Bigr) \right\} \end{array}
この関数は
今回の条件に該当する「可測関数」ですが
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \liminf_{n\to\infty} f_{n} &\textcolor{pink}{=}& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n} \\ \\ 0 &≠& 1 \end{array}
計算してみると明らかに一致しません。
(振動を除くために単調増加のような縛りが必要)
ルベーグ可積分と優収束条件
「非負可測関数」に変形した後
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int \inf_{N≤n}\Bigl\{ f_n-F \Bigr\} &=& \displaystyle \int \lim_{N\to\infty}\inf_{N≤n}\Bigl\{ f_n-F \Bigr\} \end{array}
「単調増加にする」ために
「下限」をとって比較する。
ここまでは良い感じでしたが
「一般の可測関数」に対しては
\begin{array}{ccc} 0&≤& | f_n-F | \end{array}
「このような F の存在だけ」では
まだ欲しい結果に繋がりません。
ただ
ここまで来ると
\begin{array}{ccc} \displaystyle \liminf_{n\to\infty} n1_{[0,\frac{1}{n}]}(x) &=& \left\{ \begin{array}{ccl} \displaystyle\liminf_{n\to\infty} n && x=0 \\ \\ 0 && x \in (0,1] \end{array} \right. \end{array}
「反例を除けるかもしれない」操作として
\begin{array}{ccc} -F &≤& f_n &≤& F \end{array}
このような形を想定することが可能です。
というのも
「単調性」の形から
\begin{array}{rcr} |f_n| &≤& F \\ \\ \displaystyle \int |f_n| &≤& \displaystyle \int F \end{array}
この F を「可積分関数である」とすれば
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int |f_n| &≤& \displaystyle \int F &<& \infty \end{array}
f_n も「ルベーグ可積分」になるので
この制限が反例を除ける可能性があることから
\begin{array}{rcr} |f_n| &≤& F \\ \\ \displaystyle \int |f_n| &≤& \displaystyle \int F &<& \infty \end{array}
この条件は
「良い感じの条件」の候補になると予想できます。
(まだ反例を確実に除けるかどうかは曖昧)
優関数の存在と上限
反例を省くことが可能であるか
\begin{array}{ccc} |f_n| &≤& F \end{array}
これを考えるために必要な「関数 F 」ですが
これはそもそも「必ず存在する」ものなのか
考えてみると、この辺り曖昧ですよね。
というのも
\begin{array}{ccc} f_{n}(x) &=& n1_{[0,\frac{1}{n}]}(x) \end{array}
これは極限をとると
\begin{array}{ccc} \displaystyle \liminf_{n\to\infty} n1_{[0,\frac{1}{n}]}(x) &=& \left\{ \begin{array}{ccl} \displaystyle\liminf_{n\to\infty} n && x=0 \\ \\ 0 && x \in (0,1] \end{array} \right. \end{array}
「無限になる点を持つ関数」であるため
「優関数になって欲しい関数」の構成が少し複雑です。
「優関数」という関数は
「全ての n で f_n 以上である」ため
\begin{array}{ccc} \sup\{ f_n \} &≤& F_{\mathrm{min}} &≤& F \end{array}
基本的には
このような操作によって導くことが可能ですが
(全ての x で F(x) が f_n の上界である)
\begin{array}{ccc} F&=&\displaystyle\sup\{ f_n \} &&? \end{array}
これが必ず存在するかどうかは
この時点ではまだよく分かりません。
(変数 x と n の動きが曖昧)
反例の優関数っぽい上限関数
「 f_n を上から抑える関数 F を求める」
このためにやることは
\begin{array}{ccc} n1_{[0,\frac{1}{n}]}(x) &=& \left\{ \begin{array}{ccl} n &&\displaystyle x\in \left[ 0,\frac{1}{n} \right] \\ \\ 0 &&\displaystyle x\in \left(\frac{1}{n} , 1 \right] \end{array} \right. \end{array}
実はけっこう単純です。
というのも
結局は「各点で上限をとれば良い」だけなので
\begin{array}{ccl} 1 && 1\cdot 1_{[0,\frac{1}{1}]}(x) \\ \\ 2 && 2\cdot 1_{[0,\frac{1}{2}]}(x) + 0\cdot 1_{(\frac{1}{2},1]}(x) \\ \\ &\vdots \\ \\ n && n\cdot 1_{[0,\frac{1}{n}]}(x) + 0\cdot 1_{(\frac{1}{n},1]}(x) \\ \\ &\vdots \end{array}
この形さえわかるなら
(右側の範囲には上限がある)
\begin{array}{lcl} f_n &≤& 1\cdot 1_{(\frac{1}{2},1]}(x) + 2 \cdot 1_{(\frac{1}{3},\frac{1}{2}]}(x) + 3 \cdot 1_{(\frac{1}{4},\frac{1}{3}]}(x) + \cdots \\ \\ f_n &≤& \displaystyle \sum_{n=1}^{\infty} n\cdot 1_{(\frac{1}{n+1},\frac{1}{n}]}(x) \end{array}
こうですから
\begin{array}{ccc} \left\{ \begin{array}{lcl} \sup\{f_n\}=1 &&\displaystyle x\in \left(\frac{1}{1+1},\frac{1}{1}\right] \\ \\ \sup\{f_n\}=2 &&\displaystyle x\in \left(\frac{1}{2+1},\frac{1}{2}\right] \\ \\ &\vdots \\ \\ \sup\{f_n\}=n &&\displaystyle x\in \left(\frac{1}{n+1},\frac{1}{n}\right] \\ \\ &\vdots \end{array} \right. \end{array}
全ての n での上限値を考えれば
それは全ての f_n 以上の関数になるので
\begin{array}{ccc} F(x) &=& \displaystyle \sum_{n=1}^{\infty} n\cdot 1_{(\frac{1}{n+1},\frac{1}{n}]}(x) \end{array}
これは「全ての f_n を上から抑えられる」
そんな関数の1つになります。
(各点での上限なのでこれが最小になる)
優関数の候補と必要な条件
以上のことから
\begin{array}{ccc} f_n &≤& \displaystyle \sum_{n=1}^{\infty} n\cdot 1_{(\frac{1}{n+1},\frac{1}{n}]}(x) \end{array}
「 f_n を上から抑える関数の存在」は示されました。
(これが全ての n で成立する)
しかし
これが事実であるということは
\begin{array}{ccc} |f_n| &≤& F \end{array}
この条件のみでは
\begin{array}{ccc} f_n &=& n1_{[0,\frac{1}{n}]}(x) \end{array}
この反例は排除できないということなので
\begin{array}{ccc} F &<& \infty &&? \end{array}
反例を排除したいなら
この F には更なる縛りが必要だと分かります。
(優収束条件の発想を補強する事実の1つ)
ここで考えられるのが
「ルベーグ可積分」で
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int F &<& \infty \end{array}
ここまで条件を狭めれば
良い感じになりそうなのがなんとなく予想できます。
(こうすれば F<\infty より緩い条件で反例を弾ける)
反例を上から抑える関数の積分
実際に排除できるか確認するために
\begin{array}{rcr} f_n &≤& \displaystyle \sum_{n=1}^{\infty} n\cdot 1_{(\frac{1}{n+1},\frac{1}{n}]}(x) \\ \\ \displaystyle \int f_n &≤& \displaystyle \int \sum_{n=1}^{\infty} n\cdot 1_{(\frac{1}{n+1},\frac{1}{n}]}(x) \end{array}
この積分を考えてみると
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N} n\cdot 1_{(\frac{1}{n+1},\frac{1}{n}]}(x) &=& \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int \sum_{n=1}^{N} n\cdot 1_{(\frac{1}{n+1},\frac{1}{n}]}(x) \end{array}
これはすでに確認してるので
(非負単関数の項別積分の定理)
\begin{array}{ccl} \displaystyle \int \sum_{n=1}^{N} n\cdot 1_{(\frac{1}{n+1},\frac{1}{n}]}(x) &=& \displaystyle \sum_{n=1}^{N} n \cdot μ \left( \left(\frac{1}{n+1},\frac{1}{n} \right] \right) \\ \\ &=& \displaystyle \sum_{n=1}^{N} n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ \\ &=& \displaystyle \sum_{n=1}^{N} n \frac{(n+1)-n}{n(n+1)} \end{array}
そのまま「ルベーグ積分」の定義より
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int \sum_{n=1}^{N} n\cdot 1_{(\frac{1}{n+1},\frac{1}{n}]}(x) &=& \displaystyle \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n+1} \end{array}
こうなると言えます。
結果
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n+1} &=& \infty \end{array}
これは発散する数列なので
この F は「ルベーグ可積分」ではありません。
(つまりルベーグ可積分を条件とすると排除できる)
優収束定理の証明
↑ の条件で反例を弾けることは分かりました。
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n &=& \displaystyle \int f \end{array}
しかし肝心なのは
この結論を得られるかどうかです。
まだこの時点では
\begin{array}{rcr} |f_n| &≤& F \\ \\ \displaystyle \int |f_n| &≤& \displaystyle \int F &<& \infty \end{array}
この条件が十分であるかは分かっていません。
(反例が排除されたので近付いてはいる)
下極限から分かること
実際、ここから分かることは
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \inf_{N≤n} \{ f_n+F \} \end{array}
f_n がマイナスにはならないこの形と
(マイナスだと下限の形を維持できない)
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int \inf_{N≤n} \left\{ f_{n} \right\} &=& \displaystyle \int \lim_{N\to\infty} \inf_{N≤n} \left\{ f_{n} \right\} \end{array}
「単調性」を使って導ける
\begin{array}{rcr} \displaystyle \int \inf_{N≤n} \left\{ f_{n} \right\} &≤& \displaystyle \int f_{n} && N≤n \\ \\ \displaystyle \int \lim_{N\to\infty} \inf_{N≤n} \left\{ f_{n} \right\} &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n} && N≤n \\ \\ \displaystyle \int \liminf_{n\to\infty} f_{n} &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}
「ファトゥの補題」が保証する関係くらいで
\begin{array}{lcc} \displaystyle \int \liminf_{n\to\infty} f_{n} &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n} \\ \\ \displaystyle \int f &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}
この時点では
まだ他のことはよく分かりません。
下極限の関係と極限の定義
確認しておくと
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int f &=& \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}
着地はここです。
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int f &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}
そして分かっているのはこれで
他はまだよく分かっていません。
ただ
下極限の関係が分かっているということは
\begin{array}{ccc} \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n} &=& \displaystyle \int f &=& \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}
「極限の存在条件」を考えると
「上極限と下極限の定義」より
\begin{array}{ccc} \displaystyle \inf_{N≤n}\left\{\int f_{n}\right\} &≤ & \displaystyle \sup_{N≤n}\left\{\int f_{n}\right\} \\ \\ \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n}&≤& \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}
これは明らかですから
\begin{array}{ccc} \displaystyle \liminf_{n\to\infty}\int f_{n} &\textcolor{skyblue}{≥}& \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}
後はこうなることさえ確認できれば
\begin{array}{ccc} \displaystyle \liminf_{n\to\infty}\int f_{n} &\textcolor{pink}{=}& \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}
これが成立するため
\begin{array}{ccc} \displaystyle \inf_{N≤n}\left\{\int f_{n}\right\} &≤ & \displaystyle\int f_{N} &≤& \displaystyle \sup_{N≤n}\left\{\int f_{n}\right\} \end{array}
その結果として
「極限の存在」が保証されます。
(左右の極限値が等しくなることから)
つまり
\begin{array}{ccc} \displaystyle \liminf_{n\to\infty}\int f_{n} &\textcolor{skyblue}{≥}& {} && \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} \\ \\ \displaystyle \liminf_{n\to\infty}\int f_{n} &\textcolor{skyblue}{≥}& \displaystyle \int f &\textcolor{skyblue}{≥}& \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}
上記の関係さえ示すことができれば
その結果として
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int\lim_{n\to\infty} f_{n} &=& \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}
欲しい結論を得ることが可能です。
(これが大まかな指針になる)
下限と上限の入れ替えと下極限と上極限
「上限の斉次性」辺りで示されたように
\begin{array}{lcr} \inf\{ ca_n \} &=& c\sup\{a_n\} &&c<0 \\ \\ \inf\{ (-1)a_n \} &=& (-1)\sup\{a_n\} \end{array}
このような操作を行った場合
\begin{array}{ccc} \inf\{ -a_n \} &=& -\sup\{a_n\} \end{array}
「上限と下限」は変換されます。
(内側のマイナスを取り出すなら強制的にこうなる)
ということは
\begin{array}{ccc} 0&≤&F-f_n \end{array}
f_n がマイナスになる方の優収束条件を使って
(これが可能でないと上限の方の関係が得られない)
\begin{array}{lcl} \displaystyle \liminf_{n\to\infty} (-f_n) &=& \displaystyle \lim_{N\to\infty} \left( - \sup_{N≤n} \left\{ f_{n} \right\} \right) \\ \\ \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \left( -\int f_{n} \right) &=& \displaystyle \lim_{N\to\infty} \left( - \sup_{N≤n} \left\{\int f_{n} \right\} \right) \end{array}
この変形を使うと
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int \liminf_{n\to\infty} (-f_n) &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \left( -\int f_{n} \right) \\ \\ \displaystyle \int \lim_{N\to\infty} \left( - \sup_{N≤n} \left\{ f_{n} \right\} \right) &≤& \displaystyle \lim_{N\to\infty} \left( - \sup_{N≤n} \left\{\int f_{n} \right\} \right) \end{array}
これはこのように変形可能なので
( F が無いと左の極限と積分を交換できない)
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \lim_{N\to\infty} \left( - \sup_{N≤n} \left\{ f_{n} \right\} \right) &=& \displaystyle -\int \lim_{N\to\infty} \sup_{N≤n} \left\{ f_{n} \right\} \\ \\ \displaystyle \lim_{N\to\infty} \left( - \sup_{N≤n} \left\{\int f_{n} \right\} \right) &=& \displaystyle -\lim_{N\to\infty} \sup_{N≤n} \left\{\int f_{n} \right\} \end{array}
後はそれぞれの線型性を使って式を変形し
\begin{array}{rcr} \displaystyle -\int \lim_{N\to\infty} \sup_{N≤n} \left\{ f_{n} \right\} &≤& \displaystyle -\lim_{N\to\infty} \sup_{N≤n} \left\{\int f_{n} \right\} \\ \\ \displaystyle \int \lim_{N\to\infty} \sup_{N≤n} \left\{ f_{n} \right\} &\textcolor{pink}{≥}& \displaystyle \lim_{N\to\infty} \sup_{N≤n} \left\{\int f_{n} \right\} \end{array}
不等号の向きに気を付ければ
一連の変形によって
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int \limsup_{n\to\infty} f_{n} &\textcolor{pink}{≥}& \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} \\ \\ \displaystyle \int f &\textcolor{pink}{≥}& \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}
求めていたこの関係を得ることができます。
(これが逆ファトゥの補題の導出手順)
優収束条件の下では
以上のことをまとめると
\begin{array}{ccc} f_1 &≤& f_2 &≤& \cdots &≤& f_n &≤& \cdots \end{array}
「単調増加」を定義しなくても
\begin{array}{rcr} |f_n| &≤& F \\ \\ \displaystyle \int |f_n| &≤& \displaystyle \int F &<& \infty \end{array}
この「優収束条件」さえ満たされるなら
\begin{array}{rcr} \displaystyle \int \liminf_{n\to\infty} f_{n} &\textcolor{skyblue}{≤}& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n} \\ \\ \displaystyle \int \limsup_{n\to\infty} f_{n} &\textcolor{pink}{≥}& \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}
この関係が得られて
\begin{array}{ccc} \displaystyle \liminf_{n\to\infty}\int f_{n} &\textcolor{pink}{≤}& {} && \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} \\ \\ \displaystyle \liminf_{n\to\infty}\int f_{n} &\textcolor{skyblue}{≥}& \displaystyle \int f &\textcolor{skyblue}{≥}& \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}
「極限の存在条件」が満たされるので
その結果として
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty}\int f_{n} &\textcolor{pink}{=}& \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}
この関係を得ることができます。
( f_n が f に収束するなら)
\mathrm{Fatou}\text{-}\mathrm{Lebesgue} の定理
これは「優収束定理」を軸に
主に「逆Fatouの補題」から得られる結果で
\begin{array}{ccr} \displaystyle \int \liminf_{n\to\infty} f_{n} &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n} \\ \\ & {}& \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} &≤& \displaystyle \int \limsup_{n\to\infty} f_{n} \end{array}
「 f_n は可測関数である」と
\begin{array}{rcr} |f_n| &≤& F \\ \\ \displaystyle\int |f_n| &≤&\displaystyle \int F &<& \infty \end{array}
「優収束条件のみ」が前提となっている定理になります。
( f_n が f に収束するという前提を外してる)
優収束定理との関連
「優収束定理」は
\begin{array}{ccc} \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n} &≤& \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}
この定理の特別な場合で
( f_n が f に収束する)
具体的には
\begin{array}{ccc} \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n} &=& \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}
「極限の存在条件」を満たす時が
\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_{n} &=& \displaystyle \int \lim_{n\to\infty} f_{n} \end{array}
「優収束定理」になります。
(この定理では極限の存在を保証しない)
逆ファトゥの補題とファトゥの補題
この定理の核になるのは
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int \liminf_{n\to\infty} (-f_n) &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \left( -\int f_{n} \right) \\ \\ \displaystyle \int \lim_{N\to\infty} \left( - \sup_{N≤n} \left\{ f_{n} \right\} \right) &≤& \displaystyle \lim_{N\to\infty} \left( - \sup_{N≤n} \left\{\int f_{n} \right\} \right) \end{array}
先述した「逆ファトゥの補題」の成立条件で
\begin{array}{ccr} \displaystyle \int \liminf_{n\to\infty} f_{n} &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n} \\ \\ & {}& \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} &≤& \displaystyle \int \limsup_{n\to\infty} f_{n} \end{array}
これと「ファトゥの補題」が『同時に成立する』
これがこの定理の結論になります。
定理の証明
これはほとんどが先ほどの話の確認ですね。
\begin{array}{ccc} -F &≤& f_n &≤& F \end{array}
「優収束条件」の
「 f_n がプラスになる方」から導かれるのが
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \liminf_{n\to\infty} f_{n} &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}
この「ファトゥの補題」
そして「優収束条件」の
「 f_n がマイナスになる方」から導かれるのが
\begin{array}{lcl} \displaystyle \int \liminf_{n\to\infty} (-f_n) &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \left( -\int f_{n} \right) \\ \\ \displaystyle \int \lim_{N\to\infty} \left( - \sup_{N≤n} \left\{ f_{n} \right\} \right) &≤& \displaystyle \lim_{N\to\infty} \left( - \sup_{N≤n} \left\{\int f_{n} \right\} \right) \end{array}
「逆ファトゥの補題」です。
(優関数が上下から抑えてるからこうなる)
下極限と上極限の関係
以上のことから
\begin{array}{ccr} \displaystyle \int \liminf_{n\to\infty} f_{n} &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n} \\ \\ & {}& \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} &≤& \displaystyle \int \limsup_{n\to\infty} f_{n} \end{array}
「優収束条件」から
この関係を導くことができたわけですが
\begin{array}{ccc} \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n} & ≤ & \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}
実はこれもこの定理の結論の1つになります。
(上限下限の定義より明らかとしても良い)
これの証明は単純
\begin{array}{ccc} \displaystyle \liminf_{n\to\infty} a_n & ≤ & \displaystyle \limsup_{n\to\infty} a_n \end{array}
「下極限と上極限の定義」から
これはそのままの形で導くことができます。
(厳密には上限と下限の定義から導かれる)
優収束条件
ここまでの話から
だいたいのことは分かってると思いますが
\begin{array}{rcr} |f_n| &≤& F \\ \\ \displaystyle \int |f_n| &≤& \displaystyle \int F &<&\infty \end{array}
念のため
「優収束条件」の詳細について確認をしておきます。
(上記が根幹になるけど厳密には他の条件もある)
まず \{f_n\} ですが
\begin{array}{ccc} f_n & \mathrm{is} & \mathrm{Measurable \,\, Function} \end{array}
これは「可測関数」の列です。
この範囲から出ることはありません。
(つまりほぼ全ての関数のことを指す)
それと
「関数 F 」も「可測関数」で
\begin{array}{ccc} F & \mathrm{is} & \mathrm{Measurable \,\, Function} \end{array}
ここで出てくる「優関数」という概念は
\begin{array}{ccc} |f_n| &≤& F \end{array}
「可測関数」「 |f_n| 以上」「可積分」
\begin{array}{rcc} \displaystyle \int F &<& \displaystyle \infty \end{array}
この3つを満たすことになります。
(絶対値の上なので結果として非負可測関数になる)
まとめると
\begin{array}{ccc} \exists F & \left( \begin{array}{cl} & F \,\, \mathrm{is} \,\, \mathrm{Measurable \,\, Function} \\ \\ ∧ & |f_n| ≤ F \\ \\ ∧ & \displaystyle \int F < \infty \end{array} \right) \end{array}
「優収束条件」を論理式で表した時
その全体はこんな感じになります。
(見やすさのためにいろいろ省略)
優関数は全ての点で定義しなくて良い
「優収束定理」の段階では触れませんでしたが
実は ↑ の話で出てくる以下の条件は
\begin{array}{ccc} |f_n(x)| &≤& F(x) \end{array}
実際には「全ての x 」では定義されておらず
「ほとんど全ての x 」で定義されています。
(全ての x としても別に良い)
なんでそうするかって話なんですが
これは一言で言えば柔軟性を持たせるためで
\begin{array}{ccc} f_n&=& 1_Q(x) \end{array}
例えばこのような
「点だらけの関数」の「優関数」を考えてみると
\begin{array}{ccc} F(x) &=& 0 \end{array}
「ほとんど全て」とする場合
これも「優関数」だと認めることができます。
(全てとすると多くの点で 1_Q≤0 にならない)
すると
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int 1_Q &≤& \displaystyle \int 0 \end{array}
これの計算は比較的簡単になり
「可積分」の確認も容易になるので
(全てとすると優関数は自身である 1_Q のみになる)
これを可能とするために
\begin{array}{ccc} |f_n(x)| &≤& F(x) \end{array}
これは「全ての x 」ではなく
「ほとんど全ての x 」で定義されています。
無視して良い点と無視する利点
確認しておくと
まず「点の測度は 0 」です。
\begin{array}{ccc} μ \Bigl( \{x\} \Bigr) &=& 0 \end{array}
そして「面積」の定義を自然に解釈した時
面積の計算などで生じる可能性がある「不定形」は
\begin{array}{ccc} c & μ && c\times μ \\ \\ \infty & 0 &\to& 0 \\ \\ 0 & \infty &\to&0 \end{array}
0 以外では直感と異なる結果になることから
全て 0 とするのが自然な解釈になります。
(縦横のどちらかが 0 なら平面を構成できない)
ということは
「例外になる点」や「 0 になる点」を考える時
\begin{array}{ccc} \infty \times μ\Bigl( \{x\} \Bigr) &=& 0 \\ \\ 0 \times μ\Bigl( [0,\infty) \Bigr) &=& 0 \end{array}
その面積は
例えその片方が無限になるとしても 0 になるので
例えば
\begin{array}{ccc} \infty \times 1_Q \end{array}
このような関数を考えた時
(拡大実数値単関数の不定形も ↑ と同じ)
\begin{array}{ccc} \displaystyle\int_{[0,\infty)} \infty \times 1_Q &=& \infty \times μ(Q) + 0 \times μ\Bigl( [0,\infty)\setminus Q \Bigr) \end{array}
この積分の
\begin{array}{ccc} \infty \times μ(Q) &=& 0 \end{array}
「有理数」の部分はこうなるため
\begin{array}{ccc} Q & & [0,\infty)\setminus Q \\ \\ 0 && ? \end{array}
結果
この部分は無視しても問題が無いと言えます。
(これで 1_Q=1 になる点が全て取り除かれる)
ということは
\begin{array}{ccc} \infty \times 1_Q(x) &=& 0 && x\not\in Q \end{array}
後は「無理数」の部分だけ考えれば良いので
(拡大実数値単関数の定義によりこの不定形はこうなる)
\begin{array}{ccc} \infty \times 1_Q &≤& 0 \end{array}
0 を優関数として定めれば
これが「優収束条件」を満たすとすぐに分かります。
(ほとんど全てとすると ↑ の有理数部分の手順が不要)
優収束条件と論理式
以上を踏まえて
より厳密な話をすると
\begin{array}{ccc} |f_n| &≤& F \end{array}
この条件について
「ほとんど全ての x で成立する」としたいなら
\begin{array}{ccc} μ(?) &=& 0 \end{array}
例外的なものをまとめる操作として
\begin{array}{rcc} \displaystyle \left\{ x\in D \,\,\middle| \,\, F < |f_n| \right\} \\ \\ \displaystyle \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ x\in D \,\,\middle| \,\, F < |f_n| \right\} \end{array}
|f_n|≤F 以外を定めることにより
\begin{array}{ccc} μ \left( \displaystyle \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ x\in D \,\,\middle| \,\, |f_n| ≤ F \right\} \right) &≠& 0 \end{array}
間接的な形で
\begin{array}{ccc} μ \left( \displaystyle \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ x\in D \,\,\middle| \,\, F < |f_n| \right\} \right) &=& 0 \end{array}
このように定義する必要があります。
( 0 の点を全て無視することで他を定める感じ)
優関数の存在
「優収束条件」では
「優関数の存在」を勝手に仮定しますが
\begin{array}{rcr} |f_n| &≤& F \\ \\ \displaystyle \int |f_n| &≤& \displaystyle \int F &<&\infty \end{array}
この「優関数の存在」は
「全ての可測関数」で保証できるとは限りません。
(優関数と分かるのは可積分を確認した後)
「 n に関係の無い」
「可積分な非負値可測関数」であれば
\begin{array}{ccc} |f|&≤&f \end{array}
その関数をそのまま優関数とみなせますが
(確認が最も簡単で単純なパターン)
他の関数を考える場合
\begin{array}{ccc} a.e. \,\, x & \sup\{|f_n|\} \end{array}
「上限」を使えば行けそうだと予想はできても
実際にどうやるかは曖昧です。
単関数近似定理と優関数
ここで考えられるのが
\begin{array}{ccc} n &\to& \infty \\ \\ |f_n| &\to& f \end{array}
「単関数近似定理」の発想で
(任意の非負可測関数に近似する単関数列が存在する)
\begin{array}{ccc} F&=&\left\{ \begin{array}{lcl} \sup_{x,n}\{f_n(x)\} && x\in D_1 \\ \\ \sup_{x,n}\{f_n(x)\} && x\in D_2 \\ \\ &\vdots \\ \\ \sup_{x,n}\{f_n(x)\} && x\in D_N \end{array} \right. \end{array}
「 f_n の上限」から構成される単関数
(積分範囲の分割 D_N の中で最も大きい値)
\begin{array}{ccr} D &=& \displaystyle \bigcup_{n=1}^{N} D_n \\ \\ D &=& \displaystyle \lim_{N\to\infty}\bigcup_{n=1}^{N} D_n \end{array}
あるいは
\begin{array}{ccr} F^+(x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{N} \sup_{x,n}\{f_n(x)\} 1_{D_k}(x) \\ \\ F^+(x) &=& \displaystyle \lim_{N\to\infty} \sum_{k=1}^{N} \sup_{x,n}\{f_n(x)\} 1_{D_k}(x) \end{array}
その「極限」により定まる関数が
「優関数かもしれない関数」の構成法になります。
(これは単調減少になり全ての f_n の上界になる)
上限による定義そのまま
↑ では直感的に構成できるよう
「単関数」の形を利用しましたが
(全て表現可能かはこの時点では未確認)
\begin{array}{ccc} F(x) &=& \displaystyle \sup_{x,n}\{f_n(x)\} \end{array}
直接的かつ厳密な方法だと
「優関数かもしれない関数」の構成方法は
\begin{array}{ccc} \forall x \in D & \forall n & f_n(x)≤F(x) \end{array}
このような手順になります。
(これの具体例が ↑ の単関数の例)
ただしこの場合では
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_D \sup_{x,n}\{f_n(x)\} \end{array}
「積分」がどうなるかよく分からないことがあるので
手堅いのは「単関数」による構成方法になります。
(こちらの方法は確実に最小の上限関数になる)
優関数かもしれない関数と可積分
以上の話をまとめると
つまり「優関数の存在」を確認するためには
\begin{array}{ccc} F^+&=&\left\{ \begin{array}{lcl} \sup_{x,n}\{f_n(x)\} && x\in D_1 \\ \\ \sup_{x,n}\{f_n(x)\} && x\in D_2 \\ \\ &\vdots \\ \\ \sup_{x,n}\{f_n(x)\} && x\in D_N \end{array} \right. \end{array}
まず ↑ のような上限をとる関数 F^+ の構成が必要で
(これが無いとそもそも可積分を判定できない)
\begin{array}{ccc} \displaystyle \int F^+ &=& ? \end{array}
「可積分かどうか」の確認はその後になります。
(積分を計算できないと可積分か分からない)
