|| 量を扱うための形式的な表現
「量を表す時の表現方法」のこと
スポンサーリンク
目次
全称量化子「条件を満たすもの全てを表す」
存在量化子「条件を満たすものが存在することを表す」
量化子と数学の関係「なんで真偽が判定できるのか」
全称量化と存在量化の関係「全の否定と存在の否定」
真偽と量化子
そもそもの話
量化子(全て・存在するなど)は
\begin{array}{ccc} 全て~だ &\to& 真偽確定 &&? \end{array}
どうして数学で扱えるんでしょう。
\begin{array}{ccc} 自然言語 &\to& 全て &\to& \forall \\ \\ 自然言語 &\to& 存在 &\to& \exists \\ \\ 自然言語 &\to& ほとんど &\to& a.e. \end{array}
「全て」も「ほとんど」も「存在する」も
あくまで『人間の作った言語』で
\begin{array}{ccc} 数学 &\to& ∀ && × \end{array}
初めから『数学的に扱える』と
『分かった上でデザインされたもの』ではありません。
(あくまで由来は直感的な自然言語)
真偽と記号
「数学的に扱える」とは何か
「真偽が確定する」とは何か
\begin{array}{ccc} 真偽 &←& 言語の解釈 \end{array}
これを考えるためには
『意味』について考察する必要があるんですが
(これの詳細はモデル理論の記事で)
\begin{array}{ccc} AはBだよ &\to& 正しい? &\to& 真偽確定 \end{array}
この辺りを考察していくと
\begin{array}{ccc} 主張の意味 &\to& 個人の解釈 &\to& 真偽確定 \end{array}
最終的には
必ず「人間の直感」に行き着き
\begin{array}{ccc} 真偽が確定するとは \\ \\ ↓ \\ \\ 真偽を確定できる対象が存在する \\ \\ ↓ \\ \\ なんらかの主張はそれに該当する \end{array}
その『解釈を行う対象』として
「主張・言明」を意味する「文」が出てきて
\begin{array}{ccc} 主張を表現するもの \\ \\ ↓ \\ \\ 文で表現される \\ \\ ↓ \\ \\ 文は記号で表現される \end{array}
その「文」を表現する「記号」が出てきます。
(現代数学ではこの『記号』が主な考察対象になっている)
記号と量化子の役割
この「記号」という表現方法の『省略』
\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} 1&は自然数 \\ \\ 2&は自然数 \\ \\ 3 & は自然数 \\ \\ \vdots \end{array} &\to& 全てのnは自然数 \end{array}
実はこれが「量化子」と呼ばれる記号の役割で
\begin{array}{ccc} n は自然数 &\Longleftrightarrow& \mathrm{Natural}(n) \end{array}
単純な話
\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} \mathrm{Natural}(1) \\ \\ \mathrm{Natural}(2) \\ \\ \mathrm{Natural}(3) \\ \\ \vdots \end{array} &\to& \forall n \,\, \mathrm{Natural}(n) \end{array}
「正しい主張を全て集める」なら
\begin{array}{ccc} 正しい主張 &\to& 正しい主張の全て &&先 \\ \\ その中の1つが正しい &←& 全て正しい && 後 \end{array}
「全て正しい」という主張は当然正しくなります。
(この感覚を公理として扱うのが現代数学)
全称量化子 \mathrm{All,Any}
|| 全てそうだという主張の形式表現
「 \mathrm{All,Any} 」の頭文字を逆にした記号 \forall のこと
\begin{array}{llllllllllll} \displaystyle \mathrm{For \,\, any} &x&,P(x) &&\Longleftrightarrow&& \forall x &P(x) \\ \\ P(x)&\mathrm{for \,\, any} &x &&\Longleftrightarrow&& \forall x &P(x) \\ \\ \\ \mathrm{For \,\, all} &x&,P(x) &&\Longleftrightarrow&& \forall x &P(x) \\ \\ P(x)&\mathrm{for \,\, all} &x &&\Longleftrightarrow&& \forall x &P(x) \end{array}
意味はこんな感じで
\begin{array}{ccc}∀x &P(x) &&\Longleftrightarrow&&P(a_1)∧P(a_2)∧ \cdots \\ \\ &{} &&\Longleftrightarrow&& \displaystyle\bigwedge_{x∈X}P(x) \end{array}
厳密な中身はこんな感じです。
(超限帰納法を用いれば無限方向に拡張できる)
記号の意味
全称量化の定義は
\begin{array}{ccc} \mathrm{For \,\, all} &x&,P(x) \end{array}
こんな感じで
(英語だとほんとそのまま)
\begin{array}{ccc} 全てのxについて、xはPである \end{array}
これのこういう直訳をよく見るんですが
これ、なんかよく分かんなくないですか?
(「について」の部分がなんかぼやけてる気が)
分かるならいいんですけど
\begin{array}{ccc} 全てのxは&Pという条件を満たす \\ \\ xは全て&条件Pを満たす \\ \\ \\ 条件Pを満たす&(全てのxは) \\ \\ 条件Pは満たされる&(全てのxで) \end{array}
こんな感じの意味で覚えた方が
たぶん理解しやすいと思います。
(どれも意味に差はありません)
命題記号との関連
「全称量化」は ↓ を意味する
\begin{array}{c} \forall x &P(x) &&\Longleftrightarrow&& \displaystyle\bigwedge_{x∈X}P(x) \end{array}
これについては
\begin{array}{ccc} \forall x\in \{0,1,2\} \,\, P(x) &\Longleftrightarrow& P(0)∧P(1)∧P(2) \end{array}
有限範囲を考えるとすぐに分かると思います。
(命題記号である論理積の知識は必要)
存在量化子 \mathrm{Exists}
|| 存在するという主張の形式表現
「 \mathrm{Exist} 」の頭文字を逆にした記号 \exists のこと
\begin{array}{llllll} \mathrm{There \,\,exists} &x& \mathrm{such \,\, that} &P(x) &&\Longleftrightarrow&&\exists x &P(x) \end{array}
意味はこんな感じで
\begin{array}{c} \exists x & P(x) &&\Longleftrightarrow&& P(a_1)∨P(a_2)∨\cdots \\ \\ & &&\Longleftrightarrow&& \displaystyle\bigvee_{x∈X}P(x) \end{array}
こっちは全称量化と対になっています。
(あっちは論理積でこっちは論理和)
記号の意味
こっちも英語はそのままなんですが
\begin{array}{ccc} \mathrm{There \,\,exists} &x& \mathrm{such \,\, that} &P(x) \end{array}
よく見る直訳は
\begin{array}{ccc} P(x) となるような x が存在する \end{array}
ちょっと分かり難い感じがします。
(「 P(x) となるような」の部分がなんか曖昧な気が)
なのでよく見る方が分かり辛いなら
\begin{array}{ccc} 条件Pを満たす & xが存在する \\ \\ xが存在する & (条件Pを満たすような) \end{array}
こっちの方で覚えてはいかがでしょうか。
(こっちの方が直感的なはず)
命題記号との関連
これも有限範囲で考えると
\begin{array}{c} \exists x & P(x) &&\Longleftrightarrow&& \displaystyle\bigvee_{x∈X}P(x) \end{array}
「1つでも成立すればいい」ということから
\begin{array}{ccc} \exists x\in \{0,1,2\} \,\, P(x) &\Longleftrightarrow& P(0)∨P(1)∨P(2) \end{array}
意味的に同じことが直感的に分かると思います。
(全部の x で P(x) が偽なら両方とも偽)
量化記号の解釈
この「量化記号」についてですが
\begin{array}{ccc} \forall x \,\, P(x) &\to& 全てのxは条件Pを満たす \\ \\ \exists x \,\, P(x) &\to& 条件Pを満たすxが存在する \end{array}
これらは『こうだ!』と言っているので
\begin{array}{ccc} xは条件Pを満たす &\to& P(x)は真である \\ \\ 条件Pを満たすxが存在する &\to& P(x) は真である \end{array}
実はこのような『主張』を意味しています。
(構成としては「~は~である」と同型)
全と存在の関係
これもまた解釈になりますが
\begin{array}{ccc} 全てのxがP(x)を満たす &\Longrightarrow& P(x)を満たさないxが無い \\ \\ 全てのxがP(x)を満たさない &\Longleftarrow& P(x)を満たすxが存在しない \end{array}
この2つはこのような意味も持つことから
(下の P(x) を \lnot P(x) に入れ替えれば)
\begin{array}{lcl} \forall x \,\, P(x) &\Longleftrightarrow& \lnot \exists x \,\, \lnot P(x) \\ \\ \forall x \,\, \lnot P(x) &\Longleftrightarrow& \lnot \exists x \,\, P(x) \\ \\ \\ \exists x \,\, P(x) &\Longleftrightarrow& \lnot \forall x \,\, \lnot P(x) \\ \\ \exists x \,\, \lnot P(x) &\Longleftrightarrow& \lnot \forall x \,\, P(x) \end{array}
こういった関係であると言えるので
これもまた公理として定められています。
集合と量化子
「量化子」の中でも特に「全称量化」は
「内包性公理」に深く関わっていて
\begin{array}{ccc} \forall x\in \{x\in D \mid P(x) \} &\Longleftrightarrow& \forall x \,\, x\in D⇒φ(x) \end{array}
このような集合を厳密に考える時
「全称量化」が必要になります。
ややこしい表現
この感覚から
\begin{array}{lcc} \{ x\in D \mid P(x) \} \\ \\ \{ x\in D \mid \forall x \,\, P(x) \} \end{array}
これらの意味があやふやになりますが
(内包性公理は条件 P(x) を満たす全ての x をとってくる)
\begin{array}{lcl} x\in D⇒P(x) &\Longleftrightarrow& D内のxの1つが条件P(x)を満たす \\ \\ x\in D⇒\forall x \,\, P(x) &\Longleftrightarrow& D内の全てのxが条件P(x)を満たす \end{array}
実は定義的にはこんな風になるので
\begin{array}{ccc} \{ x\in D \mid \forall x \,\, P(x) \} \\ \\ ↓ \\ \\ DにPを満たさないxが1つでもあれば空集合 \end{array}
ちゃんと分解すると全然違うものだと分かります。
(内包性を使う集合表現で量化は条件にあまり来ない)
全と存在の視覚イメージ
「集合」を使うと
\begin{array}{ccc} \forall x\in \{x\in D \mid P(x) \} &\Longleftrightarrow& \forall x \,\, x\in D⇒φ(x) \\ \\ \exists x\in \{x\in D \mid P(x) \} &\Longleftrightarrow& \exists x \,\, x\in D⇒φ(x) \end{array}
「 x をとる範囲 D 」を使えば
実はこれらのイメージはしやすくて
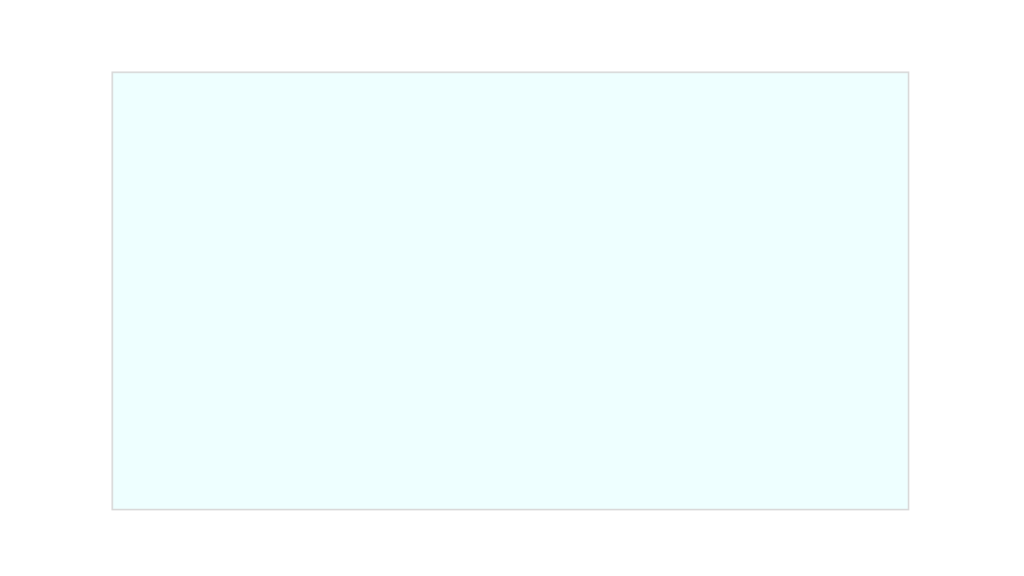
\begin{array}{ccc} \forall x \,\, x\in D⇒φ(x) \end{array}
「全称量化」と「存在量化」は

\begin{array}{ccc} \exists x \,\, x\in D⇒φ(x) \end{array}
それぞれこんな感じになっています。
(満ちてるのが全称で点在しているのが存在)

“量化子 Quantifier” への1件の返信
コメントは受け付けていません。