|| 数学の基礎になるもの
論理学の数学バージョンです
スポンサーリンク
論理学 Logic
|| 真理とは何かを調べた成果
字面から推測できる通り
\begin{array}{ccc} 論理学 &\overset{色々}{\longrightarrow}& 数理論理学 \end{array}
これが「数理論理学」の元になったもので
「数理論理学」はここから発想されたものになります。
数理論理学 Mathmatical Logic
これはいろんな基礎から形作られているもので
\begin{array}{lcll} 言語 && 一階述語論理 & 主張の形が由来 \\ \\ 基礎 && 集合論 & 定義のやり方が由来 \\ \\ 意味 && モデル理論 & 意味論が由来 \\ \\ 推論 && 証明論 & 論証が由来 \\ \\ 確認 && 再帰理論 &計算可能の定義が由来 \end{array}
古い時代から続くいろんな知恵を結集した
\begin{array}{lcl} 哲学的論理学 && 原初の論理という概念 \\ \\ 近代的論理学 && ここでいろいろあった \\ \\ 数理論理学 && いろいろ整備された結果 \end{array}
ある種の到達点になります。
(概形は示せるが詳細がけっこう深い)
近代論理学 Symbolic Logic
別名「記号論理学」と呼ばれるこれが
「近現代の論理学」に当たるもので
\begin{array}{lcl} 最初期 && 集合論の発想 \\ \\ 記号化 && 証明の形式化 \\ \\ 分化 && 推論と意味と言語 \\ \\ 計算可能 && 再帰理論の発想 \end{array}
ここでは本当にいろんなことが起きています。
(起き過ぎてて正確な整理が難しい)
集合論
「数理論理学」の核となるこれは
\begin{array}{lcl} 概念の定義 && 外延と内包 \\ \\ 概念の視覚化 && 枠とその中身 \end{array}
「定義のやり方」から見えてくる
(定義方法の発想はポールロワイヤル論理学時点)
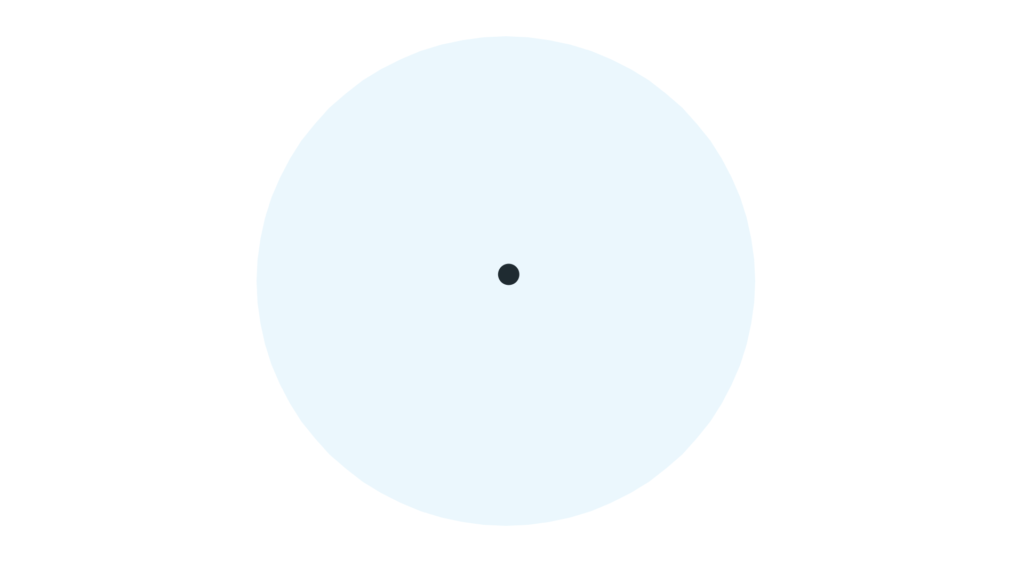
\begin{array}{ccc} 人間,猿,魚,鳥,... &←& 動物 \end{array}
「情報の視覚イメージ」が由来になっていて
(ここから枠とその中身という発想が得られる)
\begin{array}{ccc} 情報は全て「枠と中身」の形? \\ \\ ↓ \\ \\ 具体的に情報を記述 \\ \\ ↓ \\ \\ 例外が見つからない \end{array}
あらゆる概念をサンプルとした帰納的推測から
「集合論の原型となる発想」は得られています。
(これが概念の記号化という発想に繋がる)
証明の記号化
概念は「集合という形で記号化できる」
この発想から生まれ発展していったのが
\begin{array}{lcl} モデル理論 && 全体像の区分け \\ \\ 証明論 && ちゃんとした推論の規則 \\ \\ 一階述語論理 && 言語の具体的な中身 \\ \\ 再帰理論 && 計算できるとは \end{array}
こういった分野で
(証明ってそもそも何?という意味の考察からスタート)
\begin{array}{lcl} モデル理論 &\to& 数学全体への考察 \\ \\ 証明論 &\to& 推論規則の具体化に伴う複雑化 \\ \\ 一階述語論理 &\to& 表現力と証明可能範囲の両立 \\ \\ 再帰理論 &\to& 計算可能性から複雑性へ \end{array}
これらは発展が進む過程で独立し
それぞれの中身は深化していきました。
(発展は相互作用的で複雑に絡み合っている)
補足しておくと
\begin{array}{lcl} モデル理論の発想 && 証明とは何か? \\ \\ 述語論理の誕生 && 命題の中身を具体化して整理 \\ \\ 証明論の誕生 && ちゃんとした証明の整理 \\ \\ モデル理論の誕生 && これまでの全体を整理 \\ \\ 一階述語論理の誕生 && モデル理論の突き詰めにより \end{array}
概念として固定化されるまでの流れはこんな感じです。
(概念の意味を考察するという見方なら常にモデル理論内)
モデル理論
これは「意味」について考察された成果で
\begin{array}{ccc} 言語 &\to& 言語の解釈 &\to& 真偽の判定 \end{array}
「数学の全体像」を整備する役割を担っています。
(ある程度の整備が進んだ後にモデル理論として確立)
\begin{array}{lcl} 言語 && 一階述語論理 \\ \\ 言語の解釈 && モデル理論の役割 \\ \\ 真偽の判定 && 証明論 \end{array}
「証明の記号化」からの分化を綺麗に定義できるのは
「モデル理論」がその区分けをしてくれているからです。
証明論
「ちゃんと証明できる」とは何か
これを考察した成果がこれで
\begin{array}{ccc} ちゃんとした証明って? \\ \\ ↓ \\ \\ 妥当な推論規則の整備 \end{array}
「ちゃんとした証明である」という概念の
「具体的な中身」をこれは提供してくれます。
一階述語論理
「主張」を分解して数理的に整備した「命題論理」
「命題論理」の具体的な中身を整備した「述語論理」
\begin{array}{lcl} 主張の段階 && 真偽が分かるやつの形 \\ \\ 命題論理の段階 && 真か偽か分かるという要請のみ \\ \\ 述語論理の段階 && 命題の中身を具体化 \end{array}
それを更に整備して
\begin{array}{lcl} 最初期 && 量化の範囲に言及無し \\ \\ 問題発生 && 量化の範囲は無制限じゃダメ \\ \\ ドメインの制限 && 集合論の矛盾を解消 \\ \\ 自己参照の排除 && 個体変数のみ量化可能 \end{array}
「証明ができる」領域に落とし込んだのがこれで
これにより「証明の最小単位」が明確化されました。
(これが証明に使える理由を提供するのがモデル理論)
再帰理論
これは「計算できる」を突き詰めた成果で
\begin{array}{ccc} 計算できるとは? &\to& 原子帰納関数 \end{array}
「計算可能関数」の定義から
\begin{array}{ccc} 複雑過ぎて計算に時間が掛かり過ぎる \\ \\ ↓ \\ \\ 実質的に計算不可能では? \end{array}
「計算の複雑さ」にまで現代では発展しています。
(元は有限範囲での証明が可能かどうかから来ている)
