|| 全体を意味する実体のこと
物理学でも数学でも「全体」を意味します
スポンサーリンク
目次
数学的宇宙「欲しい性質を満たす具体的な実体(モデル)」
議論領域「宇宙そのものあるいはそれを切り取った一部」
フォン・ノイマン宇宙「整礎的集合から得られたでかい領域」
構成可能宇宙「人間に扱える有限モデルに行き着く領域」
宇宙型「型という数学的対象自体の型」
グロタンディーク宇宙「集合の圏の安全領域」
数学的宇宙 Mathematics Universe
|| 欲しい性質を持ってる具体的な実体
代表的な「モデル」のことで
\begin{array}{ccc} \mathrm{Mathematics} &\to&\mathrm{Model} &\to& \mathrm{Universe} \end{array}
これは「数学」自体に対するモデルになります。
(数学が持っていて欲しい性質を持つ具体的な実体)
宇宙という概念の整理
「宇宙」というと
\begin{array}{ccc} 宇 &\Longleftrightarrow & 天地四方 &\Longleftrightarrow& 上下前後左右 \\ \\ 宙 &\Longleftrightarrow& 往古来今 &\Longleftrightarrow& 過去現在未来 \end{array}
このような「実体」を意味する概念ですが
(感覚的には認識できる全体を意味する)
その「実体」の範囲を
「認識可能な範囲」という形で解釈する場合
(認識も実存するとすれば物理的実体を拡大解釈できる)
\begin{array}{ccc} \mathrm{Universe} &&→&& 全体的な広がり \end{array}
その中身は
\begin{array}{ccc} \mathrm{Ordered}+\lnot \mathrm{Ordered} &←& \mathrm{Universe} \end{array}
「秩序ある宇宙 \mathrm{Cosmos} 」と
「無秩序な宇宙 \mathrm{Chaos} 」に分けられるので
この感覚から
\begin{array}{ccc} \mathrm{Cosmos} &&\to && \mathrm{Universe}_{\mathrm{Mathematics} } \end{array}
「数学的宇宙」という概念は
「秩序ある宇宙」の1つとして定義されます。
秩序ある宇宙でも無秩序を内包する
しかし「秩序ある宇宙」であっても
\begin{array}{ccc} R &=& \{ x \mid -\infty < x < \infty \} \end{array}
例えば「実数 \mathrm{Real}\mathrm{Number} 」を考えた時
\begin{array}{ccc} 有限個の実数の性質 &&\to&& 実数全体 \end{array}
この「秩序により得られた集まり」の中身には
「秩序がある」とは言い難いです。
というのも
\begin{array}{ccc} 0.6129368198376910871 \cdots \end{array}
「超越数」なんかを考えれば
( 0 から 9 をランダムに無限回並べてできる数とか)
\begin{array}{ccc} 自然数の要素数 &<& 無理数の要素数 \end{array}
その「要素数(中にある点の数)」は
「秩序のある数(自然数など)」と比べて遥かに多いですし。
(これの詳細はカントールの定理を参照してください)
議論領域 Domain of Discourse
|| その時に変数が取り得る範囲
「宇宙(数学的宇宙)の使用する一部」のこと
\begin{array}{lcc} 集合論的宇宙 &&\to&& 部分集合(ZF) & 部分クラス(NBG) \\ \\ 圏論的宇宙 &&\to&& 部分圏 & 部分対象 \\ \\ 型理論的宇宙 &&\to&& 部分型 & 型の部分型 \end{array}
具体的にはこんな感じで
概念としては非常に便利に扱われます。
(全体の中の一部あるいは全体そのものを指す)
集合論的宇宙 Set Theory
|| 集合で数学を全て説明できるという思想
これは「順序数」を元にした考え方で
\begin{array}{ccc} \mathrm{Ordinal} &&\to&& \mathrm{Universe} \end{array}
「整列性」がその根拠になっています。
(全て整列させられるという事実から発想される)
集合論的宇宙の役割
この「集合論的宇宙」というのは
主に「メタレベルの何か」を考えるために必要なもので
\begin{array}{ccc} ZFC &?& ZFC+GCH \end{array}
有名なところだと
「選択公理」「実数の濃度」の話なんかで出てきます。
(これら公理の独立性なんかを検証できる)
フォン・ノイマン宇宙 Von Neumann
|| 確実に大きくなる操作と順序数
これは「カントールの定理」から発想されたもので
\begin{array}{ccc} \mathrm{Cardinal}(S) &<& \mathrm{Cardinal}(2^S) \end{array}
『確実に大きくなる操作(冪集合)』を表現してみた結果
(絶対に要素数が増えるという意味で大きくなる)
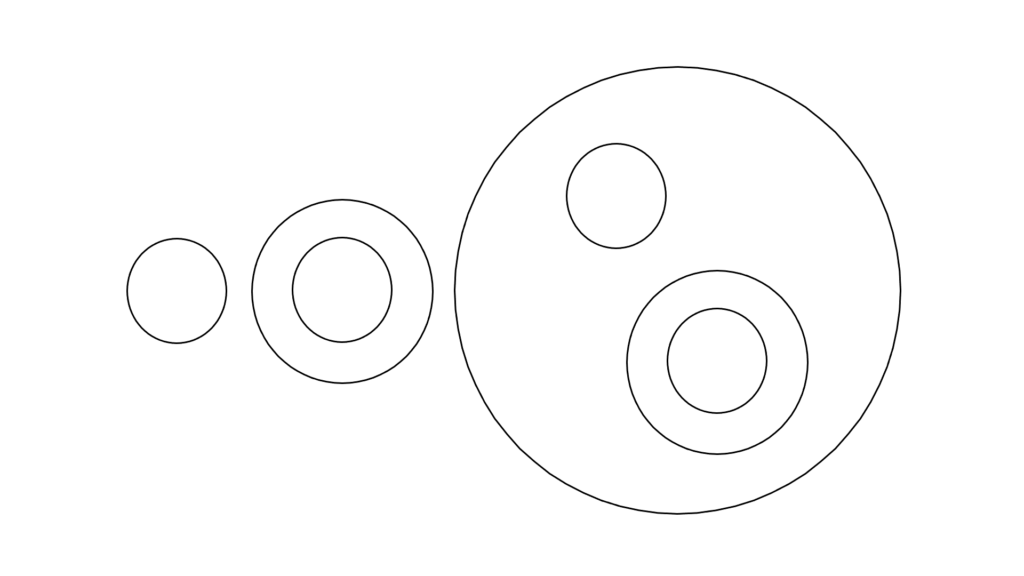
\begin{array}{lcc} V_0&=&∅ \\ \\ V_{α+1}&=&2^{V_α} \\ \\ V_λ&=&\displaystyle\bigcup_{β<λ}V_β \end{array}
このような形になっています。
(この宇宙の定義は超限帰納法の形そのまま)
構成可能宇宙 Constructible
|| 人間が扱えるものだけ集めてみた
『人間が扱える範囲』の「ノイマン宇宙」
\begin{array}{lcc} \displaystyle L_0 &=& ∅ \\ \\ L_{α+1} &=& \mathrm{Define}(L_α) \\ \\ L_λ &=& \displaystyle \bigcup_{β\in λ} L_β \end{array}
「有限(人間が扱える)の範囲」で
「 L_α を定義することが可能」である
(「全」は量化により \forall x 有限範囲で定義可能)
\begin{array}{ccc} \mathrm{Define}(L_α) &\Longleftrightarrow& L_αの範囲で定義可能 \end{array}
これを保証したのが「構成可能宇宙」で
\begin{array}{ccc} 結果 &\to& \begin{array}{lcc} 規則性無し \\ 入力と出力のペアが無限通り \\ 各ペアに個別の定義が必要 \end{array} \end{array}
「無限個の定義が必要である」場合なんかを
この集合論的宇宙は排除しています。
定義不能集合の存在
なんでこれが必要かは
\begin{array}{ccc} 数学的宇宙 &\left\{ \begin{array}{llc} フォンノイマン宇宙 & \left\{ \begin{array}{lcc} 定義可能集合 \\ \\ 定義不可能集合 \end{array} \right. \\ \\ ZF外宇宙 \end{array} \right. \end{array}
「フォンノイマン宇宙」では存在する
「存在することは分かる集合」を考えると分かり易いです。
( ZF は存在するかどうかしか問わない)
というのも
\begin{array}{ccc} R &\to& 2^R \end{array}
例えば実数の冪集合 2^R をとったりしてみると
(実数の部分集合を全て集めた集合)
\begin{array}{ccc} 区間の集まり &\subset& 2^R \end{array}
「存在することは分かる集合」の中には
\begin{array}{ccc} 無限桁のランダムな実数a,bの区間の存在 \\ \\ ↓ \\ \\ 実数は無限に存在するため区間(a,b)は無限に存在する \\ \\ ↓ \\ \\ その無限個存在するものを集めた集合が存在する \\ \\ ↓ \\ \\ その2^Rの部分集合には無限個の定義が必要になる \end{array}
このような
「中身を定義できない部分集合」が出現し得えます。
(具体的な中身は定義できないが存在はする)
つまり
「フォンノイマン宇宙」のままでは
\begin{array}{ccc} フォンノイマン宇宙で考える \\ \\ ↓ \\ \\ 中身が分からない集合が存在する \end{array}
「定義不可能集合」が存在してしまい
それを無視できないため
\begin{array}{ccc} 中身を定義できない集合は影響を調べられない \\ \\ ↓ \\ \\ 無視して良いかすら分からない \end{array}
それらがどのような影響を及ぼすのか
\begin{array}{ccc} A∪B && \to && 中身がどうなるのか分からない \\ \\ \forall x &&\to&& xに定義不可能集合が入り得る \end{array}
それすらも説明ができない状態になってるんです。
(故になんとかしてこれらを排除する必要があった)
定義可能の意味
それ故に考案されたのが
「構成可能宇宙」という集合論的宇宙で
\begin{array}{ccc} 定義可能 &\Longleftrightarrow& 集合の中身を全て記述可能 \end{array}
ここで使われる「定義可能」の意味は
抽象的にはこのようになっています。
\begin{array}{ccc} \mathrm{Define}(L_α) &\Longleftrightarrow& L_αの冪集合を定義可能範囲に \end{array}
この記号の定義もこれに準拠していて
\begin{array}{ccc} 2^{L_α} &\to& \mathrm{Define}(L_α) \subset 2^{L_α} \end{array}
「冪集合操作」を改造したものになっています。
(冪集合の要素に制限を加えたのが \mathrm{Define} )
定義可能範囲に制限された冪集合操作
より具体的かつ厳密には
「 L_{α+1} の要素として選ばれる」ことになる
\begin{array}{ccc} L_{α+1} &=& \{ S \subset L_α \mid Sは有限言語で定義可能 \} \end{array}
「 L_α の部分集合 S 」には
このような制限が加えられていて
\begin{array}{ccl} L_{α+1} &=& \{ S \subset L_α \mid Sは有限個の論理式で定義可能 \} \end{array}
「有限言語」の厳密な定義から
\begin{array}{ccc} x\in S &\Longleftrightarrow& x\in L_α∧φ(x,p_1,p_2,...,p_n) \end{array}
この部分集合 S はこのように定義されています。
(有限個のパラメーターを持つ論理式で要素を表現できる)
有限個のパラメーターと論理式
↑ の φ と p_n についてですが
\begin{array}{ccc} φ(x,p_1,p_2,...,p_n) \end{array}
これの意味はそれぞれ ↓ のようになっていて
\begin{array}{lcc} φ &\Longleftrightarrow& 有限個の記号から作られる整論理式 \\ \\ x &\Longleftrightarrow& L_αの要素から指定できる自由変数 \\ \\ p_n &\Longleftrightarrow& 条件として使うL_αの要素 \end{array}
抽象的な状態だと
見た目、かなりややこしく感じますが
\begin{array}{ccc} φ(x,p_1,p_2) &\Longleftrightarrow& x=p_1∨x=p_2 \end{array}
具体例を考えると
そんなに難しくないことが分かると思います。
(これの p_n を増やせば任意の有限集合を作れる)
補足しておくと
\begin{array}{ccc} φ(x) &\Longleftrightarrow& x=x \end{array}
L_α 自体をとりたい場合は
このような恒真命題を使えば実現できます。
(こういう論理式で指定できる S が L_{α+1} の要素)
厳密には人間が扱える範囲ではない
最後、補足しておくと
\begin{array}{ccc} φ &\Longleftrightarrow& 有限個の記号で記述可能な整論理式 \end{array}
実はこのような
\begin{array}{ccc} \exists φ & \exists p_1,p_2,p_3,...,p_n \in L_α \end{array}
『有限範囲』のものであっても
\begin{array}{ccc} \mathrm{Define}(L_α) &=&\displaystyle \left\{ S \subset L_α \,\, \Bigl| \,\, S=\{ x\in L_α \mid φ(x,p_1,...,p_n) \} \right\} \end{array}
「構成可能宇宙」は
まだ「人間に扱える大きさ」にはなっていません。
というのも
\begin{array}{lcl} φ(x,p_1,...,p_{100}) &=& x=p_1∨\cdots∨x=p_{100} &&△ \\ \\ φ(x,p_1,...,p_{10^{12}}) &=& x=p_1∨\cdots∨x=p_{10^{12}} && × \end{array}
例えばこれらは「有限範囲で記述可能」ですが
「人間」は『1兆個の論理式を確認できません』
\begin{array}{ccc} \mathrm{Symbol}(φ) &\Longleftrightarrow& φで使用した記号の数 \end{array}
まあ要はそういう話で
\begin{array}{ccc} \mathrm{Symbol}(φ) &≤& 記憶可能量 &≤& 読み込み速度×寿命 \end{array}
「記憶可能量」「読み込み速度」「寿命」
人間にはこういった限界があることから
\begin{array}{ccc} 人間が理解可能な宇宙 &\subset& 構成可能宇宙 \end{array}
「構成可能宇宙」内の全てを理解することはできません。
(記述可能性という観点で証明不可能なものが存在し得る)
型理論的宇宙 Type Theory
|| 数学は全て型で説明できるはずだという思想
これは「型を生成する型」という形で定義されるもので
\begin{array}{ccc} 型&:&型理論的宇宙 \end{array}
「型(何かを生成するルールの集まり)」を
「項(型の具体的な中身)」として持っています。
(ルールの集まりそのものを生成する型がこの宇宙)
正確な表記は
\begin{array}{ccc} 0,1,...,\mathrm{Natural} , \mathrm{Vector}(3),... &:& \mathrm{Type}_0 \end{array}
「最も下位の型の型 \mathrm{Type}_0 」を考えると
(この型の型が最下位の型理論的宇宙)
\begin{array}{lcl} \mathrm{Type}_0 &:& \mathrm{Type}_1 \\ \\ \mathrm{Type}_1 &:& \mathrm{Type}_2 \\ \\ &\vdots \end{array}
こんな感じになります。
(果てなく無限に上位の型宇宙が存在する)
無限に存在する理由
これは「型の型」を考えた時の
\begin{array}{ccc} 項 &:& 型 \\ \\ \mathrm{Type} &:& \mathrm{Type} \end{array}
「自己参照」を回避した結果で
(Girardのパラドックスが生じる)
\begin{array}{ccc} 自己参照すると矛盾 &\to& より上位のルールがある \end{array}
かなり筋肉に寄った解決方法になります。
(無限に上位の型が存在すれば解決)
圏論的宇宙 Category Theory
|| 圏論で考察の対象になる大きなもの
これは「サイズ管理の対象」になる概念で
\begin{array}{ccc} そのまま扱うと矛盾するかも? \\ \\ ↓ \\ \\ 安全な領域が必要になる \end{array}
「安全に圏論を議論する」ための材料になります。
(圏の1つに定義される全体を表す概念)
グロタンディーク宇宙 Grothendieck
|| 圏論で扱える集合の全体像
これは「集合の圏」を扱うために必要なもので
\begin{array}{ccc} 集合をそのまま扱うと矛盾する \\ \\ ↓ \\ \\ 矛盾しない集合の広い範囲が必要 \end{array}
「自然数 N の存在」を前提として
(集合論上で存在を確定させられる)
\begin{array}{rcr} S \in U &\Longrightarrow& S は集合 && 集合の定義 \\ \\ S \in U &\Longrightarrow& S\subset U && 集合の要素も全部持ってる \\ \\ \\ a,b \in U &\Longrightarrow& \{a,b\} \in U && 具体集合生成公理 \\ \\ S \in U &\Longrightarrow& 2^S \in U && 冪集合公理 \\ \\ S_i \in U &\Longrightarrow& \displaystyle \bigcup_{i\in I} S_i \in U && 和集合公理 \\ \\ \\ && N\in U && 自然数の存在 \end{array}
このような U であるという形で定義されています。
(和集合の左は正確には I\in U ∧ \forall i\in I \,\, S_i \in U )
