|| いろいろな情報を視覚化する
「見えない情報」を『視覚化する方法』
スポンサーリンク
目次
情報「人間が認識可能な記号」
定義可能「情報の中身を認識可能」
限定全「全体は無制限じゃなく範囲内」
視覚化可能情報「集合の発想に基づく」
抽象「要素を持つ集合のこと」
具体「集合にとっての要素のこと」
基礎操作「情報の基礎的な扱い」
類似「共通する要素を持つ」
分類「情報の生成と狭義の意味」
2値分類「それとそれ以外(真偽の原型)」
3値分類「完全に分割できない(直感的な2値分類)」
導入
まず初めに
この概念が必要だと感じたきっかけについて
\begin{array}{lcl} 厳密化と専門化による難解さ &\to& 簡単に \\ \\ 必要になる勉強量の多さ &\to& 使える操作だけ紹介 \\ \\ 社会問題化したイコール &\to& 正しい情報の周知 \end{array}
ざっと確認しておくと
その理由はこんな感じです。
(この記事では可能な限り簡単な言葉を使います)
イコールの誤用とは
特に周知したいのが
\begin{array}{ccc} \mathrm{be}(A,B) &\Longleftrightarrow& AはBである \\ \\ \mathrm{be}(A,B) &\Longleftrightarrow& A \,\, \mathrm{is} \,\, B \end{array}
これについてで
\begin{array}{ccc} \mathrm{be}(A,B) & \left\{ \begin{array}{lcl} A\in B && AはBの構成要素 \\ \\ \displaystyle \frac{Aの要素数}{Bの要素数}≒1 && AとBは似てる \\ \\ A=B && AとBは同じ \end{array} \right. \end{array}
これの中でも
\begin{array}{lcl} A\in B && ほとんどの場合 \\ \\ \displaystyle \frac{Aの要素数}{Bの要素数}≒1 && 実際の同じ \\ \\ A=B && 机上の同じ \end{array}
「同じ」を意味することはほぼ無い
(数値処理などの統計処理でしか成立しない)
\begin{array}{ccc} A=Bではない &\to& A=Bを根拠とする主張 && × \end{array}
故にこれを論理の基盤とするものは
ほとんどのパターンで間違っている
( A と同じものは A しかない)
\begin{array}{lcl} =の誤用 &\to& 平等は正義 && × \\ \\ 真なる人の上下基準 &\to& 形而上のもの && 〇 \\ \\ \\ =の誤用 &\to& 差別は悪 && × \\ \\ 差で分ける &\to& 善も悪もある && 〇 \end{array}
この事実を周知したいと考えています。
(平等は正義よりも実は悪寄りの概念)
間違えるという不幸を減らす
↑ の社会的な問題も含め
「あらゆる個人的な問題」も解決したいというのが
\begin{array}{ccc} 数理の周知 &\to& 問題解決能力の向上 \end{array}
この実用的数学の存在意義で
\begin{array}{lcl} 記憶の考察 &\to& 記憶力の向上 \\ \\ 思考の考察 &\to& 思考能力の向上 \\ \\ 正しさの考察 &\to& 誤解が減る \\ \\ 因果の考察 &\to& 因果関係の整理能力向上 \end{array}
基本的にはこういう部分で恩恵を実感できます。
(効果の弱い努力や人生の浪費が減る)
実用的数学基礎の前提
整理しておくと
\begin{array}{lclcl} 確定 && 厳密さ &\to& 範囲を数学へ \\ \\ 優先 && 分かり易さ &\to& 直感に寄せる \\ \\ 目的 && 用語を翻訳 &\to& 一般的な言葉を優先 \end{array}
基本方針はこんな感じで
\begin{array}{ccc} 材料 && クラス&→&情報 \end{array}
この「前提」の段階では
「全体を表現できる材料」について整備します。
(全体像はNBG集合論を参考にする)
変数の範囲
これはちょっと専門的になっちゃいますが
\begin{array}{ccc} 変数の中身 &\to& 構成可能宇宙に限定 \end{array}
矛盾を回避するためにも
とれる範囲は「構成可能宇宙」に限定します。
(人間に扱える範囲くらいに思ってればOK)
表現の拡張
これは「定義」の形をそのまま流用
\begin{array}{ccc} 0 &=& \{\} \\ \\ 考察対象 &=& \{ x \mid xは~ \} \end{array}
ここでの「考察したい対象」は
「集合の名前(ただの記号)」として扱います。
(考察対象の具体的な形は名前+中身とする)
情報 Information
|| なにかを表現したもの
「実用的数学における最小単位」のこと
\begin{array}{ccc} 形を与える &\to& 情報 \\ \\ \mathrm{in}\text{-}\mathrm{formare} &\to& \mathrm{Information} \end{array}
現代において
「広義の意味では」「概念」と差はありませんが
(この記事における情報の意味も広義の意味)
\begin{array}{ccc} 情報 && 客観的 & 記号的 \\ \\ 概念 && 主観的 & 意味的 \end{array}
『理解のしやすさ』と
『記号的な側面』を重視してこちらを採用しています。
(この立場だと「概念」はこれを用いて定義される)
数理哲学の範囲とする
整理しておくと
\begin{array}{lcl} 要請段階 && 名前と中身がある枠 \\ \\ 採用段階 && 数学的公理の選択 \\ \\ 構成段階 && \mathrm{NBG}なら情報はクラス \end{array}
これはこんな感じの構造になっているので
\begin{array}{ccc} 哲学 &\to& 数学 \\ \\ 枠 &\to& クラス \end{array}
これはこの段階では「哲学」範囲のものになります。
(採用する公理が決定された後に厳密さを持つ)
定義可能 Definable
|| 認識可能と集合論の公理を意味する表現
『認識したものを定義できる』の「省略表現」
\begin{array}{ccc} 定義可能 &\Longleftrightarrow& 認識論公理+集合論定義公理 \end{array}
これは「情報の存在」を保証するための
いわば「哲学的な制約」で
\begin{array}{lcl} 認識論公理 && 認識することは可能である \\ \\ 集合論定義公理 && 外延性公理+内包性公理 \end{array}
これにより考察対象は「数理」に落とし込まれます。
(哲学範囲の話を数理範囲の話にする工程)
制限全 Restricted All
|| 集合論の矛盾を回避する別表現
「無制限内包」についての外部制約
\begin{array}{lcl} \mathrm{ZF} &\to& 制限内包性公理 \\ \\ \mathrm{NBG} &\to& 無制限内包 \end{array}
これは「無制限内包」周りの専門性の高い部分について
(素朴集合論の矛盾を回避するための工夫)
\begin{array}{lcl} 要請段階 && 定義可能の要請的定義 \\ \\ 公理選択段階 && 内包性公理の形が決まる \\ \\ 全体確認段階 && 制限全の意識 \\ \\ 確定段階 && 定義可能の厳密な中身が確定 \end{array}
できる限り意識しなくて良いようにした
「変数の中身をとる場所」を定める外部装置になります。
(無制限内包はあまり意識しなくても特に問題無い)
制限全の役割
これは「情報」という概念を扱う時の
\begin{array}{lcl} 要請段階 && 名前と中身がある枠 \\ \\ 採用段階 && 数学的公理の選択 \\ \\ 構成段階 && \mathrm{NBG}なら情報はクラス \end{array}
「要請段階」と「採用段階」における
『全』の扱いに言及するもので
\begin{array}{ccc} 数学 &\to& 数理哲学 &\to& 哲学 \\ \\ 宇宙内全 &\to& 制限全 &\to& 全 \end{array}
それ以上の意味はありません。
(厳密な「全」の扱いを意識するための手順)
視覚化可能情報 Visualizable
|| 実用的数学基礎の基本となる原理
「定義」に基づく『原理』の翻訳
\begin{array}{ccc} 集合論 && 要素 &\in & 集合 \\ \\ 感覚的翻訳 && 具体的情報 &\in & 抽象的情報 \\ \\ \\ && \mathrm{Element} &\in& \mathrm{Set} \\ \\ && \mathrm{Instance} &\in & \mathrm{Abstract} \end{array}
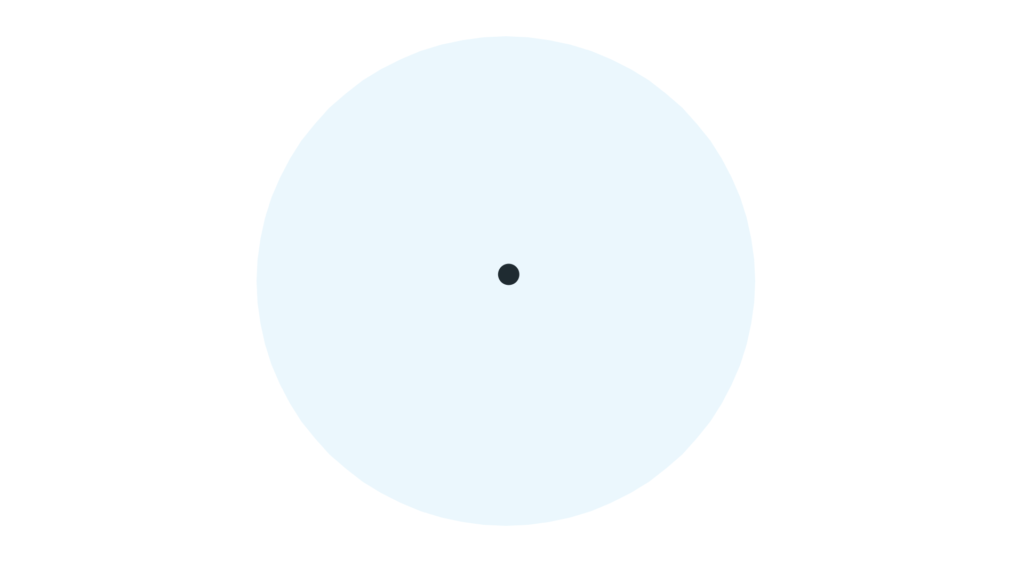
「集合論」のこれをより感覚に寄せた翻訳で
\begin{array}{ccccl} A&\in& B && \mathrm{be}(A,B) \\ \\ \\ 人間&\in& 動物 && 人間は動物である \\ \\ 魚 &\in& 動物 && 魚は動物である \\ \\ メダカ &\in& 魚 && メダカは魚である \\ \\ 鯛 &\in& 魚 && 鯛は魚である \end{array}
この観察から自然に得ることができます。
(抽象情報もより上位の抽象情報の具体情報になり得る)
同じという例外
非常に特異かつ厳しい条件
\begin{array}{ccccl} A&=&A && AはAである \\ \\ 私&=&私 && 私は私である \\ \\ 1+1&=&2 && 1+1は2である \end{array}
『抽象情報の中身』である
『具体情報が全て完全に一致する』場合に限り
(1つでも具体情報が異なっていてはいけない)
\begin{array}{ccc} 斎藤 &\in& 人間 && 〇 \\ \\ 山田 &\in & 人間 && 〇 \\ \\ 斎藤&=& 山田 && × \end{array}
「同じ」という状態はあり得ます。
(同一律以外は机上のもの)
基礎操作
「集合の操作」を考えた時
\begin{array}{lclcl} 部分集合 && A⊂B && AはBの一部 \\ \\ 共通部分 && A∩B && AとBに共通する要素 \\ \\ 和集合 && A∪B && AとBの全ての要素 \\ \\ 差集合 && A\setminus B && AからBの要素を取り除く \end{array}
基本となるものは多く考えられるわけですが
(他に補集合や冪集合なんかもある)
\begin{array}{ccc} 基礎 & \left\{ \begin{array}{lcl} 感覚的 && 冪集合× \\ \\ よく使う && 和集合× \\ \\ 分かり易い && 共通部分〇 \\ \\ 単純 && 応用操作× \end{array} \right. \end{array}
「実用的数学」における『基礎』は
\begin{array}{lcl} 情報の比較 &\to& 類似(共通部分) \\ \\ 情報の生成 &\to& 分類(部分集合) \end{array}
「情報の比較」操作と
「情報の生成」操作のみとします。
(単純な思考操作は ↑ とこれだけあれば十分)
類似 Similar
|| 情報の比較における基礎的な操作
「情報同士の比較」を行った時
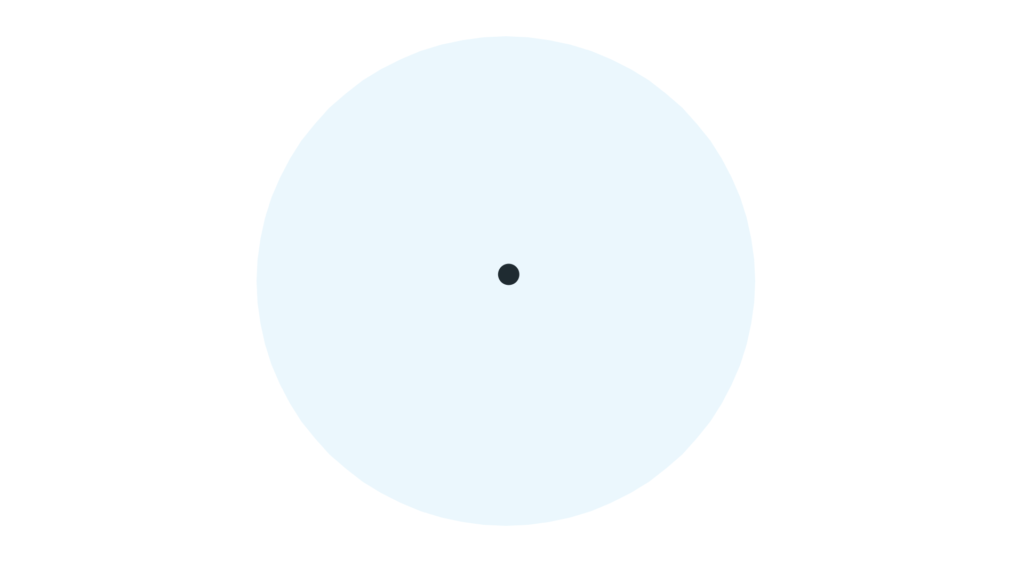
\begin{array}{ccc} 具体情報 &\in& 抽象情報 \end{array}
「抽象情報と具体情報」という形と
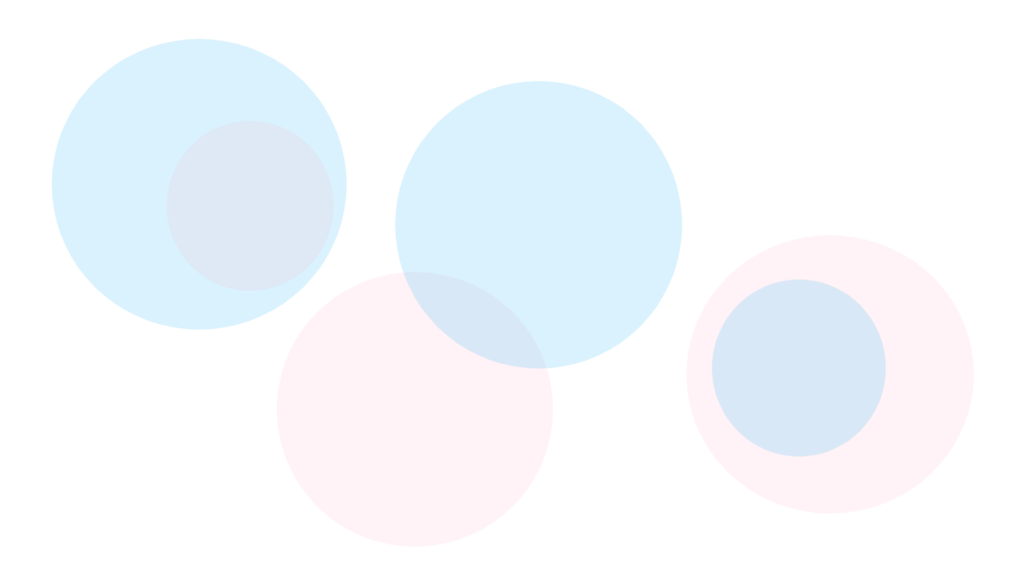
\begin{array}{lcl} 情報A &\subset & 情報B \\ \\ 情報B &\subset & 情報A \\ \\ 情報A &?& 情報B \end{array}
「どちらかに含まれる」という形以外に
(片方がもう片方の具体情報を全て持つ)
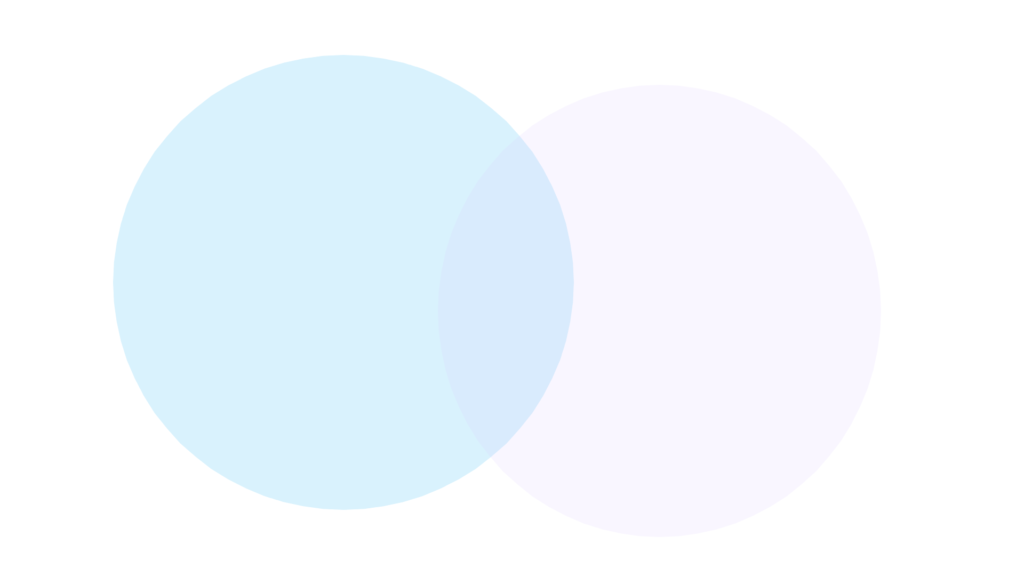
\begin{array}{ccc} 情報A∩情報B &≠& 空情報 \end{array}
「共通する情報を持つ」という状態が考えられます。
(空情報は具体情報を持たない情報とする)
これが「類似」を意味するもので
\begin{array}{lcl} 錯覚 &\to& 実際 \\ \\ 同じ &\to& 似てる \end{array}
この情報比較の観察と
\begin{array}{ccc} 両親∩子=\{内気\} &\to& 似てる \end{array}
『集合論の共通部分操作』が
(1つでも共通点があれば人は似てると感じる)
\begin{array}{ccl} 共通部分がある &\Longleftrightarrow& 似てる(同じという錯覚) \\ \\ 共通部分がある &\Longleftrightarrow& 類似していると感じる \end{array}
「類似(翻訳表現)」の由来になっています。
(「同じである」が錯覚であることを説明できる)
分類 Partition
|| 情報を創り出す時に使う操作
これは具体情報を持ってくる場所で
\begin{array}{ccc} どこからでも &\to& 分類情報の生成 \\ \\ 抽象情報 &\to& 狭義の抽象情報 \end{array}
それぞれ役割が異なる基礎操作になります。
(両方とも部分集合操作を用いる)
実例の観察を行えば
\begin{array}{lcl} ウロコがある水中生物の情報 &\to& 魚 \\ \\ 羽がある動物の情報 &\to& 鳥 \\ \\ \\ 数学を意味する情報 &\to& 現代の数学 \\ \\ 価値観についての情報 &\to& 現在の価値観 \end{array}
その身近さは実感しやすいでしょう。
(おそらく多くの人は直感的にこの感覚が分かる)
2値分類 Binarity
|| 完全に2分割するための基本操作
「補集合」操作を「分類」で翻訳したもの
\begin{array}{c} それ & & それ以外 && 合わせると全 \\ \\ A & & \lnot A && 排中律 \end{array}
これは「 A じゃない」の感覚の話で
(これにより「否定」の感覚を視覚化できる)
\begin{array}{lclcl} A &\longleftrightarrow & 非A && 非は \mathrm{not} \\ \\ A &\longleftrightarrow& \lnot A && \lnot も \mathrm{not} \\ \\ \\ 同一 &\longleftrightarrow& 非同一 && ほぼ全て非同一 \\ \\ 存在 &\longleftrightarrow& 非存在 && 非存在は観測不可 \\ \\ \\ 自分 &\longleftrightarrow& 自分以外 && 過去の自分は他人か問題 \\ \\ 人間 &\longleftrightarrow& 人間以外 && 人間の定義による \end{array}
実例としてはこんな感じです。
(きちんと2値になってるものは意外と少ないです)
認識外情報
これを用いる理由の大半は
\begin{array}{lclcl} 平等 &\Longrightarrow& 正しい平等 & それ以外の平等 \\ \\ 差別 &\Longrightarrow& 悪い差別 & それ以外の差別 \\ \\ 努力 &\Longrightarrow& 効果のある努力 & それ以外の努力 \\ \\ 自分 &\Longrightarrow& 正しい自分 & それ以外の自分 \end{array}
こんな感じの「情報を意識するため」で
(認識外の情報が意識できる)
\begin{array}{ccc} 正しい平等 &\subset & 正しいこと \\ \\ 悪い差別 &\subset & 悪いこと \end{array}
この基礎操作を使えば
\begin{array}{ccc} 平等 &≠& 正しい平等 &=& 正しいことの一部 \\ \\ 差別 &≠& 悪い差別 &=& 悪いことの一部 \end{array}
「情報の実態を考える」ことが可能になります。
(局所的な情報から全体を得る感じ)
3値分類 Fuzzy Binarity
|| 曖昧さが残ってる2値分類
「現実でよく見る2値分類」はほぼこれ
\begin{array}{lcl} それ &←& 確実にそれと分かる \\ \\ それ以外 &←& 確実にそれ以外と分かる \\ \\ 例外 &←& どちらか曖昧もしくはどちらでもない \end{array}
「現実の2値分類のほぼ全て」のことで
「2値分類」の『前段階』に当たるものになります。
\begin{array}{cccc} 真 & \longleftrightarrow & 偽 && 真偽不明 \\ \\ 正しい &\longleftrightarrow& 間違い && どちらか不明 \\ \\ \\ 正 &\longleftrightarrow& 負 && 0 \\ \\ 右 &\longleftrightarrow& 左 && 中間 \\ \\ 内 &\longleftrightarrow& 外 && 境界 \\ \\ \\ 善 & \longleftrightarrow & 悪 && 判別不明 \\ \\ 正義 &\longleftrightarrow& 悪 && どちらか不明 \\ \\ \\ 秩序 &\longleftrightarrow& 混沌 && 主観に依存 \\ \\ 美 &\longleftrightarrow& 醜 && どちらか不明 \\ \\ 強 &\longleftrightarrow& 弱 && 曖昧 \end{array}
ある情報と「情報の対義語」は
実はほとんどがこれに該当します。
(「~ではない」の表現以外はほぼ全て3値分類)
形式的定義
↑ の段階でもだいぶ形式に寄せましたが
整理ついでに厳密さの確保をしておきます。
(細かい厳密さについては数学に丸投げ)
\begin{array}{ccc} 情報 &\Longleftrightarrow& クラス \\ \\ \mathrm{Information} &\Longleftrightarrow& \mathrm{Class} \end{array}
「情報」は「クラス(集合と真クラス)」であるとする
(日本語は英語と比較して具体的な感覚が強い)
\begin{array}{ccc} 定義可能 &\Longleftrightarrow& 認識可能 &+& 定義公理 \\ \\ \mathrm{Definable} &\Longleftrightarrow& \mathrm{Recognizable} &+& \mathrm{Axioms} \end{array}
「定義可能」は「認識可能+定義公理」とする
(情報という概念を定義する上での哲学的な制約)
\begin{array}{ccc} 具体情報 &\in & 構成可能宇宙 \end{array}
「ドメイン(変数範囲)」は「構成可能宇宙」とする
\begin{array}{ccc} \mathrm{Visualizable \,\, Set} &\Longleftrightarrow& \mathrm{Class} \end{array}
「視覚化可能情報」は「クラス」であり
(集合としての側面を強調した情報の呼び方)
\begin{array}{ccc} 要素 &\in & 集合 \\ \\ 具体的情報 &\in & 抽象的情報 \\ \\ \\ \mathrm{Element} &\in& \mathrm{Set} \\ \\ \mathrm{Instance} &\in & \mathrm{Abstract} \end{array}
その基礎は「抽象情報と具体情報」であるとする
(同じ A=A はこの特殊な例外とする)
\begin{array}{ccc} 分類 &\Longleftrightarrow & 部分集合 \\ \\ \mathrm{Partition} &\Longleftrightarrow& \mathrm{SubSet} \end{array}
「分類」は「部分集合」であるとする
\begin{array}{ccc} 類似してる &\Longleftrightarrow& 共通部分がある \\ \\ \mathrm{Similar} &\Longleftrightarrow& A∩B≠∅ \end{array}
「類似」は「共通部分の存在」とする
(似ているより少し硬くて薄い表現)
\begin{array}{ccc} 2値分類 &\Longleftrightarrow& 集合 &+&補集合 \\ \\ \mathrm{Binarity} &\Longleftrightarrow& A&+&\overline{A} \end{array}
「分類の基礎操作」として
「2値分類」を「補集合」で定義する
(ある情報と「その情報ではない」に限り成立)
\begin{array}{ccc} 3値分類 &\Longleftrightarrow&情報&反対の情報&例外 \\ \\ \mathrm{Fazzy \,\, Binarity}&\Longleftrightarrow&A&B& C \end{array}
これより「直感的な操作」として
「3値分類」をこのように定義する
(ある情報とその対義語についての分類)
