|| 情報や概念と非常に似ている人間の原理
「観測者にとって」の「認識可能範囲」のこと
スポンサーリンク
目次
基礎記憶「記憶の最小単位」
既知記憶「既に記憶してる情報」
関連「共通部分がある ⇔ 関連がある」
知覚「強制的に認識される ⇔ 知覚する」
分かる「記憶が可能である ⇔ 分かる」
導入
「記憶」というのは
「観測者にとっての情報」のことである
\begin{array}{ccc} 記憶 &\Longrightarrow& 記憶可能な情報 \\ \\ 記憶 &\Longrightarrow& 記憶可能な概念 \end{array}
まだちょっと曖昧ではありますが
これはわりと納得できると思います。
\begin{array}{ccc} 記憶 &\subset& 記憶可能な情報 &\subset & 認識可能範囲 \end{array}
私たちは「記憶できること」以外を認識できませんし
それ以上の範囲から逸脱することは決してありません。
(これ故に「知識による差」は必ず生じる)
記憶 Memory
|| 認識可能な情報の一部
「観測者が認識可能な情報」の一部分
\begin{array}{lcl} 基礎記憶 &\Longleftrightarrow& 最下層に来る情報 \\ \\ 既知記憶 &\Longleftrightarrow& 思い出すことができる記憶 \\ \\ 未記憶情報 &\Longleftrightarrow& まだ記憶してない情報 \end{array}
主に「3分類」によって分けることができます。
(私たちが思い出せるのは常に過去の情報)
基礎記憶 Fundamental
|| 観測者に依存する記憶の基礎
「人間」にとっては「五感を表す情報」のこと
\begin{array}{ccc} 機械 &\Longleftrightarrow& 0,1 \\ \\ 人間 &\Longleftrightarrow& 五感情報 \end{array}
「観測者」に依存する概念なので
\begin{array}{ccc} 観測者 &\to& 扱える記憶 &\to& 基礎記憶 \end{array}
「観測者の厳密な定義」によって
(観測者を記憶を要素に持つ集合とするなど)
\begin{array}{lcl} 直感的要請段階 && 観測者の記憶基盤 \\ \\ 形式的要請段階 && 基礎として定義できる情報 \\ \\ 公理選択段階 && 記憶を意味する情報を翻訳 \\ \\ 公理確定段階 && 記憶を集合として厳密に扱える \end{array}
「厳密な意味での基礎記憶」は定義されます。
(この段階では直感的な要請的定義に留まる)
五感情報
補足しておくと
「人間の基礎記憶」を表現する『情報』は
\begin{array}{ccc} 五感情報 & \left\{ \begin{array}{ll} 視覚情報 & \left\{ \begin{array}{lcl} 色がある \\ \\ 透明 \\ \\ 明るい \\ \\ 暗い \end{array} \right. \\ \\ \\ 聴覚情報 & \left\{ \begin{array}{ll} 心地良い \\ \\ うるさい \\ \\ 気にならない \end{array} \right. \\ \\ \\ 触覚情報 & \left\{ \begin{array}{ll} 柔い \\ \\ 固い \\ \\ 気持ち良い \\ \\ 痛い \end{array} \right. \\ \\ \\ 味覚情報 & \left\{ \begin{array}{ll} 旨い \\ \\ 塩っぽい \\ \\ 甘い \\ \\ 苦い \\ \\ 渋い \end{array} \right. \\ \\ \\ 嗅覚情報 & \left\{ \begin{array}{ll} 無臭 \\ \\ 良い匂い \\ \\ 臭い \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array}
知っての通りこんな感じです。
(程度について追加すれば表現の精度を上げられる)
\begin{array}{ccc} 五感情報の本質 & \left\{ \begin{array}{ll} xは視覚を意味する情報である \\ \\ xは聴覚を意味する情報である \\ \\ xは触覚を意味する情報である \\ \\ x は味覚を意味する情報である \\ \\ x は嗅覚を意味する情報である \end{array} \right. \end{array}
ある程度正確に定義できるのは「本質まで」なので
この中身が確定した段階で厳密に扱えるようになります。
(この中身が多いと「表現力が豊か」と言われる)
既知記憶 Known
|| 厳密に扱える範囲の記憶
「思い出すことが可能な記憶」のこと
\begin{array}{lcl} 直感的要請段階 && 思い出せること \\ \\ 形式的要請段階 && 一部言語化できる思い出せる情報 \\ \\ \\ 公理選択段階 && 記憶を形式言語に翻訳 \\ \\ 公理確定段階 && 記憶情報を厳密に扱える \end{array}
「既に記憶している」と分かっている
この段階の「記憶」のことで
\begin{array}{lcl} 既知記憶 && 現時点で思い出せる情報 \\ \\ 未記憶情報 && 未来で記憶する可能性のある情報 \end{array}
私たちが「厳密に」取り扱えるのは
この「既知記憶」のみになります。
基礎原理
この記事では
「思考が意識される」前の段階である
\begin{array}{lcl} 記憶直感段階 && なんとなく前のことを思い出せる \\ \\ 記憶言語化段階 && 思い出せることを記憶と名付ける \\ \\ 記憶整理段階 && 記憶がどういうものか言語化される \\ \\ \\ 思考直感段階 && 思考の原型となる感覚が分かる \\ \\ 思考言語化段階 && 記憶の操作を思考と名付ける \\ \\ 思考整理段階 && 思考がどういうものか言語化される \end{array}
「記憶整理段階」までの記憶原理の話を扱います。
(思考についての詳細は別の記事で)
関連 Common
|| 記憶同士の関係における1つの形態
「共通部分の有無」の原型となる概念
\begin{array}{lcl} AとBに関連がある &\Longleftrightarrow& AとBに共通部分がある \\ \\ AとBに関連が無い &\Longleftrightarrow& AとBに共通部分が無い \end{array}
「集合論」における
\begin{array}{rcl} \mathrm{Common}(A,B) &\Longleftrightarrow& A∩B≠∅ \\ \\ \lnot\mathrm{Common}(A,B) &\Longleftrightarrow& A∩B=∅ \end{array}
「集合の関係」に対応するもので
(順番的には関連の感覚を意味する直感が先)
\begin{array}{rcl} AとBに関連がある &\Longleftrightarrow& \mathrm{Common}(A,B) \end{array}
「情報」同士の関係はこれでほとんど説明ができます。
(関連は記憶の基礎的な関係の1つ)
記憶の関係
以上の「関連」と合わせて
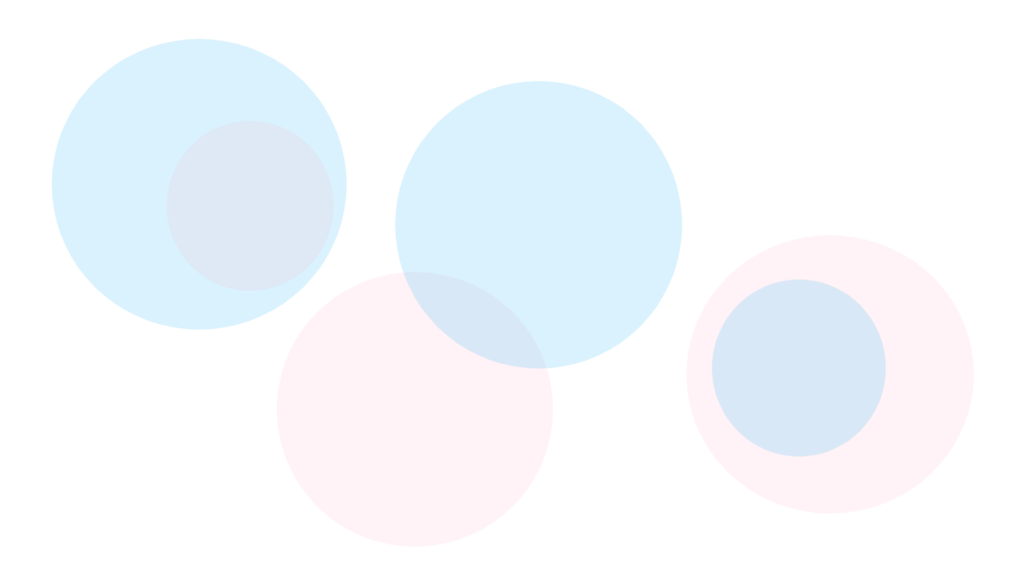
\begin{array}{ccc} 記憶の関係 & \left\{ \begin{array}{lcl} A\in B && AはBの具体情報である \\ \\ A\in B && BはAの抽象情報である \\ \\ A∩B≠∅ && AとBには関連がある \\ \\ A∩B=∅ && AとBには関連が無い \end{array} \right. \end{array}
「記憶」同士の『関係』は
このような形で定義することができます。
(これは集合の関係をそのまま翻訳した形)
境界が概念によって曖昧
直感的な概念の構成を考えると
\begin{array}{ccc} 道具 \in もの &\to& 道具∩もの=\{椅子,机,箸,携帯,...\} \\ \\ 魚 \in 動物 &\to& 魚∩動物=\{ 鯖,鰯,鯉,金魚,... \} \end{array}
「具体と抽象」という形と
「共通部分がある」という形には
\begin{array}{ccc} A\in B &\to& A∩B≠∅ \end{array}
あまり明確な違いが無いように見えます。
(これ故に「関連」を自然に定義できていると言える)
これ自体は正常な感覚なんですが
「集合の構成」を考えると
\begin{array}{lcl} \{a\} \in \Bigl\{ \{a\} \Bigr\} &\to& \{a\}∩\Bigl\{ \{a\} \Bigr\}=∅ \\ \\ \{a\} \in \Bigl\{ a,\{a\} \Bigr\} &\to& \{a\}∩\Bigl\{ a,\{a\} \Bigr\}=\{a\} \end{array}
「関連が無い」という状態と
「関係がある」という状態は両立させることが可能で
\begin{array}{ccc} 赤い \in りんご &\to& 赤い∩りんご=? \end{array}
「区別が必要そうな概念」もまた確かに存在するため
(最小単位となる五感情報であれば共通部分は無い)
\begin{array}{ccc} ほとんど && A\in B &\to& A∩B≠∅ \\ \\ 下層の形式 && A\in B &\to& A∩B=∅ \end{array}
「区別が必要な概念を表現する」ために
この部分はこのように定義する必要があります。
(別で定義しないとここを分離できない)
知覚 Sense
|| 強制的に入ってくる情報
「記憶になる前」段階の「入力される情報」のこと
\begin{array}{ccc} Iを感覚器官が自動的に入力する &\Longleftrightarrow& Iを知覚する \end{array}
「思い出せないもの」は
「記憶である」と『認識することさえできない』
\begin{array}{lcl} 直感的知覚段階 && 五感などが拾った情報 \\ \\ 形式的知覚段階 && 記憶媒体に情報が記録される \\ \\ \\ 直感的記憶段階 && いくつかの情報は思い出せる \\ \\ 形式的記憶段階 && 思い出せる情報が記憶になる \end{array}
これを説明するのに適した概念が「知覚」で
(知覚の具体的な中身は観測者の感覚器官に依存する)
\begin{array}{ccc} 知覚情報 & \left\{ \begin{array}{lcl} 記憶情報 && 思い出せる情報 \\ \\ 忘却情報 && 思い出せない情報 \end{array} \right. \end{array}
「知覚情報の一部」が「記憶」になります。
(ほとんどは忘却情報に分類される)
分かる Fit
|| 観測者に情報が馴染む感覚
「記憶可能」を定義するための「主観的判定」
\begin{array}{lcl} 入力段階 && Iは知覚情報である \\ \\ 処理段階 && Iは観測者の記憶と関係がある \\ \\ 出力段階 && Iは記憶可能情報である \end{array}
「観測者」に強く依存する概念で
(思い出すためには五感情報などの記憶との関係が必要)
\begin{array}{lcl} 分かりやすい &\Longleftrightarrow& 記憶しやすい \\ \\ 分かり辛い &\Longleftrightarrow& 記憶し辛い \end{array}
「分かり易い情報」が
「なぜ分かり易いか」を説明する根拠になります。
無意識段階と意識段階
実感レベルで分かる通り
\begin{array}{lcl} 知覚段階 && 感覚器官が勝手に情報を入力 \\ \\ 記憶段階 && 思い出せる情報が存在する \\ \\ 分かる確認段階 && 記憶が馴染みやすいか評価 \end{array}
人は「分かると確認する」前の段階で
情報を「記憶する」ことができます。
なので「分かる」の段階は
「記憶の後」の段階に来るんですが
\begin{array}{lcl} 知覚段階 && 感覚器官が勝手に情報を入力 \\ \\ 直感的分かる段階 && 知覚情報の無意識評価 \\ \\ 意識段階 && 分かる情報を優先して認識 \\ \\ \\ 無意識記憶段階 && 優先認識する情報を優先記憶 \\ \\ 意識記憶段階 && 思い出せる情報を記憶として認識 \\ \\ 確認的分かる段階 && 記憶の意識的な評価 \end{array}
これを細分化してみると
\begin{array}{lcl} 直感的分かる段階 && 知覚情報の無意識評価 \\ \\ 記憶段階 && 思い出せる情報が存在する \\ \\ 確認的分かる段階 && 記憶の意識的な評価 \end{array}
『無意識段階の分かる』と
『意識段階の分かる』が明らかに存在し
\begin{array}{lcl} 無意識に分かる && ぱっと見で意識がそこに向く \\ \\ 記憶可能である && 分かる情報は記憶しやすい \\ \\ 意識的に分かる && 思い出せる情報の評価 \end{array}
これらは「記憶」の段階をまたいでいることが分かるため
(両者の順番は異なるが処理の内容は同様)
\begin{array}{lcl} 記憶前段階の分かる && 知覚情報を記憶可能情報へ \\ \\ 記憶後段階の分かる && 記憶可能情報を理解情報へ \end{array}
「記憶の後の段階」なのが事実であるように
「記憶の前の段階」に来るのも事実になります。
(理解情報は「ほぼ確実に記憶可能な情報」のこと)
分かり易い
これについては
\begin{array}{lcl} 記憶し易い情報 && 手,水,... \\ \\ 記憶し辛い情報 && 籤,\mathrm{hnhauwpnu},... \end{array}
具体的な事例を見れば
\begin{array}{ccl} 手 &\to& 関係する記憶が多い \\ \\ \mathrm{btauapiueh} &\to& 関係する記憶がほぼ無い \end{array}
普通に納得できると思います。
(人は自身の記憶に関係する情報を覚えやすい)
実感のまま
\begin{array}{ccc} 分かる情報 & \left\{ \begin{array}{lcl} 五感情報で説明できる \\ \\ 理解情報で説明できる \end{array} \right. \end{array}
「分かり易い情報」というのが
「記憶し易い情報」です。
記憶の関係と分かり辛さ
「記憶し易い情報」が
「分かり易い情報」であるという事実を使うと
\begin{array}{lcl} 分からない情報 & \left\{ \begin{array}{lcl} 五感情報で説明し辛い \\ \\ 理解情報で説明し辛い \end{array} \right. \end{array}
「記憶し辛い情報」を記憶する方法として
\begin{array}{ccc} 分かりやすくする情報 & \left\{ \begin{array}{l} 全体の感覚を説明する情報 \\ \\ 実際に使われる情報 \\ \\ 良い感じに分解された情報 \end{array} \right. \end{array}
「記憶し易い情報との関係」を増やす
\begin{array}{cl} マイナーな料理 & \left\{ \begin{array}{ll} 調味料や材料 \\ \\ 基本五味の程度 \\ \\ 詳しい触感 \\ \\ 匂いの感じ \end{array} \right. \\ \\ \\ 数学 & \left\{ \begin{array}{l} 正しさを追求する \\ \\ 高精度の未来予測で使う \\ \\ 使う言語は論理学から \\ \\ 0,1,2,3,... みたいな自然数が主役 \end{array} \right. \end{array}
そんな手段を導くことができます。
(記憶力が良い人はこれを無意識にやっている)
分かりたい
「記憶」の原理プロセスにおいて
\begin{array}{lcl} 知覚段階 && 感覚器官が勝手に情報を入力 \\ \\ 直感的分かる段階 && 知覚情報の無意識評価 \\ \\ 意識段階 && 分かる情報を優先して認識 \\ \\ \\ 無意識記憶段階 && 優先認識する情報を優先記憶 \\ \\ 意識記憶段階 && 思い出せる情報を記憶として認識 \\ \\ 確認的分かる段階 && 記憶の意識的な評価 \end{array}
↑ では「知覚」の段階から扱ってきましたが
(記憶初期段階と無意識の範囲は ↑ で説明できる)
「知覚」の段階を経た『後』では
(初期段階ではそもそも「言語」が存在しない)
\begin{array}{lcl} 無意識欲求段階 && 特定の情報への関心 \\ \\ 意識段階 && 知りたい情報を優先して認識 \\ \\ \\ 無意識記憶段階 && 優先認識情報を記憶可能情報へ \\ \\ 意識記憶段階 && 思い出せる情報を記憶として認識 \end{array}
「これを知りたい」というような
(言語が無ければ「知りたい」を認識できない)
\begin{array}{rcl} 無意識的知的欲求 &\to& \left\{ \begin{array}{l} 基礎記憶に関係 \\ \\ 無意識の疑問に由来する \\ \\ 偶発的な分かる情報の発見 \end{array} \right. \\ \\ \\ 意識的知的欲求 &\to& \left\{ \begin{array}{l} 自覚的な欲に由来する \\ \\ 既知記憶から生じた疑問に由来する \\ \\ 意識的な情報への関心 \end{array} \right. \end{array}
「欲求」による記憶プロセスも考えることができます。
(この段階から「思考」の操作に該当してくる)
