|| 集合論から得られた数学の公理
『直感的な集合論』を厳密に整備した集合論のこと
スポンサーリンク
目次
同一律「それがそれ自身だっていう保証」
定義の一意性
外延性公理「中身が同じなら同じもの」
制限内包性公理「条件を使って集合が作れる」
性質の保証
基礎公理「下地がちゃんとある」
無限公理「有限じゃない集合がある」
操作の保証
写像公理「像や像の集まりが集合であることの保証」
和集合公理「要素を合体させたような集合がある」
具体集合生成公理「中身を指定して生成できる集合がある」
冪集合の公理「部分集合を全部集めた集合がある」
サイズの限界と選択
到達不能基数「中身が分かるサイズの限界」
選択公理「選んだものだけで集合が作れる」
集合の基本概念
空集合の存在「要素を持たない集合の存在」
積集合「共通部分になる集合」
必要な知識
これの基盤になる話として
\begin{array}{ccc} x \in\{ n\in N \mid nは奇数 \} &\Longleftrightarrow& \forall x \in N \,\, xは奇数 \end{array}
またそれを表す形式的表現として
『量化記号』が使われるのでこれも必須
\begin{array}{lcc} Sの要素数 &\Longleftrightarrow& \mathrm{Cardinal}(S) \\ \\ Sの要素数はn&\Longleftrightarrow& |S|=n \end{array}
最後に上から抑える概念として
『基数』も知っておきたいところです。
集合の存在公理 \mathrm{Identity}
|| 当たり前ってことにしないといけない
これはいわゆる『同一律』のことで
\begin{array}{c} ∃S&\Bigl( S=S \Bigr) \end{array}
「それはそれだ」みたいな感覚を形式化したものです。
(これがないと = を使うことができない)
外延性公理 \mathrm{Extension}
|| 定義のやり方その 1
これは「外延的記法」の形式的な表現で
\begin{array}{llllll} \displaystyle ∀S_X∀S_Y &\Bigl( & \Bigl( \textcolor{skyblue}{∀e} \Bigl[ (e∈S_X)⇔(e∈S_Y) \Bigr]\Bigr) ⇒ \Bigl[ \textcolor{skyblue}{S_X=S_Y} \Bigr] & \Bigr) \end{array}
「中身が一緒なら同じ」ということをこれは保証します。
(これがないと同じであることの確認方法が無い)
見やすさのため
できるだけ記号を外した形は
\begin{array}{ccc} \textcolor{skyblue}{∀e} \,\, e∈X⇔e∈Y &\Longrightarrow& X=Y \end{array}
こんな感じです。
(先に紹介した定義はこの変数を量化した形)
具体的な感覚
補足しておくと
\begin{array}{lcl} \{1,2,3\}&=&\{2,1,3\} \\ \\ \{1,2,3\}&=&\{3,1,2\} \\ \\ \{1,2,3\}&=&\{1,1,2,3,3\} \end{array}
具体的にはこういう感じで
この場合は要素の並びに意味はありません。
順番に意味を持たせたい場合は
要素を「順番とセットのペア」にしなければならず
\begin{array}{lcccl} 1,2,3 &&→&&\{ (1,1),(2,2),(3,3) \} \\ \\ 2,1,3 &&→&&\{(2,1),(1,2),(3,3)\} \\ \\ 1,2,3,2 &&→&&\{ (1,1),(2,2),(3,3),(2,4) \} \end{array}
具体的にはこのようにする必要があります。
(基本的に「並び順」や「重複」は無視される)
制限内包性公理 \mathrm{Intension}
|| 定義のやり方その 2
「内包的記法」の形式的な表現のこと
\begin{array}{llllll} \displaystyle S_{\mathrm{intension}}&=&\{e∈S_{\mathrm{domain}} \mid φ(e) \} \end{array}
これは「ラッセルのパラドックスを回避」した
『条件 φ を満たす要素 e の集まり』を意味していて
\begin{array}{ccc} e\in 全て &&\to && e\in 特定の集合 \end{array}
「条件を満たす要素 e の範囲」は
「 S_{\mathrm{domain}} という集合」に限定されています。
(集合全体からではないため分離・分出公理とも呼ばれる)
条件の具体的な意味
また「条件 φ 」というのは
\begin{array}{ccc} φ&=&(φ_1,φ_2,...,φ_n) \end{array}
『一階述語論理』の範囲で許されている
『論理式の有限の列』に限定されているため
\begin{array}{ccc} φ,ψ &\in & \mathrm{AtomicFormula} &\subset & \mathrm{Well}\text{-}\mathrm{Formed}\mathrm{Formula} \end{array}
\begin{array}{ccc} \lnot φ &\in & \mathrm{Well}\text{-}\mathrm{Formed}\mathrm{Formula} \\ \\ φ∧ψ &\in & \mathrm{Well}\text{-}\mathrm{Formed}\mathrm{Formula} \\ \\ φ∨ψ &\in & \mathrm{Well}\text{-}\mathrm{Formed}\mathrm{Formula} \\ \\ φ⇒ψ &\in & \mathrm{Well}\text{-}\mathrm{Formed}\mathrm{Formula} \\ \\ φ⇔ψ &\in & \mathrm{Well}\text{-}\mathrm{Formed}\mathrm{Formula} \\ \\ \\ \forall x \,\, φ &\in & \mathrm{Well}\text{-}\mathrm{Formed}\mathrm{Formula} \\ \\ \exists x \,\, φ &\in & \mathrm{Well}\text{-}\mathrm{Formed}\mathrm{Formula} \end{array}
「全ての条件」を扱えるわけではありません。
(整論理式 \mathrm{Well}\text{-}\mathrm{Formed}\mathrm{Formula} に限定される)
補足しておくと
\begin{array}{llllll} \displaystyle e∉S \\ \\ e∈A∧e∈B \\ \\ 1≤n<10 \end{array}
有限列の論理式 φ の中身はこんな感じです。
(複雑なものは分解されるので基本的にシンプルになる)
公理的集合論の発端という側面
これの「制限」というのは
\begin{array}{lcl} S_{\mathrm{unlimited}}&=&\{e \mid φ(e) \} \\ \\ S_{\mathrm{intension}}&=&\{e∈S_{\mathrm{domain}} \mid φ(e) \} \end{array}
「ラッセルのパラドックスの回避」から来ていて
(この矛盾が集合論を見直すきっかけになった)
\begin{array}{ccc} S_{\mathrm{unlimited}}&=&\{e \mid φ(e) \} && × \end{array}
「無制限の内包」を制限しているという意味で
「制限内包性公理」と呼ばれています。
正則性公理 \mathrm{Foundation}
|| 基礎(一番下)が存在することの保証
「基礎公理」「整礎性公理」と呼ばれることもあります。
\begin{array}{llllll} \displaystyle \textcolor{skyblue}{∀S}&\Bigl( &[\,S≠∅\,]⇒\textcolor{skyblue}{∃s}\Bigl[ \,(s∈S)∧\textcolor{skyblue}{¬(∃e_c\,(e_c∈S∧e_c∈s)}) \, \Bigr] &\Bigr) \\ \\ \textcolor{skyblue}{∀S≠∅}&\Bigl(&\,\textcolor{skyblue}{∃s∈S\,[\,s∩S=∅\,]} &\Bigr) \end{array}
この形式だけだと分かり辛いですが
要は「下地がちゃんとある」って話で
\begin{array}{ccc} ∃s\in S & s∩S=∅ \end{array}
これを「全ての非空集合 S に要求する」というのが
「基礎公理」が「集合に課す制限」になります。
(例外なく一元集合でも s の存在を強制する)
数学的帰納法の感覚と集合
「集合を厳密に取り扱う」場合
\begin{array}{ccr} && ∅\in V \\ \\ S_n\in V &\to& S_{n+1}\in V \end{array}
「大きな集合」から直接扱うよりも
「最小」「後者」のような形で扱う方が
\begin{array}{ccc} ? &\in& S_{?} \end{array}
なにも決まってない状態よりも扱いやすい。
これはすぐに納得できる事実だと思います。
数学的帰納法の感覚と宇宙
実際、この考えによって生まれたのが
\begin{array}{lcc} V_0 &=& ∅ \\ \\ V_{α+1} &=& \mathrm{Power}(V_α) \\ \\ V_λ &=& \displaystyle \bigcup_{β\in λ} β \end{array}
「フォンノイマン宇宙」と呼ばれる概念で
\begin{array}{ccc} 議論領域内の話にしたい \\ \\ ↓ \\ \\ 宇宙という追跡可能な実体のみを使う \end{array}
私たちの扱う数学の対象は
全てこの「宇宙」の中に納まるようになっています。
(より厳密にはそのくらい広くなるよう宇宙は定義される)
数学的帰納法の感覚と集合としての自然数
ただ歴史的な流れとしては
「宇宙」よりも先に「基礎公理」が発見されてるので
\begin{array}{ccr} && ∅\in V \\ \\ S_n\in V &\to& S_{n+1}\in V \end{array}
その感覚は「宇宙から」ではなく
「数学的帰納法から」来てると考えるのが自然です。
(宇宙は閉鎖性と数学的帰納法から着想を得ている)
実際、代表的な集合として
\begin{array}{ccr} && ∅\in N \\ \\ n\in N &\to& n∪\{n\}\in N \end{array}
「自然数全体 N 」という集合は
(大小関係は推移的で部分集合には最小元が存在)
\begin{array}{ccl} 0&=&\{\} \\ \\ 1&=&\{0\} \\ \\ 2&=&\{0,1\} \\ \\ 3&=&\{0,1,2\} \\ \\ &\vdots \\ \\ n+1&=&\{0,1,2,3,...,n\} \end{array}
厳密にはこのように定義されています。
(この定義が順序数の定義に繋がる)
集合としての表現と帰属関係
そしてこの定義においては
\begin{array}{ccc} n<k &\Longleftrightarrow& n\in k \end{array}
「順序」はこのように定義されていて
(厳密には全ての要素と比較できるとは限らない)
\begin{array}{ccc} 0 &\in& n \end{array}
「一番下の集合」は
必ず他の全ての集合より下に位置します。
(この < は自然数や実数のそれとは厳密には異なる)
階層構造と下の集合
この「下」というのは
仮に自然数のような一直線の構造でなくとも
\begin{array}{ccc}\displaystyle \left\{ \Bigl\{ \{ ∅ \} \Bigr\}, \Bigl\{ ∅,\{ ∅ \} \Bigr\} \right\} \end{array}
「全ての集合」で言えることなので
(厳密にはこれは直感的な話)
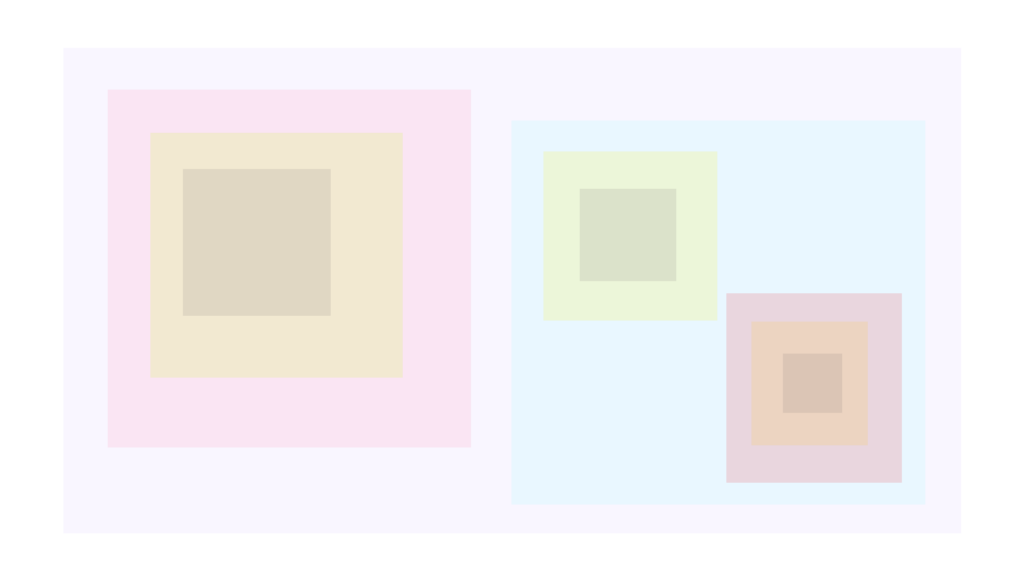
\begin{array}{ccc} ∅ &\in& \{ ∅ \} &\in& \Bigl\{ \{ ∅ \} \Bigr\} &\in& \displaystyle \left\{ \Bigl\{ \{ ∅ \} \Bigr\}, \Bigl\{ ∅,\{ ∅ \} \Bigr\} \right\} \\ \\ ∅ &\in& \{ ∅ \} &\in& \Bigl\{ ∅,\{ ∅ \} \Bigr\}&\in& \displaystyle \left\{ \Bigl\{ \{ ∅ \} \Bigr\}, \Bigl\{ ∅,\{ ∅ \} \Bigr\} \right\} \\ \\ ∅ && {} &\in& \Bigl\{ ∅,\{ ∅ \} \Bigr\} \end{array}
『普通の集合』であれば
「下」が必ず存在するはずだと言えます。
下が存在しない構造
直感的に考えるのであれば
「帰属関係 \in 」を下に辿っていくと
\begin{array}{ccc} ∅ &\in& \cdots &\in& S \end{array}
最終的には「一番下」に辿り着けるはずですが
\begin{array}{ccc} 無限降下列 && \cdots\in S_n \in \cdots \in S_1 \in S_0 \\ \\ 自己参照 && S=\{S\} \\ \\ 循環 && X\in Y\in X \end{array}
例えばこういった構造が成立する場合
(一番下という構成要素が不明な形)
\begin{array}{ccc} S&=&\{ ∅,S \} \end{array}
『全ての集合』では
「一番下」を得ることができなくなります。
(これの部分集合 S=\{S\} には確実に一番下が無い)
一番下とこれらを取り除ける条件
「基礎公理」というのは
\begin{array}{ccc} 無限降下列 && \cdots\in S_n \in \cdots \in S_1 \in S_0 \\ \\ 自己参照 && S=\{S\} \\ \\ 循環 && X\in Y\in X \end{array}
この「 ↑ だけ」を弾くために得られたもので
(一番下が無いと帰納的な構造が作れない)
「集合(非空)には一番下がある」という違いから
(一番下が無いか有るかがこれらの分かり易い違い)
\begin{array}{ccc} sを集合Sの一番下の要素とする \\ \\ ↓ \\ \\ より厳密にはsは極小元となるはず \\ \\ ↓ \\ \\ Sの要素xの中にx\in sとなるxが存在しない \\ \\ ↓ \\ \\ この「極小元の存在」が基礎公理の原型になる \end{array}
このような発想を経て
(基礎公理の原型は極小元の存在保証)
\begin{array}{ccc} x\in S ∧ x\not\in s \\ \\ ↓ \\ \\ S∩s=∅ \end{array}
「簡単な操作にしたい」という要望を経ることで
結果的にこの形を得ることができます。
(本当に大丈夫かの確認は別記事で)
無限公理 \mathrm{Infinity}
|| 後者について閉じてる集合がありますよ
一般形は「原子帰納的関数」の一種である
「後者関数 \mathrm{Successor \,\, Function}」で表現されます。
\begin{array}{llllll} \displaystyle ∃S&\Bigl(& (∅∈S)∧\Bigl( ∀e∈S\,(\textcolor{skyblue}{\mathrm{Suc}(e)∈S}) \Bigr) &\Bigr) \end{array}
「後者関数」を具体的に書き直した形は ↓ で
\begin{array}{llllll} \displaystyle ∃S&\Bigl(& (∅∈S)∧\Bigl( ∀e∈S\,(\textcolor{skyblue}{e∪\{e\}∈S}) \Bigr) &\Bigr) \\ \\ ∃S&\Bigl(& (∅∈S)∧\Bigl( ∀e∈S\,(\textcolor{skyblue}{2^e∈S}) \Bigr) &\Bigr) \end{array}
これも「無限公理」と呼ばれることがあります。
(この公理は厳密には「後者公理」と呼んだ方が適切です)
補足しておくと
\begin{array}{llllll} \displaystyle \mathrm{Suc}(e)&=&e∪\{e\} \\ \\ \mathrm{Suc}(e)&=&2^e \end{array}
この形の由来については
「自然数」について知っていればなんとなく分かります。
無限の存在
これは「自然数の非有界性」と
\begin{array}{ccc} \displaystyle \mathrm{Number}_{\mathrm{max}}&<&\mathrm{Number}_{\mathrm{max}}+1 \end{array}
本質的には同じ話で
(最大値が存在するという仮定は否定される)
\begin{array}{ccc} A\in B &\Longleftrightarrow& A<B \end{array}
『無限集合が存在する』というより
\begin{array}{ccc} \forall S∈N&S∈S_{\mathrm{lim}} && ? \end{array}
『最大になる有限の集合 S_{\mathrm{lim}} 』が
(ここでは最大を定義できる順序を \in であるとする)
\begin{array}{ccc}\mathrm{Suc}(e)&=&e∪\{e\} \end{array}
「後者の存在」により
\begin{array}{cc} S_{\mathrm{lim}}∪\{S_{\mathrm{lim}}\} &\in & S_{\mathrm{suc}} &\not\in& S_{\mathrm{lim}} \end{array}
否定されるという話になります。
(最大が無い → 限りが無い)
写像公理 \mathrm{Permutation}
|| 置き換えについての保証
『写像』の操作ができる保証のことで
(置換公理とも呼ばれることが多い)
\begin{array}{lcl} \forall X & \Bigl( \mathrm{Image} (X,y) &⇒& \exists Y \,\, \mathrm{Range}(X,Y) \Bigr) \end{array}
『要素の像』や『像の集まり』が
\begin{array}{ccl} \mathrm{Image}(X,y) & \Longleftrightarrow & \forall x\in X \,\, \exists ! y \,\, φ(x,y) \\ \\ \mathrm{Range}(X,Y) & \Longleftrightarrow & \forall x\in X \,\, \exists y\in Y \,\, φ(x,y) \end{array}
『集合である』ことをこの公理は保証します。
( φ は内包性公理で出てきた整論理式です)
分割しているのは
「像の一意性」についてと
「像の集まり(値域)」の部分で
\begin{array}{ccl} \mathrm{Image}(X,y) & \Longleftrightarrow & xの像yは1つしかない \\ \\ \mathrm{Range}(X,Y) & \Longleftrightarrow & xの像としてYの要素yが存在する \end{array}
そこそこ意味が違うからです。
念のため補足しておくと
\begin{array}{ccc} \exists ! a \,\, φ(a) &\Longleftrightarrow& \exists a \,\, \Bigl( φ(a)∧\forall b \,\, \Bigl( φ(b)⇒b=a \Bigr) \Bigr) \end{array}
「唯一存在記号 \exists ! 」の定義はこんな感じ。
(存在とその一意性を意味します)
写像公理が保証するやつの具体例
「定義域 S=\{1,2,3\} 」『値域 f(S)=\{2,3\} 』
「写像」を『 1↦2,2↦3 』みたいに決めると
\begin{array}{llllll} \displaystyle f&\left\{ \begin{array}{ccc} 1&→&2 \\ \\ 2&→&3 \end{array} \right. \end{array}
「像 f(1) と f(2) 」がそれぞれ1つだけあって
「像の集まり \{f(1),f(2)\} 」は『集合になる』
これが『置換公理』が保証するものになります。
公理を表現する整論理式の意味
この公理で使われている
「整論理式 φ 」についてですが
\begin{array}{ccc} φ(x,y) &\Longleftrightarrow& y=x^2 \end{array}
これは具体的にはこのような「関係」を表すもので
\begin{array}{ccc} f(x) &\Longleftrightarrow& y=x^2 \end{array}
これが直接的に「写像 f 」を定義するものになります。
(関係はなんでも良いわけではなく整論理式に限定される)
補足しておくと
「任意に決めるような整論理式」は
\begin{array}{ccc} φ(x,y) &\Longleftrightarrow& (x=1⇒y=3)∨(x=2⇒y=5) \end{array}
こんな感じになります。
(この形式がかなりの自由度を確保する)
写像と値域の定義を定める
「写像公理」を意味する論理式の
\begin{array}{lcl} \forall X & \Bigl( \mathrm{Image} (X,y) &⇒& \exists Y \,\, \mathrm{Range}(X,Y) \Bigr) \end{array}
「値域 \mathrm{Range} 」の部分は
\begin{array}{ccl} \mathrm{Image}(X,y) & \Longleftrightarrow & \forall x\in X \,\, \exists ! y \,\, φ(x,y) \\ \\ \mathrm{Range}(X,Y) & \Longleftrightarrow & \forall x\in X \,\, \exists y\in Y \,\, φ(x,y) \end{array}
「像の集まりが存在する」ことを直接的に表現してるので
この部分についての疑問は無いと思います。
(値域の定義は像の集まり)
しかし前半部分の
\begin{array}{ccc} \mathrm{Image}(X,y) & \Longleftrightarrow & \forall x\in X \,\, \exists ! y \,\, φ(x,y) \end{array}
これについては
『何を意味しているのか』という点で
少し引っかかる部分があると思います。
結論から行くと
\begin{array}{ccc} 1&\to&2 \\ \\ 2&\to& 2 \\ \\ 3&\to& 4 \end{array}
これは「定義域の要素からは1つの線だけ」という
『写像に求められる性質』を意味していて
(ここで写像が厳密に定義される)
\begin{array}{ccc} \forall x\in X \,\, \exists ! y \,\, φ(x,y) \end{array}
その要請が
「像 y は1つしかない」という表現に繋がっています。
(他の x と像が重複しても1つの x に対応する像は1つ)
和集合公理 \mathrm{Union}
|| ある集合と集合の全部
これは『集合の足し算』を意味する
\begin{array}{ccc} x \in A∪B &\Longleftrightarrow& x\in A ∨ x\in B \end{array}
「和集合」という概念を保証するもので
\begin{array}{llllll} \displaystyle ∀U&\textcolor{skyblue}{∃S_U}&∀e&\Bigl(\,(\textcolor{skyblue}{e∈S_U})⇔\textcolor{skyblue}{∃S_{\mathrm{cnd}}}\,\Bigl(\textcolor{skyblue}{e∈S_{\mathrm{cnd}}}∧S_{\mathrm{cnd}}∈U\Bigr)\,\Bigr) \end{array}
具体的には
\begin{array}{llllll} \displaystyle A&=&\{a,b\} \\ \\ B&=&\{1,2,3,4\} \\ \\ \\ A∪B&=&\{a,b,1,2,3,4\} \end{array}
こんな感じの操作により生成されるものが
「集合である」ことをこの公理は保証します。
具体集合生成公理 \mathrm{Pair}
|| 具体的に中身が分かる集合を作れる操作の保証
これは「中身が分かる集合を生成できる」保証で
\begin{array}{cclcl} \forall a & \forall b & \exists \{a,b\} \\ \\ \forall a & \forall b & \exists S & \forall s \,\, \Bigl( (s\in S) ⇔ (s=a∨s=b) \Bigr) \end{array}
唯一「集合の中身に言及する」公理になります。
(他の公理では集合の中身について言及が無い)
具体的には
\begin{array}{ccccl} a,b &&\to&& \{a,b\} \\ \\ a,a &&\to&& \{a,a\} &=& \{a\} \end{array}
生成できると宣言されている集合はこんな感じで
この公理が「生成された集合の存在」を保証します。
(直接的に対 (a,b) と関係しているわけではありません)
他の公理に不足している部分
「和集合公理」を参考に
単純な形を採用して考えてみると
\begin{array}{ccc} U&=&\{ A,B,C \} \end{array}
「和集合公理」の主張は
\begin{array}{ccc} S_U &=& A∪B∪C \end{array}
こんな感じなんですが
(こんな S_U が存在すると主張している)
ここで出てくる「 A,B,C 」の中身
\begin{array}{ccc} A,B,C && ? \end{array}
これについて
「和集合公理」は何も言及していません。
( U の中身を和集合公理では判別不可能)
同様に
\begin{array}{lcc} 公理 && 役割 && 扱う集合の中身 \\ \\ \\ 外延性 && 同じかどうかの判定 && 不明 \\ \\ 内包性 && 条件で生成できる集合の存在 && 不明 \\ \\ 正則性 && 全ての集合に一番下を要求 && 不明 \\ \\ 無限 && 有限じゃない集合の存在 && 不明 \\ \\ 置換 && 写像と値域の存在 && 不明 \\ \\ 和集合 && 中身を統合した集合の存在 && 不明 \\ \\ 冪集合 && 全ての部分集合を持つ集合の存在 && 不明 \end{array}
他の公理も「集合があればこうなる」と言ってますが
『集合の中身』に言及している公理はありません。
対公理というよりは
つまり「有限集合」なんかを考えた時
\begin{array}{lcc} \{a,b\} \\ \\ \{a,a\} &=& \{a\} \end{array}
このようになる集合は
「和集合公理のみ」では生成できないので
(中身が a,b だと言うためにはこの公理が必須)
\begin{array}{ccc} a,b &&\to&& \{a,b\} \end{array}
こういった
「中身を指定できる集合の存在」を保証するものとして
「対公理(具体集合生成公理)」は存在しています。
間接的には対に関わる
「直積集合」の要素になる「対」に関わらず
\begin{array}{ccc} \mathrm{Axiom} &\to& \left\{ \begin{array}{lcl} a,b &\to& \{a,b\} \\ \\ a,a &\to& \{a,a\} \end{array} \right. \end{array}
この公理は「中身の指定」を行えるので
\begin{array}{ccc} \{a\},\{a,b\} &\to& \Bigl\{ \{a\},\{a,b\} \Bigr\} \end{array}
当然「順序対 (a,b) の生成」という操作も
この公理は保証してくれます。
順序対の表現方法
「対 (a,b) 」を厳密に定義する「順序対」の構成
その形式は ↓ みたいな感じになっていて
\begin{array}{llllll} \displaystyle (a,b)&:=&\Bigl\{ \{a\},\{a,b\} \Bigr\} \end{array}
この定義の場合だと
「順序」は「包含関係 ⊂ 」で定義されており
\begin{array}{ccc} 1&& 2 && 3 \\ \\ \{0\} &⊂& \{0,1\} &⊂&\{0,1,2\} \end{array}
これでどちらが右側にあるのか
直感的に判断できるようになっています。
(この発想は順序数の原型となる自然数の構成に由来する)
冪集合公理 \mathrm{Power \,\, Set}
|| 部分集合を全て集める操作の保証
『要素の選択が全てのパターンで可能』という保証
(ここからラテン語の \mathrm{potentia} 「可能性・力」が来ている)
\begin{array}{llllll} \displaystyle ∀S&\textcolor{skyblue}{∃2^S}& \Bigl(\,∀S_{\mathrm{pt}}\,\Bigl[\,(S_{\mathrm{pt}}⊆S)⇒\textcolor{skyblue}{(S_{\mathrm{pt}}∈2^S)}\,\Bigr] \,\Bigr) \end{array}
集合が『 S=\{1,3,5\} 』こんな感じなら
\begin{array}{llllll} \displaystyle \displaystyle 2^S&=&\Bigl\{ ∅,\{1\},\{3\},\{5\},\{1,3\},\{1,5\},\{3,5\},\{1,3,5\} \Bigr\} \end{array}
これの「冪集合 2^S 」はこのようになります。
( \mathrm{Power} から P(S) と書かれることもあります)
冪の意味と二項定理
「冪( \mathrm{Power} )」の由来は
\begin{array}{ccc} (1+1)^n &=& {}_{n}\mathrm{C}_{0}1^0\cdot 1^{n-0} + {}_{n}\mathrm{C}_{1}1^1\cdot 1^{n-1} + \cdots + {}_{n}\mathrm{C}_{0}1^n\cdot 1^{n-n} \end{array}
「二項定理」の感覚から来ていて
(要素数が n の部分集合の数の総和)
\begin{array}{ccc} \mathrm{Cardinal}\Bigl( P(S) \Bigr) &=& 2^{\mathrm{Cardinal}(S)} \end{array}
「冪集合の要素数」はこのようになることから
\begin{array}{ccc} \mathrm{Power}(S) &=& 2^S \end{array}
要素数がどうなるかを示す意味も込めて
このような表現が生まれました。
\mathrm{Zermelo \,\, Fraenkel} 集合論
ここまでの「公理的集合論」を『 ZF 』と言い
(人名に由来する公理系の名前の省略形)
\begin{array}{ccc} \mathrm{Identity} && S=S \\ \\ \\ \mathrm{Extension} && \forall e \,\, e\in X∧e\in Y ⇒ X=Y \\ \\ \mathrm{Intension} && \exists S_φ \,\, \forall e \,\, e\in S_φ ⇔ e\in S∧φ(e) \\ \\ \\ \mathrm{Foundation} && \exists s\in S \,\, S∩s=∅ \\ \\ \mathrm{Infinity} && e\in S ⇒\mathrm{Suc}(e)\in S \\ \\ \\ \mathrm{Pair} && \exists \{a,b\} \\ \\ \mathrm{Permutation} && \exists f \,\, f(x,y) \\ \\ \\ \mathrm{Union} && \exists X∪Y \,\, \forall e \,\, (e\in X∨e\in Y)⇔e\in X∪Y \\ \\ \mathrm{Power} && \exists 2^S \,\, \forall S_{\mathrm{part}}⊂S \,\, S_{\mathrm{part}}\in 2^S \end{array}
あらゆる公理的集合論の雛型として
この ZF は基礎論でよく出てきます。
( ↑ の論理式は省略形なので厳密さを欠いています)
到達不能基数 \mathrm{Inaccessible\,Cardinal}
|| 基礎が保証される限界
集合の操作で作れる「大きさの限界 κ_{\mathrm{inacs}} 」のこと
(詳細は『到達不能基数』の記事で解説)
\begin{array}{llllll} \displaystyle ∀κ & \textcolor{pink}{∃κ_{\mathrm{inacs}}}&\Bigl(\,\textcolor{pink}{2^{κ}<κ_{\mathrm{inacs}}}\,\Bigr) \end{array}
『極限基数 κ 』は「正則」かつ「非加算」とします。
(この存在は ZF とは独立した公理になります)
感覚としては
\begin{array}{ccc} λ&<&2^λ&<&\cdots&<& 2^{2^{\cdots λ}} &<& \cdots &<& κ_{\mathrm{inacs}} \end{array}
こういう話だと思ってください。
(どんな操作を加えても一致することは無い)
選択公理 \mathrm{Choice}
|| 選ぶという感覚を形式化して保証したもの
いろんな集合から『要素を 1 つ選ぶ』
そして「選んだ要素で集合を作れる」ことを保証する公理
\begin{array}{llllll} \displaystyle &\left( \begin{array}{llllll} \displaystyle &∀G∀S∈G&\Bigl(\,S≠∅\,\Bigr) \\ \\ ∧& ∀G∀S_X∈G∀S_Y∈G&\Bigl(\,(S_X≠S_Y)⇒(S_X∩S_Y=∅)\,\Bigr) \end{array} \right) \\ \\ ⇒&\begin{array}{llllll} \displaystyle ∃S_{\mathrm{choice}}∀S∈G&\Bigl(\,∃!e\,\Bigl(\,e∈(S∩S_{\mathrm{choice}})\,\Bigr)\,\Bigr) \end{array} \end{array}
表現はこんな感じになります。
(これは厳密だけどかなり堅い形)
具体的な感じ
これの主張自体はかなり単純です。
例えば ↓ みたいな集合があるとすると
\begin{array}{llllll} \displaystyle G&=&\{S_A,S_B\} \\ \\ S_A&=&\{1,2,3\} \\ \\ S_B&=&\{m,n\} \end{array}
選択公理が存在を保証する集合として
\begin{array}{llllll} \displaystyle S_{\mathrm{choice}_1}&=&\{2,m\} \\ \\ S_{\mathrm{choice}_2}&=&\{1,n\} \end{array}
このような集合を作れると言ってるだけ。
(有限の場合だとできないわけがない)
厳密な論理式は非常に堅いですが
\begin{array}{llllll} \displaystyle \Bigl\{ \{0\},\{1\},\{2\},\{3\},...,\{n\},... \Bigr\} \end{array}
「無限集合」だとしても
\{0,1,2,3,4,5,...n,...\}
これが可能だというのは直感的に分かると思います。
(可能じゃないというのは直感に反する)
論理式の解説
選択公理の操作自体はすごく単純です。
ただ、形式は少し面倒な感じになっています。
その理由は使うことになる「集合」に制約があるためで
\begin{array}{llllll} \displaystyle ∀G∀S∈G&\Bigl(\,S≠∅\,\Bigr) \end{array}
『集合族(集合が要素の集合) G 』
その「要素(集合) S 」には
「空ではない」ことが
\begin{array}{llllll} \displaystyle ∀G∀S_X∈G∀S_Y∈G&\Bigl(\,(S_X≠S_Y)⇒(S_X∩S_Y=∅)\,\Bigr) \end{array}
『その集合族の中にある集合』には
「互いに素(要素が被らない)」であることが
\begin{array}{ccc} N &\to& \{0,1\} ,\{0,3\} && × \end{array}
それぞれ前提となる条件になっていて
これが論理式を長くしちゃっています。
ただ、その部分を除けば後は単純で
\begin{array}{llllll} \displaystyle ∃S_{\mathrm{choice}}∀S∈G&\Bigl(\,∃!e\,\Bigl(\,e∈(S∩S_{\mathrm{choice}})\,\Bigr)\,\Bigr) \end{array}
『選択』によって創られる集合自体は
そんなに長い論理式にはなりません。
まとめると
「選びたい集合」は『空じゃないし要素が被らない』
その上で『選んだ要素を取り出した集合が存在する』
\begin{array}{llllll} \displaystyle &\left( \begin{array}{llllll} \displaystyle &∀G∀S∈G&\Bigl(\,S≠∅\,\Bigr) \\ \\ ∧& ∀G∀S_X∈G∀S_Y∈G&\Bigl(\,(S_X≠S_Y)⇒(S_X∩S_Y=∅)\,\Bigr) \end{array} \right) \\ \\ ⇒&\begin{array}{llllll} \displaystyle ∃S_{\mathrm{choice}}∀S∈G&\Bigl(\,∃!e\,\Bigl(\,e∈(S∩S_{\mathrm{choice}})\,\Bigr)\,\Bigr) \end{array} \end{array}
この論理式はそんなことを言っています。
使用上の諸注意
これは『直感的に明らか』な操作ですが
実は問題を抱えていて
\begin{array}{llllcll} \displaystyle \mathrm{Card}(G)&≤&ω_0&&〇 \\ \\ \displaystyle \mathrm{Card}(G)&>&ω_0&&? \end{array}
『選ぶ数』が「無限」になる時
より正確には『非加算無限 ω>ω_0 』になる時
\begin{array}{ccc} \mathrm{Choice}(R) &&\to&& 矛盾 \end{array}
矛盾を生む可能性が出てきます。
(詳細は非可測集合などの話を参照してください)
選択公理と選択関数
↑ では集合の存在に重きを置いた話をしましたが
( ↑ は置換公理や対公理なんかを使わなくても良い形)
\begin{array}{lcc} \mathrm{Choice}(S) &=& e_1 \\ \\ \mathrm{Choice}(S\setminus \{e_1\}) &=& e_2 \\ \\ \mathrm{Choice}(S\setminus \{e_1,e_2\}) &=& e_3 \\ \\ &\vdots \\ \\ \mathrm{Choice}(S\setminus \{e_1,e_2,...,e_n\}) &=& e_{n+1} \\ \\ &\vdots \end{array}
この公理の本質は
「選択関数 \mathrm{Choice} 」を厳密に整備することなので
\begin{array}{ccc} \mathrm{Choice} &:& G &\to& \displaystyle \bigcup_{S\in G} S \end{array}
「選択関数の厳密な定義」という形でも
\begin{array}{ccc} \forall G \Bigl( & \Bigl( \forall X\in G \,\, X≠∅ \Bigr) ⇒ \Bigl( \exists \mathrm{Choice} \,\, \forall X\in G \,\, \mathrm{Choice}(X)\in X \Bigr) & \Bigr) \end{array}
この公理を意味する論理式は得ることができます。
(互いに素の条件を省略してますがこれはどちらでもOK)
空集合 \mathrm{Empty\,Set}
|| 枠だけはある中身が空っぽの集合
「要素を持たない『集合』」であるこれは
\begin{array}{llllll} \displaystyle ∃S_{\mathrm{empty}}∀e& \Bigl[ \,e∉S_{\mathrm{empty}} \, \Bigr] \end{array}
『空集合の公理』とされる場合もありますが
\begin{array}{llllll} \displaystyle S_{\mathrm{empty}}&=&\{e∈S \mid e≠e\} \end{array}
だいたい「内包性の公理」によって定義されています。
(公理にしても良いが導けるため位置としては定理)
積集合 Intersection
|| ある集合と集合の共通する部分だけ
『共通部分』だけで作られた「集合」のことで
\begin{array}{llllll} \displaystyle S_{\mathrm{intersection}}&=&\left\{ e \,\middle| \, ∀S_{\mathrm{cnd}}∈U\,\Bigl[\,e∈S_{\mathrm{cnd}}\,\Bigr] \right\} \end{array}
これも「内包性の公理」から導くことができます。
(これは共通部分と呼ばれることが多い)
基本的な操作としての直感的な定義
これは「和集合」と同様
\begin{array}{ccc} e\in X∩Y &\Longleftrightarrow& e\in X∧e\in Y \end{array}
「有限個の集合」を扱う場合はこんな感じで
(和集合は論理和でこちらは論理積)
↑ の定義は
『共通部分をとりたい集合の集まり U 』と
『その中の使う集合 S_{\mathrm{cnd}} 』から
\begin{array}{llllll} \displaystyle ∀S_{\mathrm{cnd}}∈U&\Bigl[ e∈S_{\mathrm{cnd}} \Bigr] \end{array}
「全ての候補 S_{\mathrm{cnd}} が持つ要素」という形で
「より広い範囲」をカバーできる定義になっています。
様々な公理
基礎的な公理的集合論である ZF
\begin{array}{ccc} ZF+C &&\to&& ZFC \end{array}
これに『選択公理 \mathrm{Choice} 』を加えたものが
『 ZFC 』と呼ばれる公理系で
同様に
\begin{array}{ccc} ZFC+GCH \end{array}
これに「一般連続体仮説 GCH 」を加えたものが
『 ZFC+GCH 』と呼ばれる公理系になります。
(基礎論で出てくるこの文字の意味はこれ)
他にも『実数直線』に関するもので
「ススリンの仮説 SH 」なんてものもあり
(これは ZFC とは独立してるが GCH と独立かは不明)
\begin{array}{lcc} ZFC+\mathrm{SH} \\ \\ ZF+\mathrm{Class} &→& NBG \end{array}
他にも ZF をクラス方向に拡張した
NBG なんて名前の公理系も存在します。
ちなみにわたしたちがよく使う「公理系」は
\begin{array}{ccc} 認識できる &&\to&& 存在すると認める \\ \\ 正しくないと変 &&\to && 明らかだと仮定する \end{array}
こんな感じです。
(実際にはもっといろいろあります)
