|| 数学を統一的に説明する方法の1つ
「集合」の性質をまとめた成果
スポンサーリンク
目次
集合「中身が入ってる枠みたいなもの」
要素「集合の中身にあるなにか」
帰属関係「集合と要素の間にある関係の名前」
部分集合「集合の一部を切り取ってできた集合のこと」
写像「集合と集合の間に作れる結びつきのこと」
関数「入力から1つの出力を得る操作」
述語「入力から真か偽を出力するもの」
関係「写像を更に一般化したもの」
定義域「入力の中で出力を持つもの全体」
始域「矢印の手前にある集合のこと」
終域「矢印の先にある集合のこと」
値域「出力の中で入力を持つもの全体」
像「値域あるいは値域の要素のこと」
概念の定義
「集合」という概念の発想は
「概念を説明する方法」から来ていて
\begin{array}{lcl} S&=&\{e_1,e_2,e_3,...,e_n \} \\ \\ \\ あ行&=&\{あ,い,う,え,お\} \\ \\ いくつかの顔文字&=&\{\text{( ゚Д゚),(´Д`),(;゚Д゚)}\} \end{array}
「外延的記法の感覚(列挙型)」
\begin{array}{lcl} S&=&\{ x∈U \mid P(x) \} \\ \\ 集合&=&\{ x \, の範囲 \mid x \, の条件 \} \\ \\ \\ N&=&\{x∈U \mid x ∈N \} \\ \\ N&=&\{x∈\mathrm{Number} \mid x \, \mathrm{is\,Natural\,number} \} \\ \\ N&=&\{ x \, は数 \mid x \,は自然数 \} \end{array}
「内包的記法の感覚(条件型)」
これらをまとめた考え方が「集合」になります。
(定義という概念の整理により集合は生まれた)
集合 Set
|| 概念の名前とその中身を表現するもの
「概念の視覚イメージ」と解釈できる「枠」のこと
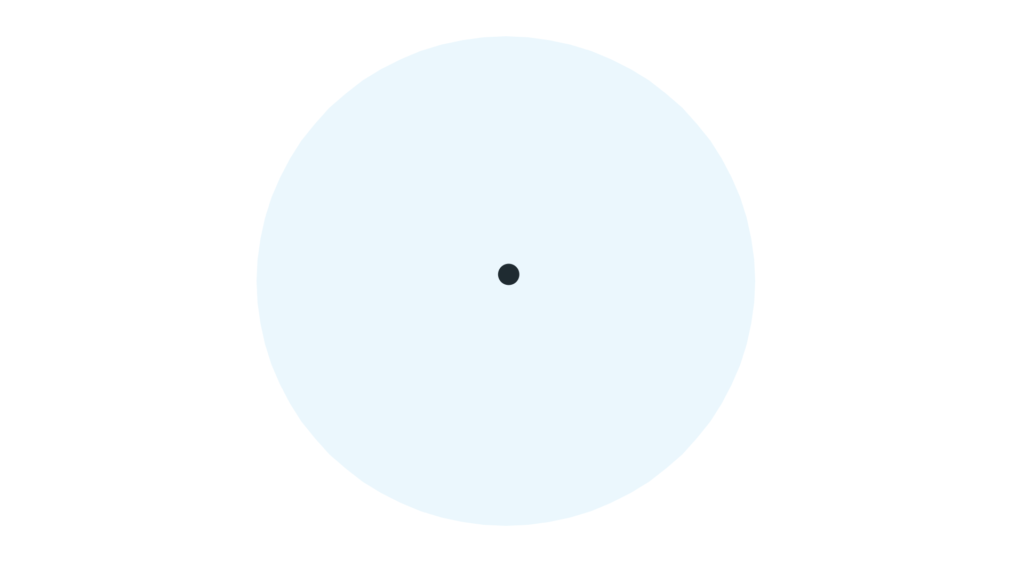
\begin{array}{ccc} 要素 &\in& 集合 \\ \\ \mathrm{Element}&\in&\mathrm{Set} \\ \\ \\ りんご &\in& 果物 \\ \\ 自分 &\in& 存在するもの \end{array}
記号 \in の右側にあるやつが「集合」です。
(集合ではない特殊な例外の時もある)
要素 Element
|| 集合の中身になるもの
「概念を構成する情報」のこと
\begin{array}{ccc} 人間,猿,魚,鳥,... &\in& 動物 \end{array}
記号 \in の左側が「要素」と呼ばれます。
(元という名前もありますが分かり辛いので不採用)
帰属関係 Membership
|| 集合と要素の間にある関係の名前
「集合と要素の関係」のこと
\begin{array}{ccc} 生きてる,水分を持つ,... &\in& 誰か \end{array}
この時の「記号 \in 」の名前です。
(基礎的なので特別な名前が付いています)
集合の中にある集合
補足しておくと
この「帰属関係」は相対的な概念で
(左と右の両方があって初めて定義できる)
\begin{array}{ccc} 要素 &\in & 集合 &\in& 集合 \\ \\ e&\in& A &\in& B \end{array}
このような形の時
「集合 A 」は「集合 B の要素」になります。
(集合を要素に持つ集合は集合族と呼ばれることがある)
部分集合 Subset
|| 集合から一部を切り取ったもの
「とある集合」の『一部』のこと
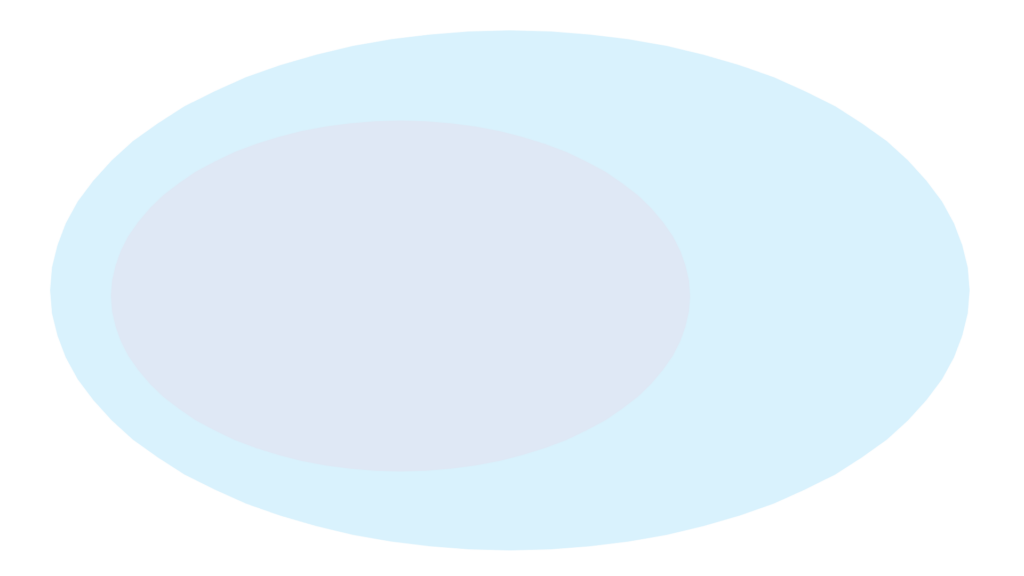
\begin{array}{ccc} s&⊂&S \\ \\ \{a,b\}&⊂&\{a,b,c,d,e\} \\ \\ \{あ,い\}&⊂&\{あ,い,う,え,お\} \\ \\ 身近な動物 &\in& 動物 \end{array}
この「集合 S の要素の一部だけ持つ集合 s 」のことで
この s が「 S の部分集合」になります。
( S の要素以外を持ってる集合は違う)
包含関係 Inclusion
|| 集合とその集合の部分集合の関係の名前
「集合と部分集合の関係」のこと
\begin{array}{ccc} sはSの部分集合 &\Longleftrightarrow& sの要素ならSの要素でもある \\ \\ s \subset S &\Longleftrightarrow&∀x \,\, x∈s ⇒ x∈S \end{array}
厳密にはこういった関係にある時
「 S と s は包含関係にある」と言います。
(だいたい s は S の部分集合と言われる)
帰属関係と包含関係
何かしら「具体的な概念で考える」場合
\begin{array}{ccc} 金属 &\in& もの \\ \\ 金属 &\subset & もの \end{array}
これらは似たようなものに見えてしまいますが
(金属の具体例もまた「もの」の構成情報に含まれる)
\begin{array}{ccc} e\in S &≠& e\subset S \end{array}
実はまったくの別物で
\begin{array}{lcl}\begin{array}{l} S=\{s\} \\ \\ s=\{a\} \end{array} &\longrightarrow& \begin{array}{ccc} s∈S&&〇 \\ \\ s⊂S&&× \end{array} \\ \\ \\ \begin{array}{l} S=\{あ,い,う\} \\ \\ s=\{あ,い\} \end{array} &\longrightarrow & \begin{array}{ccc} s∈S&&× \\ \\ s⊂S&&〇 \end{array} \end{array}
これは概念ではなく記号で考えると
\begin{array}{lcccll} s\in S &&\to&& S=\{s\}&s=\{なんでもいい\} \\ \\ s\subset S &&\to&& S=\{a,b\} & s=\{aかb\} \end{array}
その違いがはっきり分かると思います。
(同じになるよう集合の構造を定義することは可能)
写像 Mapping
|| 関数の挙動を抽象化したもの
「関数」から「入出力」を経て抽象化された概念
\begin{array}{c} && x &\mapsto &f(x) \\ \\ f&:& \mathrm{Input} &→& \mathrm{Output} \\ \\ f&:& \mathrm{Source} &→& \mathrm{Target} \\ \\ f&:& \mathrm{Domain} &→& \mathrm{Image} \end{array}
基本原理は「1入力からの出力」で
「写像」では「出力側」を問いません。
(入力側だけ感覚を維持して出力側は抽象化)
関数 Function
|| 写像の原型となった直感的な概念
「1入力と1出力を相互に定める」『対応』のこと
\begin{array}{ccc} f(x) &=& y \\ \\ x &=& f^{-1}(y) \end{array}
「写像」は『出力結果が同じになる』ことを許容しますが
「関数」では『出力に対応する入力は1つだけ』です。
(複数の入力が同一の出力結果にならない)
述語 Predicate
|| 入力に対して真か偽を返すやつ
『AはBである』みたいな「主張」のこと
\begin{array}{ccccl} aRb && R(a,b) && aとbはRである \\ \\ a=b && =(a,b) &&aとbは同じである \\ \\ a<b && <(a,b) && aはbよりも小である \\ \\ A \in B && \in (A,B) && AはBの要素である \\ \\ A⊂B && ⊂ (A,B) && AはBの部分集合である \end{array}
こういうのが代表的なもので
\begin{array}{ccc} R(a_1,a_2,...,a_n) &\to& \mathrm{True},\mathrm{False} \end{array}
これが「真か偽になる」ことから
\begin{array}{ccc} P &:& X &\to& \{\mathrm{True},\mathrm{False}\} \end{array}
「入力に対して出力がある」ため
「述語」は「写像」の定義を満たすと言えます。
関係 Relation
|| 写像を更に抽象化した概念
これは「写像」と同様の形で
\begin{array}{ccc} 写像 && f &\subset & X\times Y \\ \\ 関係 && R &\subset & X\times Y \end{array}
厳密にはこのように定められているんですが
(直積集合によって定義されている)
\begin{array}{ccc} 写像 && 定義域側からは1本線 \\ \\ 関係 && 特に制限が無い \end{array}
「関係」の定義には特に制限がありません。
(つまり写像と関係は f\subset R )
なので「写像」では許されないような
\begin{array}{ccc} 1は自然数である →真 &&\Longleftrightarrow&& (1,真) \\ \\ 1は自然数である →偽 &&\Longleftrightarrow&& (1,偽) \end{array}
こういうものを「両方含む」状態が
「関係」の範囲では許されています。
(写像だと 1 からはどちらかにしかならない)
定義域 Domain
|| 入力側を意味する集合
「出力を持つ要素だけ」を集めたもの
\begin{array}{ccc} f &:& X&\to& Y \\ \\ && 定義域 && f(x)の集まり \end{array}
「写像 f の左側 X 」のことで
\begin{array}{ccc} \mathrm{Domain}(f) &=& \{ x\in X \mid \exists y \in Y \,\, (x,y)\in f \} \end{array}
「定義域 \mathrm{Domain}(f) 内の要素 x 」には
「出力 f(x)=y を必ず持つ」ことが要求されています。
終域 Codomain
|| 出力先を大まかに指定するためのもの
「出力側」を大まかに意味する概念
\begin{array}{ccc} f &:& X&\to& Y \\ \\ && 定義域 & & 終域 \end{array}
「出力結果を全て含むもの Y 」のことですが
「出力結果のみ」を意味しているわけではありません。
(出力結果のみを意味することもある)
始域 Source
|| 終域に対応する定義域側の概念
「定義域」を抽象化した集合のこと
\begin{array}{ccc} f &:& X&\to& Y \\ \\ && 始域 & & 終域 \end{array}
こちらは「定義域」の意味で使われることもあれば
「定義域を含む集合」の意味で使われることもあります。
(呼び方の分かり易さや定義の柔軟性に優れる)
値域 Range
|| 出力結果を全てまとめたもの
「定義域からの出力結果だけをまとめた集合」のこと
\begin{array}{ccc} \mathrm{Range}(f) &=& \{ y\in Y \mid \exists x\in X \,\, (x,y)\in f \} \end{array}
「定義域」に対応する「出力側」の概念です。
(終域の中身を出力のみに制限したもの)
像 Image
|| 出力結果を意味する抽象的な概念
「値域の要素」か「値域」を意味する概念
\begin{array}{ccc} f &:& X&\to& Y \\ \\ && x&\mapsto & y \end{array}
「写像 f 」における『出力側 y,Y 』のこと
\begin{array}{lcl} 像 & 要素 && f(x) \\ \\ 像 & 集合 && \{ y\in Y \mid \exists x\in X \,\, (x,y)\in f \} \end{array}
「終域」とは完全に別物の概念で
「出力結果」を大まかに意味する用語になります。
(終域が値域と一致する場合は結果的に終域を意味する)
各領域の比較
整理すると
\begin{array}{lll} 始域 &\mathrm{Source}& 出発する大まかな場所 \\ \\ 定義域 &\mathrm{Domain}& 実際に出発したやつら \\ \\ \\ 値域 &\mathrm{Range}& 実際に到着したやつら \\ \\ 終域 &\mathrm{coDomain}& 大まかな目的地 \end{array}
これらはこんな感じのもので
\begin{array}{ccc} \mathrm{Domain} &\subset & \mathrm{Source} \\ \\ \mathrm{Range} &\subset& \mathrm{coDomain} \end{array}
その関係はこんな感じになっています。
(全体を指したりで一致することはよくある)
また「像」については
\begin{array}{lcl} \mathrm{Image}_{\mathrm{Element}} &\in & \mathrm{Range} \\ \\ \mathrm{Image}_{\mathrm{Set}} &=& \mathrm{Range} \\ \\ \\ \mathrm{Image}_{\mathrm{Element}} &\in & \mathrm{coDomain} \\ \\ \mathrm{Image}_{\mathrm{Set}} &≠& \mathrm{coDomain} &≠& \mathrm{Range} \\ \\ \mathrm{Image}_{\mathrm{Set}} &=& \mathrm{coDomain} &=& \mathrm{Range} \end{array}
こんな感じになっています。
(基本的には終域と像は別物)
