|| 自然数の集合には最小の値が含まれる
「最小元の存在」を保証する公理
スポンサーリンク
目次
ペアノの公理「自然数の構成を一般化した公理系」
加法「数のペアからその和を出力する関数(写像)」
大小関係「加法によって定義される順序を決める二項関係」
順序集合「大小比較なんかが可能であることを保証する土台」
整列集合「最小元を保証する整列原理の土台」
最小元原理「自然数の集合には最小元が必ず存在する」
最大限の存在定理「最大元が存在する条件の確認」
ペアノの公理
これは「自然数の構成」を一般化した概念で
\begin{array}{rcr} && 0 \in N \\ \\ 0 \in N &\to& 0+1 \in N \\ \\ 1 \in N &\to& 1+1 \in N \\ \\ &\vdots \end{array}
「自然数の存在」の保証や
\begin{array}{ccc} P (0) ∧ \Bigl( \forall n \,\, P (n) ⇒ P (n+1) \Bigr) & ⇒ & \forall n \,\, P (n) \\ \\ P(1) ∧ \Bigl( \forall n \,\, P(n) ⇒ P(n+1) \Bigr) & ⇒ & \forall n \,\, P(n) \end{array}
「数学的帰納法」の原理になっています。
ペアノの公理と論理式
これを構成する命題は
\begin{array}{lr} \exists 0 \,\mathrm{or}\, 1 & 0 \,\mathrm{or}\, 1 \in N && 初期値 \\ \\ \forall n & n\in N ⇒ \mathrm{Suc}(n) \in N && 後者 \end{array}
「後者関数 \mathrm{Suc} 」により定義されていて
(自然数の後者関数は \mathrm{Suc}(n)=n+1 になる)
\begin{array}{ll} \forall n & n\in N ⇒ \mathrm{Suc}(n) ≠ 0 \\ \\ & 0は後者じゃない \\ \\ \forall n \forall m & \Bigl( n,m\in N ∧ \mathrm{Suc}(n)=\mathrm{Suc}(m) \Bigr) ⇒ n=m \\ \\ & 違う値なら後者も違う \end{array}
最後の ↓ が
\begin{array}{ccc} \forall P & \Bigl( & \Bigl( P(0) ∧ \Bigl( \forall n \,\, P(n)⇒P(\mathrm{Suc}(n)) \Bigr) \Bigr) &⇒& \forall n \,\, P(n) & \Bigr) \end{array}
「数学的帰納法」の原理になります。
( \mathrm{Suc}(n)=n+1 が基本的な数学的帰納法の形式)
後者関数の定義
これは「加法 + 」を使うと
\begin{array}{ccc} \mathrm{Suc}(n) &=& n+1 \end{array}
簡単に定義できるんですが
厳密には
\begin{array}{ccc} \mathrm{Suc} &&\to&& + \end{array}
これ自体が「加法」を定義するので
「加法」によって定義されてるわけではありません。
これが定義するのは「次の数」であり
\begin{array}{ccl} 0 &=& × \\ \\ 1&=&\mathrm{Suc}(0) \\ \\ 2&=&\mathrm{Suc}(1) \\ \\ 3&=&\mathrm{Suc}(2) \\ \\ & \vdots \end{array}
その「次の数のラベル」なので
「和」と直接的な関係は無いです。
(結果的に + を意味するだけ)
加法 +
これは厳密には
「関数(写像)」として定義されていて
\begin{array}{ccc} + &:& N\times N &\to & N \\ \\ & & (n,m) & ↦ & n+m \end{array}
このような形で整備されています。
(写像の実体は対の集合として定義される)
より厳密には
ここで使われている n+m はまだ使えず
( ↑ の時点では循環定義になっている)
\begin{array}{ll} \forall n\in N & f_n(0)=n \\ \\ \forall n,m\in N & f_n \Bigl( \mathrm{Suc}(m) \Bigr) = \mathrm{Suc} \Bigl( f_n(m) \Bigr) \end{array}
「命題 P(m) 」を
「 n,m の和は f_n(m) である」とする場合の
\begin{array}{ccc} \Bigl( P(0) ∧ \Bigl( \forall m \,\, P(m)⇒P(\mathrm{Suc}(m)) \Bigr) \Bigr) &⇒& \forall m \,\, P(m) \end{array}
「数学的帰納法」によって保証されるので
(この定義での n は動かさなくて良いので最初に固定)
\begin{array}{ccc} f_n(m) &&\to&& n+m \end{array}
定義の段階では
「加法 + 」を使ってはいけません。
(この加法の定義はペアノの公理の一部)
写像の構成
ここでは深く掘り下げませんが
これは実体としては
\begin{array}{ccc} f &=& \{ (x,y) \mid x\in X ∧ y\in Y \} \end{array}
この2つの公理により存在が保証されていて
\begin{array}{ccc} f &:& X& \to& Y \\ \\ && x & ↦ & y \end{array}
「像」に当たる「 x と y=f(x) の対応」は
「置換公理」によって保証されています。
(置換公理により像は一意に定まると保証される)
定義の順序
ちょっとややこしいですが
「加法」の定義の出発点は
\begin{array}{ccc} P_n(m) && \equiv && n,m \, の和は \, n+m \, である \end{array}
「非形式」の宣言と感覚的なイメージです。
(これは命題になる前の段階)
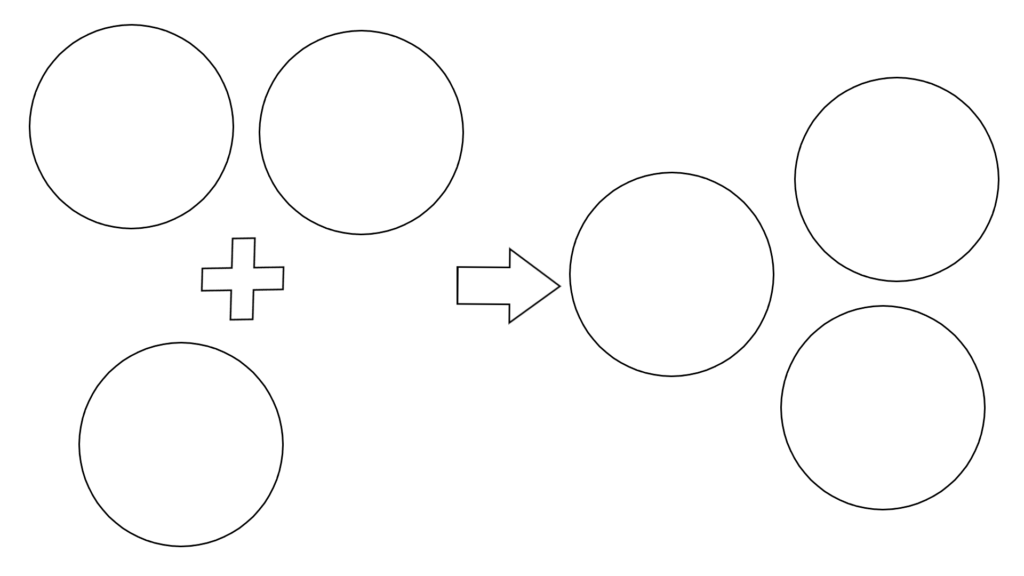
ここから
\begin{array}{ccc} f_n &:& N\times N &\to & N \\ \\ & & (n,m) & ↦ & f_n(m) \end{array}
「関数(写像)」による厳密な定義が与えられて
(この段階でのこれは加法に対する要望)
\begin{array}{ll} \forall n\in N & f_n(0)=n \\ \\ \forall n,m\in N & f_n \Bigl( \mathrm{Suc}(m) \Bigr) = \mathrm{Suc} \Bigl( f_n(m) \Bigr) \end{array}
このような振る舞いをするという形で
(後者を入れ込むことで + の振る舞いを実現)
\begin{array}{ccc} n+m &=& n+m \\ \\ n+\mathrm{Suc}(m) & = & \mathrm{Suc} ( n+m ) \\ \\ f_n \Bigl( \mathrm{Suc}(m) \Bigr) & = & \mathrm{Suc} \Bigl( f_n(m) \Bigr) \end{array}
これは厳密に定義されています。
大小関係 Size
我々がよく使うこの関係は
\begin{array}{ccc} + && \to&& ≤ \end{array}
厳密には「加法」により定義されていて
\begin{array}{ccc} \forall n,m\in N & n≤m &\Longleftrightarrow& \exists k\in N \,\, n+k=m \end{array}
これを意味する論理式はこのようになっています。
(右の論理式が大小関係の記号を定義する)
少し込み入ってますが
\begin{array}{ccc} A & B && A\Leftrightarrow B \\ \\ \mathrm{True} & \mathrm{True} && \mathrm{True} \\ \\ \mathrm{False} & \mathrm{False} && \mathrm{True} \end{array}
「量化子」の内側ではこうなるので
この主張はきちんと「全ての n,m 」で成立します。
(どちらかが外だと 1≤0 などで偽になってしまう)
順序の公理と全順序関係
「全順序関係」についての詳細は省きますが
(完全律を満たす順序関係)
\begin{array}{lcll} 反射律 &:& \forall n\in N & n≤n \\ \\ 反対称律 &:& \forall n,m\in N & n≤m∧m≤n \,\, ⇒ \,\, n=m \\ \\ 推移律 &:& \forall n,m,k\in N &n≤m∧m≤k \,\, ⇒ \,\, n≤k \\ \\ 完全律 &:& \forall n,m\in N &n≤m∨m≤k \end{array}
この「大小関係 ≤ 」は
「全順序関係」の条件を全て満たします。
(順番的には大小比較から全順序が発想される)
大小関係と反射律
これは「 0 の存在」により
\begin{array}{lcl} n≤m &\Longleftrightarrow& \exists k\in N \,\, n+k=m \\ \\ n≤n &\Longleftrightarrow& \exists 0 \in N \,\, n+0=n \end{array}
「任意の n で成立する」ことは
「大小比較の定義 \forall n 」からすぐに示せます。
( n≤n を保証できる k=0 が存在するため)
大小関係と反対称律
これを証明するためには
\begin{array}{ccc} (n+m)+k = n+(m+k) \\ \\ n+k=m+k \,\, ⇒ \,\, n=m \end{array}
「結合法則」と「簡約律」が必要になります。
(加法の基本性質については別記事で)
というのも
\begin{array}{ccc} \forall n,m\in N & n≤m∧m≤n \,\, ⇒ \,\, n=m \end{array}
この着地から見えてくる事実は
\begin{array}{ccc} n≤m & \Leftrightarrow& n+k_1=m \\ \\ m≤n & \Leftrightarrow& m+k_2=n \end{array}
これだけです。
ここから代入する形で
\begin{array}{rcc} m+k_1 &= &n \\ \\ (n+k_2)+k_1 & = &n \end{array}
これが得られるわけですが
\begin{array}{ccc} (n+k_2)+k_1 & = &n \\ \\ n+(k_2+k_1) & = &n \end{array}
ここからこれを得るためには
「結合法則が成立する」ことが必須
\begin{array}{ccc} n+(k_2+k_1) & = &n +0 \end{array}
またここから導かれるこれを使って
(変形で使う n+0=n は定義)
\begin{array}{ccc} k_2+k_1 & = & 0 \end{array}
これを得るためには
\begin{array}{ccc} n+k=m+k & ⇒ & n=m \\ \\ k+n=k+m & ⇒ & n=m \\ \\ n+k=n+0 & ⇒ & k=0 \end{array}
「簡約律」が必須になります。
(厳密にはここで交換法則が使われてる)
そして以上の操作を認める場合
\begin{array}{ccc} k_1+k_2=0 &&⇒&& k_1=0∧k_2=0 \end{array}
こうなるので
\begin{array}{ccc} n≤m & \Leftrightarrow& n+k_1=m \\ \\ m≤n & \Leftrightarrow& m+k_2=n \end{array}
この前提から
\begin{array}{lcl} n+0 &=& m+0 \\ \\ n &=& m \end{array}
この結論を得ることができます。
(この手順は証明でよく見られる)
自然数の和 n+m が 0 なら n,m は 0
自然数は 0 以上であるため
↓ は直感的に明らかですが
\begin{array}{ccc} k_1+k_2 &=& 0 \\ \\ 0+0 &=& 0 \end{array}
これは論理的には明らかじゃないので
きちんと証明する必要があります。
やることは単純
「加法の定義」より
\begin{array}{ccc} +(n,0) &=& n \\ \\ +(0,0) &=& 0 \end{array}
まず m=0 で考えるなら
\begin{array}{ccc} n+m=0 &\Leftrightarrow& n=0 ∧ m=0 \end{array}
これは定義より明らかですから
( n が 0 になるのは当然 n=0 の時だけ)
後は直感的な結論を考えて
残りの m≠0 となるパターンを考えると
\begin{array}{ccc} m &=& \mathrm{Suc} (k) \end{array}
この仮定から矛盾が導出できるため
( 0 ではない以上なんらかの後者であるはず)
\begin{array}{lcc} n+m &=& 0 \\ \\ n+\mathrm{Suc}(k) &=& \mathrm{Suc}(n+k) \end{array}
m≠0 が間違いであると分かり
( 0 は後者じゃないという公理により否定される)
\begin{array}{ccc} m&=&0 \end{array}
m=0 でなければならない
この結論から間接的に n=0 もまた得られます。
大小比較と推移律
これは大変そうに見えて
\begin{array}{ccc} \forall n,m,k\in N &n≤m∧m≤k \,\, ⇒ \,\, n≤k \end{array}
意外と単純な形で証明できます。
というのも
\begin{array}{ccc} n≤m & \Leftrightarrow& n+j_1=m \\ \\ m≤k & \Leftrightarrow& m+j_2=k \end{array}
前提から得られるこの結果は
\begin{array}{rcc} m+j_2 &=& k \\ \\ (n+j_1)+j_2 &=& k \\ \\ n + ( j_1+j_2 ) &=& k \end{array}
そのままこれを意味するので
\begin{array}{ccc} j_1+j_2 &=& j \end{array}
後は「加法の閉鎖性」を考えれば
(自然数の足し算結果は自然数)
\begin{array}{ccc} n≤k & \Leftrightarrow& n+j=k \end{array}
そのままこの結論を得ることができます。
大小関係と完全律
これの証明はちょっと大変です。
\begin{array}{ccc} \forall n,m\in N & n≤m∨m≤k \end{array}
というのも
これの意味は「必ず比較ができる」なので
\begin{array}{ccc} P_n(m) & \Leftrightarrow & n≤m∨m≤n \end{array}
全てのパターンを網羅しなければなりません。
(適切な場合分けをする必要がある)
m=0 の場合
まず単純な形を考えるために
\begin{array}{lcl} n≤m &∨& n≥m \\ \\ n≤0 &∨& n≥0 \end{array}
この形で考えてみると
\begin{array}{ccc} n≤m &\Longleftrightarrow& \exists k\in N \,\, n+k=m \end{array}
「大小関係の定義」より
\begin{array}{ccc} n≤0 &\Longleftrightarrow& \exists k\in N \,\, n+k=0 \end{array}
まずこの形であれば
自然数 k=0 が存在するのは明らかなので
\begin{array}{ccc} n≤0 &\Longleftrightarrow& \exists 0\in N \,\, n+0=0 \end{array}
このパターンは確実に成立
(これを詳細に説明する補助命題の証明は別記事)
\begin{array}{ccc} 0≤n &\Longleftrightarrow& \exists k\in N \,\, 0+k=n \end{array}
またこちらに関しては
\begin{array}{ccc} \forall n\in N & +(n,0) = n \end{array}
n がドメイン N に含まれることから
(前提として n は最初に固定される)
\begin{array}{ccc} 0≤n &\Longleftrightarrow& \exists n\in N \,\, 0+n=n \end{array}
明らかに成立すると言えます。
(加法の定義と加法の交換法則も使ってる)
整理すると
\begin{array}{ccc} n=0 &\Longleftrightarrow& n≤0 ∨ 0≤n \end{array}
このパターンでは常にこれが成立し
\begin{array}{ccc} 0<n &\Longleftrightarrow& 0≤n \end{array}
このパターンでは
常にこうなるということが分かりました。
(命題の成立自体は 0≤n の部分だけで十分)
m を動かす場合
本題であるこちらの方は
「命題 P_n(m) 」を元にして
\begin{array}{ccc} P_n(m) & \Leftrightarrow & n≤m∨m≤n \end{array}
\mathrm{Suc}(m) の場合を確認し
「数学的帰納法」の要件を満たすことで
\begin{array}{lcl} n≤m &∨& n≥m \\ \\ n≤\mathrm{Suc}(m) &∨& n≥\mathrm{Suc}(m) \end{array}
成立することを確認する必要があります。
具体的には
「数学的帰納法」の手順より
\begin{array}{ccc} P_n(m) & \Leftrightarrow & n≤m∨m≤n \end{array}
まずこれを正しいと「仮定」する必要があって
(この仮定は直感的に明らかな仮定)
\begin{array}{ccc} n≤m &∨& m≤n \end{array}
その仮定から
このどちらかは正しいということになるので
\begin{array}{ccc} n &≤& m \\ \\ && m &≤& n \end{array}
それを前提として
話を進めていく必要があります。
n≤m の場合
まず直感的に明らかである
\begin{array}{ccc} n &≤ &m \end{array}
こちらの方を確認してみると
\begin{array}{lcl} n+k&=&m \\ \\ n+k+1&=&m+1 \end{array}
こんな風に考えれば
\begin{array}{lcl} n+\mathrm{Suc}(k) &=& \mathrm{Suc}(n+k) \\ \\ n+\mathrm{Suc}(k) &=& \mathrm{Suc}(m) \end{array}
「加法の定義」と「後者の存在」により
\begin{array}{ccc} n≤\mathrm{Suc}(m) &\Longleftrightarrow& \exists \mathrm{Suc}(k)\in N \,\, n+\mathrm{Suc(k)}=\mathrm{Suc}(m) \end{array}
これがこうなることはすぐに導くことができます。
(この時点だと「全ての m で」とはまだ言えない)
m≤n の場合
問題はこっちで
\begin{array}{lcc} 1 &≤& 1 \\ \\ 1+1 &≥& 1 \end{array}
例えばこういうパターンを考えると
↑ のように単純な結論を得ることはできませんから
\begin{array}{lcl} n+\mathrm{Suc}(0)&=& \mathrm{Suc}(n+0) \\ \\ n+\mathrm{Suc}(1)&=& \mathrm{Suc}(n+1) \end{array}
こんな形を想定しながら
それぞれ場合分けして考える必要があります。
k=0 の時
確認しておくと
\begin{array}{ccc} m≤n &\Longleftrightarrow& \exists k\in N \,\, m+k=n \end{array}
このパターンでは
\begin{array}{ccc} m≤n &\Longleftrightarrow& \exists 0\in N \,\, m+0=n \end{array}
こうなりますから
「直感的に正しい仮定」の下では
\begin{array}{lcl} m+0 &=& n \\ \\ m &=& n \end{array}
これはこうなると言えます。
ここから
「数学的帰納法」の要件を満たすために
\begin{array}{ccc} \mathrm{Suc}(m) &=& \mathrm{Suc}(n) \\ \\ &{}& \mathrm{Suc}(n) &≥& n \end{array}
これを確認してみると
( \mathrm{Suc}(m) と n の大小比較をとりたい)
結果として
\begin{array}{ccc} n≤\mathrm{Suc}(m) &\Longleftrightarrow& \exists \mathrm{Suc}(0) \in N \,\, n+\mathrm{Suc(0)}=\mathrm{Suc}(m) \end{array}
このような結論を得ることができるので
このパターンでも命題 P_n(m) は正しくなります。
( m≤n という仮定から命題 P_n(m) を導ける)
k≠0 の時
これは少し複雑で
k≠0 であることから
\begin{array}{ccl} 1&=&\mathrm{Suc}(0) \\ \\ k &=& \mathrm{Suc}(k_{-1}) \end{array}
「 k はなんらかの後者」だと言える
この事実を使う必要があります。
( k_{-1} は k^{\prime} と置く方が適切)
というのも
\begin{array}{ccc} m≤n &\Longleftrightarrow& \exists k\in N \,\, m+k=n \end{array}
ここから
(直感的に正しい仮定)
\begin{array}{ccc} \mathrm{Suc}(m) + ? &=& n \end{array}
この形を目指したいんですが
ここに必要な ? は明らかに k-1 です。
(厳密にはこの時点で - は定義されてない)
なのでここに行き着くには
\begin{array}{ccc} k &=& \mathrm{Suc}(k_{-1}) \end{array}
この「 k_{-1} の存在」を保証しておく必要があって
(後者の公理より 0 以外はなんらかの値の後者)
これが無い場合
↓ の式変形ができなくなります。
\begin{array}{lcl} m+k&=&n \\ \\ m+\mathrm{Suc}(k_{-1}) &=& n \\ \\ \mathrm{Suc}(m+k_{-1}) &=& n \end{array}
逆を言えば
ここまで分かっているなら
後は着地を目指していくだけで
\begin{array}{lcl} \mathrm{Suc}(m+k_{-1}) &=& n \\ \\ \mathrm{Suc}(m)+k_{-1} &=& n \end{array}
命題 P_n(m) は証明することができます。
(ここの変形では交換法則か補助命題を用いる)
P_n(m) は全ての m で成立する
まとめると
\begin{array}{ccc} n≤m & & \exists k \\ \\ m≤n & \left\{ \begin{array}{ccc} k=0 \\ \\ k≠0 \end{array} \right. & \exists k \end{array}
この全てのパターンで
「数学的帰納法」が成立すると言えることから
「全ての m 」で
\begin{array}{ccc} P_n(m) & \Leftrightarrow & n≤m∨m≤n \end{array}
これは成立すると言えます。
(任意の n は最初に固定されてる)
順序集合 Order
「大小」に限らず「比較」ができ
それにより「順序」を定義することができる
\begin{array}{lcll} 反射律 &:& \forall n\in N & n≤n \\ \\ 反対称律 &:& \forall n,m\in N & n≤m∧m≤n \,\, ⇒ \,\, n=m \\ \\ 推移律 &:& \forall n,m,k\in N &n≤m∧m≤k \,\, ⇒ \,\, n≤k \end{array}
これを意味する最小単位として
これは「集合 S 上の関係 R 」という形で
\begin{array}{ccc} (S,R) \,\, \mathrm{is} \,\, \mathrm{Ordered \,\, Set} \end{array}
このように定義されています。
( S 上の R は完全律以外の3つを確実に満たす)
全順序集合 Total Order
この「順序集合」の中でも
\begin{array}{lcll} 反射律 &:& \forall n\in N & n≤n \\ \\ 反対称律 &:& \forall n,m\in N & n≤m∧m≤n \,\, ⇒ \,\, n=m \\ \\ 推移律 &:& \forall n,m,k\in N &n≤m∧m≤k \,\, ⇒ \,\, n≤k \\ \\ 完全律 &:& \forall n,m\in N &n≤m∨m≤k \end{array}
特に「完全律(全順序律)」を満たすものは
「全順序集合」と呼ばれ
この記事の主題である
「自然数 N 上の大小関係 ≤ 」は
\begin{array}{ccc} (N,≤) \,\, \mathrm{is} \,\, \mathrm{Totally} \,\, \mathrm{Ordered \,\, Set} \end{array}
この「全順序集合」にあたります。
(実数上の大小関係も全順序集合)
整列集合 Well-Order
そしてこの「全順序集合」の中でも
\begin{array}{ccc} \exists \min( N_* ) & (N_* ⊂N) ∧ (N_*≠∅) \end{array}
特に「最小元原理」を満たすものは
「整列集合」と呼ばれ
「全順序集合」と同様
\begin{array}{ccc} (N,≤) \,\, \mathrm{is} \,\, \mathrm{Well}\text{-}\mathrm{Ordered \,\, Set} \end{array}
「自然数上の大小関係」は
「整列集合」の条件を満たします。
(以降の話は全順序集合上の話であるとします)
最小元原理
これは「公理」とされることもある主張で
(初期値なんかの最小値の存在を保証する役割を持つ)
\begin{array}{ccc} \exists \min( N_* ) & (N_* ⊂N) ∧ (N_*≠∅) \end{array}
「自然数の部分集合(空ではない)」の中に
「最小の値が叶ず存在する」
これを保証してくれます。
ペアノの公理からの証明
「公理」として考えるのなら
これの証明は必要ありませんが
\begin{array}{ccc} 0 \in N && \to && 0 \in N_* & ? \end{array}
「ペアノの公理」を基盤とする場合
これは「定理」として導かれる結論になります。
最小元を持つはず
「空集合ではない」
「自然数の部分集合 N_* 」を考えて
\begin{array}{ccc} N_* ⊂N & ∧ & N_*≠∅ \end{array}
これの「最小の元」を考えるために
\begin{array}{ccc} n_{\mathrm{min}} &\not\in& N_* \end{array}
とりあえず
「最小元を持たない」と仮定してみます。
(直感的には持つはずなので背理法を採用)
最小の元を持たないとは
しかしここで問題になるのが
「最小の元」を意味する N_* の要素を
\begin{array}{ccc} \min(N_*) &=& ? \end{array}
どのように表現したら良いかって話で
(この時点では最小の元という概念は外付け)
\begin{array}{ccc} ? &&\to&& \min(N_*) \end{array}
このままだと
「最小である」ことをうまく表現できません。
(そのまま最小を使うと循環定義になる)
ここから話を進めるためには
\begin{array}{ccc} P(n) &&←&& n \, は \, N_* \,の中で最小 \end{array}
「最小である」を意味する命題を
「帰納的に定義する」必要があります。
(ペアノの公理の数学的帰納法が使えそうなので)
最小を意味するだろう命題
ぱっと思いつくものとして
\begin{array}{ccc} 0 &\in& N_* && ? \\ \\ 1 &\in& N_* && ? \\ \\ & \vdots \end{array}
「初期値」と「後者」の発想から
このような確認方法を考えることができるわけですが
(自然数全体の最小から順に帰属を確認していく)
これをうまく「命題」に落とし込むためには
\begin{array}{lcl} P(0) &\equiv& 0 \in N_* \\ \\ P(1) &\equiv& 1 \in N_* ∧ 0 \not\in N_* \\ \\ P(2) &\equiv& 2 \in N_* ∧ 1 \not\in N_* ∧ 0 \not\in N_* \\ \\ &\vdots \\ \\ P(n) &\equiv& n \in N_* ∧ n-1 \not\in N_* ∧ \cdots ∧ 1 \not\in N_* ∧ 0 \not\in N_* \end{array}
ちょっとした工夫が必要になります。
(これの自然な表現は「 n より下の要素を持たない」とか)
というのも
\begin{array}{ccc} P(n) &\equiv& n \in N_* ∧ n-1 \not\in N_* ∧ \cdots ∧ 1 \not\in N_* ∧ 0 \not\in N_* \end{array}
このままでは
n\in N_* が強制されてしまうので
\begin{array}{ccc} P(0) &=& \mathrm{True} \,\, \mathrm{or} \,\, \mathrm{False} \end{array}
仮定の下では命題 P が真になってくれません。
(最小を持たないという仮定に合わせるなら不都合)
なので
より柔軟な形で命題として落とし込むなら
\begin{array}{ccc} P(n) &\equiv& n-1 \not\in N_* ∧ \cdots ∧ 1 \not\in N_* ∧ 0 \not\in N_* \end{array}
「 n\in N_* 」これを取り除いて
「持たない」という形の命題にする必要があります。
(これで N_* の中身に直接的には関係無い命題になる)
下から確認していく命題と間違ってるだろう仮定
まず最初に確認しておくと
↑ で良い感じに定めたように
\begin{array}{ccc} P(0) &=& \mathrm{True} \end{array}
「初期値より下の値は存在しない」ことから
この命題は「常に真」になります。
( N_* が 0 を持ってなくても)
そしてそういうことであれば
「最小の元を持たない」と仮定する場合
\begin{array}{ccc} P(0) &&\to&& 0 \in N_* && ? \end{array}
「 0\in N_* 」とすると
「最小の元 0 を持つ」ことになってしまうため
\begin{array}{ccc} 0 & \not\in & N_* \end{array}
これは必ずこのようになります。
(つまり最小元を持たない部分集合はこうなる)
そして同様に
\begin{array}{ccc} P(1) &&\to&& 0,1\not\in N_* \end{array}
このようになることを考えると
( 1 が最小の元になるため)
\begin{array}{ccc} P(n) &\equiv& n-1 \not\in N_* ∧ \cdots ∧ 1 \not\in N_* ∧ 0 \not\in N_* \end{array}
一般形であるこの形からもまた
「 n が最小元になる」ことより
\begin{array}{ccc} P(n) &&\to&& 0,1,2,...,n-1,n \not\in N_* \end{array}
同様の手順でこうなると考えられます。
(帰納法で最初に必要な予想手順)
数学的帰納法の適用
数学的帰納法の手順を経るために
\begin{array}{ccc} P(n) &&\to&& 0,1,2,...,n-1,\textcolor{pink}{n} \not\in N_* \end{array}
こうなると仮定してみると
(最小元を持たない自然数の集合はこうなる)
\begin{array}{ccc} P(n+1) &\equiv& n \not\in N_* ∧n-1 \not\in N_* ∧ \cdots ∧ 0 \not\in N_* \end{array}
これは「自然数の後者 n+1 」を利用すれば
このようになるということなので
「最小の元を持たない自然数の集合」は
\begin{array}{ccc} n+1 \in N_* && ? \end{array}
このようになり得るんですが
命題 P(n+1) が真である以上
\begin{array}{ccc} n+1 & \not\in & N_* \end{array}
この要素が「最小の元」となるので
これは「最小元を持たない集合」の要素にはなり得ません。
( 0 から n を除けば n+1 が最小)
以上より
「数学的帰納法」の要件が満たされたと言えることから
( P(n) を正しいと仮定したら P(n+1) が成立)
\begin{array}{ccc} P(n) &\equiv& n-1 \not\in N_* ∧ \cdots ∧ 0 \not\in N_* \end{array}
「最小元を持たない自然数の集合 N_* 」では
「全ての n 」で P が成立するので
「全ての n を持たない」
\begin{array}{ccc} N_* &=& ∅ \end{array}
この条件を満たす「空集合」のみが
「最小元を持たない自然数の集合」になり得ます。
(空集合は全ての集合の部分集合)
最小元を持たない自然数の集合と空集合
まとめると
「空集合ではない自然数の集合」の中で
\begin{array}{ccc} P(n) &\equiv& n-1 \not\in N_* ∧ \cdots ∧ 0 \not\in N_* \end{array}
「最小元を持たない部分集合」は存在しないので
(初期値とその後者を全て要素に持たないため)
\begin{array}{ccc} N_* ⊂N & ∧ & N_*≠∅ \end{array}
「空集合ではない自然数の部分集合」は
「全て最小元を持つ」と言えます。
上界の最小元
以上のことが正しいと言えることから
\begin{array}{ccc} U &=& \{ m \in N \mid \forall n\in N_* \,\, n≤m \} \end{array}
「自然数の集合(空集合ではない)」において
「上界 U の最小元 M の存在」は確実に保証されるため
\begin{array}{ccc} N_{\mathrm{bounded}} &⊂& N \end{array}
「有界な自然数の部分集合 N_{\mathrm{bounded}} 」を考えた時
「上限 M の存在」はすぐに保証されることになります。
(上界を定義すると自動的に最小元の存在も保証される)
有界な自然数における最大元の存在定理
これについてもまた
\begin{array}{ccc} N_*⊂N & N_*≠∅ \end{array}
「空ではない自然数の集合」という
同様の前提を採用すれば
\begin{array}{ccc} \exists M\in N & \forall n\in N_* & n≤M \end{array}
「上に有界(上限が存在する)」とする場合
(この M の存在が最大元が存在する根拠になる)
\begin{array}{ccc} \exists m\in N_* & \forall n \in N_* & n≤m \end{array}
「最大元が存在する」という結論が得られます。
(部分集合 N_* の中で m が全ての n 以上)
例外の確認
まず当然のことを確認しておくと
\begin{array}{ccc} N_* &=& \{ 0 \} \end{array}
これの「最大元」は 0 であり
\begin{array}{ccc} 0 & ≤ & n \end{array}
0 以外の自然数を含むなら
0 は最大元ではなくなります。
(つまり以降の話は \{0\} ではないとする)
上界の存在と上限の定義
↑ で話したように
\begin{array}{ccc} U &=& \{ m \in N \mid \forall n\in N_* \,\, n≤m \} \end{array}
「上に有界な部分集合 N_* 」には
「上界」と「上界の最小元 m 」が存在します。
そして ↓ のように
\begin{array}{ccc} m\in U &&\to&& m \in N_* \\ \\ 〇 &&{}&& ? \end{array}
m\in N_* であれば
「最大元は存在する」と言えるので
(上界の最小を持つ場合にそれが最大元になる)
この定義から
\begin{array}{ccc} m &\not\in& N_* \end{array}
「否定したい仮説」を得ることができます。
(直感的には明らかにこうならない)
最大元が存在しないという仮定
「最大元が存在する」ことを示すために
「間違いなく存在するだろう」という予想から
\begin{array}{ccc} m &\not\in& N_* \end{array}
このようになると仮定してみると
まず m が上界の要素であることから
\begin{array}{ccc} \forall n\in N_* & n≤m \end{array}
こうなることは確実だと言えます。
(これはただの上限の定義)
そして「 m は上界の最小元である」ことから
\begin{array}{ccc} m_{-1}+1 &=& m \\ \\ \mathrm{Suc}(m_{-1}) &=& m \end{array}
m_{-1} は確実に「上界ではない」ので
( 0 以外の自然数 m はなんらかの自然数の後者)
「 N_* に最大元が存在しない」場合
(より正確には m_{-1} は最大元ではないから)
\begin{array}{ccc} m_{-1} &≤& n_* \end{array}
このような n_* が
「 N_* の中に確実に存在する」ことになります。
(仮定に関係無く存在し得ることはただの事実)
念のため確認しておくと
\begin{array}{lcc} m&\in & U \\ \\ m_{-1} &\not\in &U \end{array}
仮に「 m_{-1} 以上の数が N_* に含まれない」なら
「上界 U の最小元」は m_{-1} です。
( n_* が N_* に無いなら m_{-1} は上界)
自然数の定義と上界の最小元
また「上限の定義」より
\begin{array}{ccc} n_* &≤& m \end{array}
これは確実にこうなるので
\begin{array}{ccc} m_{-1} &≤& n_* &≤& m \end{array}
これはこうなるわけですが
\begin{array}{ccc} m_{-1} &≤& m_{-1}+1 \end{array}
「この範囲にある m_{-1} 以上の自然数」は
「 m_{-1} と後者 \mathrm{Suc}(m_{-1}) 」しか存在しません。
(自然数の定義より必ずこうなる)
そして「 m_{-1} が上界ではない」以上
( m が上界の最小元であるため)
\begin{array}{ccc} m_{-1} &<& n_* \end{array}
n_* は「 m_{-1} ではない」ので
( n_*=m_{-1} とすると m_{-1} は上界)
\begin{array}{ccc} n_* &=& \mathrm{Suc}(m_{-1}) \end{array}
消去法で n_* はこのようになり
( m_{-1} 以上 m 以下の自然数は 2 つしかない)
\begin{array}{ccc} m&\in&N_* \end{array}
これは「 N_* に含まれる」ことになります。
( m_{-1} が上界ではないため)
前提から得られる結果と仮定の矛盾
まとめると
「最大元が存在しない」と仮定した場合
\begin{array}{ccc} m&\not\in&N_* \end{array}
「上限 m は N_* に含まれない」わけですが
(含まれるとすると m が最大元になる)
\begin{array}{ccc} m &=& \mathrm{Suc}(m_{-1}) \\ \\ m &=& m_{-1}+1 \end{array}
この前提から得られる
(これは仮定とは関係の無い事実)
\begin{array}{ccc} m&\in&N_* \end{array}
この事実と矛盾してしまうので
(上界の最小元の存在を認めるとこうなる)
「 N_* が最大元を持たない」
\begin{array}{ccc} m&\not\in&N_* \end{array}
この仮定は否定され
( N_* は上界の最小元を持たなければならない)
\begin{array}{ccc} \exists m\in N_* & \forall n \in N_* & n≤m \end{array}
結果、こうなると言えます。
( N_* の中に m が無いなら m_{-1} は上界の最小元)
